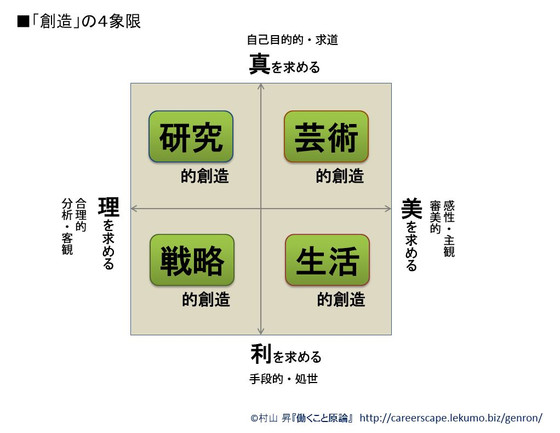王国一賢い男か・王国一ハンサムな男か
5.3.5
「王国一賢い男になるよりも、王国一ハンサムな男になるほうが魅力的だ。
なぜなら、知性を理解する洞察力を持っている人間よりも、
目を持っている人間の方がはるかに多いからである」。
ウィリアム・ハズリット(19世紀英国の批評家)が吐いたこの警句には、思わずにんまりと肯定させられる。
道を究めれば究めるほど、そこは細く深い世界になっていく。
必然、その世界を評価できる人間は少なくなる。
道を究めようとする者の最大の誘惑は、
「多くの人間に認められたい」という欲求かもしれない。
しかし、そうした欲求を満たしたいなら、道を究めるよりほかの術をとったほうがいい。
「大衆から人気を得る」というのは、少し別のところの才能なのだ。
* * * * *
江戸時代の文人、大田南畝(おおた・なんぼ)は、『浮世絵類考』の中で、
浮世絵師、東洲斎写楽についてこんな記述をしている。
「あまりに真を画かんとて
あらぬさまにかきなせしかば
長く世に行われず
一両年にして止む」
……あまりに本質を描こうと、あってはならないように描いたので、
長く活動できずに、1、2年でやめてしまった、と。
東洲斎写楽。寛政6年(1794)、豪華な雲母摺りの「役者大首絵28枚」を出版して、
浮世絵界に衝撃デビューした彼は、翌年までに140点を超える浮世絵版画を制作したものの、
その後、忽然と姿を消した。
東洲斎写楽のあの大胆な構図の「役者大首絵」は、現代でこそ、
高い美術的価値が付いている(残念ながら最初に高い価値を与えたのは海外の国であるが)。
ご存じのように、写楽の絵は、描き方がいびつ(歪)で、
あまりに歌舞伎役者の特徴をとらえすぎていた。
このことは、歌舞伎興行側・役者側からすれば好ましくないことだった。
彼らは「大スターのブロマイドなんだから、もっと忠実に、もっと恰好よく」を望んだ。
同時に、観客である庶民からもその絵は人気が出なかった。
お気に入りの役者のデフォルメされた絵など買いたいと思わなかったからだ。
版元の蔦屋重三郎は才能の目利きだったかもしれないが、
版元も商売でやっている以上、当然、多く売れるように仕向ける。
写楽に「もっと写実的に描けないか」と圧力をかけたことは容易に想像できる。
事実、「役者大首絵28枚」以降の写楽の絵はごく普通のものとなり、
明らかに生気を失くし、陳腐なものに堕していく。
写楽は非凡なる絵の才能を持ち、非凡なる絵を描いた。
無念なるかな、同時代の大衆はそれを評価できなかった。
写楽ほどの才能をもってすれば、
大衆好みのわかりやすい絵をちょこちょこと描いて、食っていくこともできたかもしれない。
しかし、それは自分をだますことになるという気持ちが強かったのだろう。
写楽のその後の人生は詳しくわかっていない。
一説には、人知れず画業の道を貫き生涯を終えたとも。
* * * * *
アメリカの音楽産業は1960年代からオーディオ製品の普及に伴って、一気に拡大を見せる。
音楽レコードはもはや一部の金持ちの趣味品ではなくなり、大衆商品になりつつあった。
その起爆剤になったのが、ロック音楽の台頭である。
1940年代からジャズ音楽界入りし、円熟の技が冴えるマイルス・デイビスもその渦中にいた。

以下は、『マイルス・デイビス自叙伝〈2〉』
(マイルス・デイビス/クインシー・トループ著、中山康樹訳、宝島社文庫)
からの抜粋である。
●
1969年は、ロックやファンクのレコードが飛ぶように売れた年で、
そのすべてが、40万人が集まったウッドストックに象徴されていた。
一つのコンサートにあんなに人が集まると誰だっておかしくなるが、
レコード会社やプロデューサーは特にそうだった。
彼らの頭にあるのは、どうしたら常にこれだけの人にレコードが売れるか、
これまで売っていなかったとしたら、
どうやったら売れるようになるかだけだった。
オレの新しいレコードは、出るたびに6万枚くらい売れていた。
それは以前なら十分な数字だったが、この新しい状況となっては、
オレに支払いを続けるには十分なものじゃないと思われていた。
1970年に『フィルモア・イースト』で、
スティーブ・ミラーというお粗末な野郎の前座をしたことがあった。
オレは、くだらないレコードを1、2枚出してヒットさせたというだけで、
オレ達が前座をやらされることにむかっ腹を立てていた。
だから、わざと遅れて行って、奴が最初に出なければならないようにしてやった。
で、オレ達が演奏する段になったら、会場全体を大ノリにさせてやった。
●
『フィルモア』に出ていたころ、ロックのミュージシャンのほとんどが、
音楽についてまったく知らないことに気づいた。
勉強したわけでもなく、他のスタイルじゃ演奏できず、楽譜を読むなんて問題外だった。
そのくせ大衆が聴きたがっている、ある種のサウンドを持っているのは確かで、
人気もあればレコードの売り上げもすごかった。
自分達が何をしているのか理解していなくても、
彼らはこれだけたくさんの人々に訴えかけて、レコードを大量に売っている。
だから、オレにできないわけがないし、
オレならもっとうまくできなきゃおかしいと考えはじめた。
●
オレには創造的な時期ってものが、いつだってあるんだ。
「イン・ア・サイレント・ウェイ」から始まった数年間は、
1枚1枚のレコードで、まったく違うことをやっていた。
どの音楽も、すべて前よりも変わっていたし、誰も聴いたことがないことをやっていた。
だから、ほとんどの批評家連中が手を焼いたわけだ。
連中は分類するのが好きで、わかりやすいように、
自分の頭のどこか決まった場所に押し込んでしまう。
だからしょっちゅう変化するものは嫌われるんだ。
何が起きているのか一所懸命理解しなきゃならないし、
そんなこと連中はしたがらない。
オレがどんどん変化しはじめると、やってることがわからなくて、
連中はこき下ろしはじめやがった。
だがオレには、批評家が重要だったことなんか一度もない。
やり続けてきたことを、そのままかまわずにやり続けるだけだった。
今だってオレの関心は、ミュージシャンとして成長すること以外にないんだ。
●
1971年には、ダウンビート誌でジャズマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれて、
バンドもグループ・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。
オレはトランペット部門でも1位になった。
オレだって賞をもらってうれしいのは事実だが、
特別大喜びするような類のものじゃないってことも確かだ。
音楽の中味と賞は、関係ない。
●
(1986年に)オレはホンダのバイクコマーシャルにも出たが、
そのたった一つのコマーシャルが、オレの名前を広めるという意味では
今までにやったどんなことよりも大きな効果があった。
黒人も白人もプエルトルコ人もアジア人も子供も、
オレが何をやってきたかをまったく知らない、オレの名前すら聞いたこともなかった連中が、
通りで話しかけてくるようになった。
チクショー、なんてこった! これだけの音楽をやり、たくさんの人々を喜ばせて、
世界中に知られた後に、オレを人々の心に一番強く印象づけたのが、
たった一つのコマーシャルだったなんて、クソッ。
今この国でやるべきことは、テレビに出ることだ。
そうすれば、すばらしい絵画を描いたり、
すばらしい音楽を作ったり、すばらしい本を書いたり、
すばらしいダンサーである誰よりも、広く知られて尊敬されるんだからな。
あの経験は、才能もなく、たいしたこともできない奴が、
テレビや映画に出ているというだけで、
スクリーンに現れない天才よりも、はるかに称えられ尊敬されるってことを教えてくれた。
* * * * *
純粋に己の創造を追求する者にとって、
心の奥の悪神はたびたびこうささやく───
「道を究めるなんていう高尚な生き方もなるほどけっこうだ。
しかし、賢くたって、深い世界を知ったところで、食えなきゃしょうがない。
食えなきゃ敗者だ。
大衆にモテることさ。食うのがラクになるってもんだ。
もう一度訊こう。
おまえさんは、“王国一賢い男”にも、“王国一ハンサムな男”にもなれる。
さぁ、どちらを選ぶかね?」と。