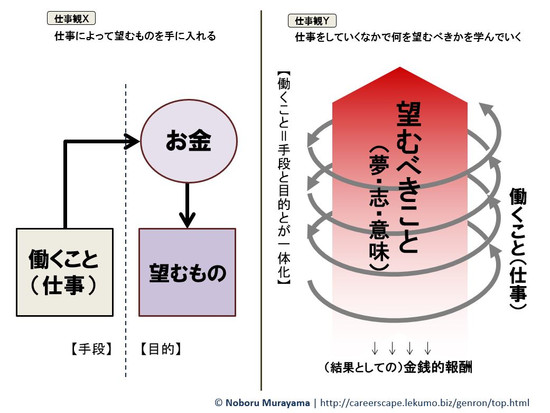自由であることの負荷
5.8.4
私は「プロフェッショナルシップ」(一個のプロであるための就労基盤意識)を醸成するための研修を行っている。それは“先端”を感じ取る仕事でもあるので、とても面白く、刺激的に、そして、ときに悲観の波に襲われながら、でも楽観の意志を失わずにやっている。
何の“先端”かと言えば、情報や技術の先端ではない。いまの時代に働く人たちの「心持ち」の先端である。私が行う研修プログラムは、働く意味や仕事の価値、個人と組織のあり方、を受講者に考えさせる内容なので、必然、彼らが内省し言葉に落としたものを私は受け取る。
顧客は主に大企業や地方自治体で、受講者はその従業員・公務員である。現代の日本の経済を牽引し、消費スタイルを形づくり、文化をつくる、いわば先導の人たちが、いま、心の内でどう働くこと・生きることについて考えているか、それを知ることは、流行という表層の波を知ることではなく、底流を知ることになるので、中長期にこの国がどの方向に変わっていくのかを感じ取ることができる。
◆「あこがれるものが特にない」
それでここでは最近の研修現場から感じることを1点書く。
研修プログラムの中で私は『あこがれモデルを探せ』というワークをやっている。これは世の中を広く見渡してみて、
・「あの商品の発想っていいな/あのサービスを見習いたい」とか、
・「ああいった事業を打ち立ててみたい」
・「あの人の仕事はすごい/ああいうワークスタイルが恰好いい」、
・「あの会社のやり方は素晴らしい/あの組織から学べることがありそうだ」
といった模範や理想としたい事例を挙げてもらい、その挙げたモデルに関し、具体的にどういう点にあこがれるのかを書く。そしてそれを現実の自分の仕事や生活にどう応用できそうかを考えるものである。
私の研修では、最終的に、自分の仕事がどんな意味につながっているか、自分の働く組織が社会的にどんな存在意義をもっているか、その上で、自分は職業を通して何をしたいか、何者になりたいかを考えさせるわけだが、それをいきなり問うても頭が回らないので、こうした補助ワークから始め、自身の興味・関心や、想い・志向性をあぶり出していく。
……さて、補助ワークとはいえ、これがなかなか書けない。
一応、ワークシートには3つのモデルを書く欄を用意しているが、がんばってようやく1つ書ける人、そしてついに1つも書けない人が、合わせて全体の2割~3割は出るだろうか。本人たちは不真面目にやっているふうでもなく、ヒントを出して思考を促しても、「いや、ほんとに、思い浮かばないんです」と当惑した表情をみせる。
「では、尊敬する人は誰かいますか?」と訊くと、「あぁ、それじゃ、お父さん」と言う。「お父さんのどんな点を尊敬しますか?」と訊くと、「自分たちを育ててくれたところ」と答える。「そのお父さんの尊敬する点を自分の生き方にどう取り入れられそう?」───「う、うーん。。。自分も立派に家族を養っていきたい」と、そんな調子である。この返答自体は無垢な気持ちから出たもので悪いとは言えない。ただ問題は、意欲を具体的に起こす思考ができなくなっていることだ。
ちなみに、彼らの年次は入社3年目から5年目、20代後半である。担当仕事はすでに一人前かそれ以上にできるように育ってはいるものの、「あこがれモデル」を想い抱くことに関しては、ある割合が、こうなってしまう現実がある。私は10年前からこの種の研ワークを取り入れているが、「あこがれが特にない/うまく抱けない」という割合は増えている傾向にあると感じている。
◆2年間の兵役が自由への意識を目覚めさせる
「あこがれる」という気持ちは、意欲を湧き起こし、意欲に方向性を与え、他の様子から学ぶ(「学ぶ」は「真似る」を由来とする)という点で、とても大事なものである。あこがれを起こせない個人が増えるということは、そのまま、社会全体の意欲の減退、方向性の喪失、学ぶ思考力の脆弱化につながっていく。
私たちは何にあこがれてもいいし、そのあこがれを目指すことで自分の力を引き出し、何になってもいい、という自由を手にしている。しかし、その自由の中で私たちはますます浮遊の度を強めている。
私がかつて企業で管理職をやっていたとき、部下に韓国人の男性がいた。彼はともかく20代の時間を惜しむように、会社内外でいろいろなことに挑戦をした。彼にいろいろと話を聞くと、そうした意欲は兵役中に芽生えたと言う。ご存じのとおり、韓国は徴兵制を敷いている。男性は一般的に20代のうちに約2年間の兵役義務を果たさねばならない。
能力も知識も感情も形成盛りの20代に2年間の服務生活。ある種の自由が奪われた状態が個々の人間に与える影響は小さいはずがない。彼は兵役中、むさぼるように読書をし、服務を終えたら何をしようこれをしようと想いが溢れたそうだ。
◆「~からの自由」と「~への自由」
幸いにも日本には徴兵制はない。自分の人生の時間は100%自分が自由に使える。しかし逆に、そうした有り余る自由に対して、私たちは戸惑ったり、敬遠したり、負担に感じたりと、どうも具合がよくないのだ。
「あこがれるものは特にない」、「やりたいことがわからない」、「会社の中で与えられた仕事をとりあえずきちんとやるだけ」、「そういえば働く目的って考えたことがない」……。目の前には自由という大海原があるにもかかわらず、防波堤に守られた湾の内にこもり、漕ぎ出すことができないでいる場合が多いのだ。
ピーター・ドラッカーは次のように言う───
「自由は楽しいものではない。それは選択の責任である。楽しいどころか重荷である」。 (『ドラッカー365の金言』)
また、エーリッヒ・フロムもこう指摘した───
「(近代人は)個人を束縛していた前個人的社会の絆からは自由になったが、個人的自我の実現、すなわち個人の知的な、感情的な、感覚的な諸能力の表現という積極的な意味における自由は、まだ獲得していない。……かれは自由の重荷から逃れて新しい依存と従属を求めるか、あるいは、人間の独自性と個性にもとづいた積極的な自由の完全な実現に進むかの二者択一に迫られる」。 (『自由からの逃走』)
フロムはこの短い記述のなかで2種類の自由につき触れている。つまり「~からの自由」と「~への自由」である。「~からの自由」とは個人を縛っていたしきたりや制度上の不自由から解放される自由をいう。そして「~への自由」は、解き放たれた個人が能動的に活用する自由である。
◆自由を敬遠する底には怠惰や臆病がある
学びたいものは何でも学ぶことができる、なりたいものには何でもなることができる(もちろん、そうなる努力をして運をつかんでのことだが)───こういう自由な環境下にありながら、つまり「~への自由」を大きく持ちながら、なぜ、私たちはそれを敬遠してしまうのだろうか。
その大きな理由の一つは、自由には危険やら責任やら、判断やらが伴うので、そのために大きなエネルギーを湧かせる必要があるからだろう。
人は、自由そのものを敬遠しているのではなく、それに付随する危険や責任、判断、エネルギーを湧かすことに対して、面倒がり、怖がっていると考えられる。
選ばなくてすむといった状況のほうが、基本的にラクなのだ。確かに、日常生活や仕事生活で、大小のあらゆることに対して、事細かに判断をしなくてはならないとしたら、面倒でたまらない。多くのことが自動的に制限的に決められ流れていくことが、実は望ましいといえる。
しかし、人生に決定的な影響を与える職業選択と、日々の仕事の創造において、その自由を敬遠するのは、一つの怠慢や臆病にほかならない。ここの手を抜いてはいけないのだ。
丸山真男は強く言う───
「アメリカのある社会学者が『自由を祝福することはやさしい。それに比べて自由を擁護することは困難である。しかし自由を擁護することに比べて、自由を市民が日々行使することはさらに困難である』といっておりますが……(中略)。
自由は置き物のようにそこにあるのではなく、現実の行使によってだけ守られる、いいかえれば日々自由になろうとすることによって、はじめて自由でありうるということなのです。その意味では近代社会の自由とか権利とかいうものは、どうやら生活の惰性を好む者、毎日の生活さえ何とか安全に過せたら、物事の判断などは人にあずけてもいいと思っている人、あるいはアームチェアから立ち上がるよりもそれに深々とよりかかっていたい気性の持主などにとっては、はなはだもって荷厄介なしろ物だといえましょう」。 (『日本の思想』)
私が研修を通して接している層は、大企業の従業員や公務員であり、はっきり言えば、いろいろな意味で“守られた層”の人たちである。
守られているがゆえに、その分、安心して十全に自己を開き、仕事を開いて、日本をぐいぐいと牽引していってほしいと願いたいところだ。フロムの表現を借りれば、「人間の独自性と個性にもとづいて積極的に」自由を活かしてほしい。しかし、現実は、「自由の重荷から逃れて新しい依存と従属を求める」傾向が強まっている。
◆個々が内面を掘り起こすことでしか世の中は善く変わらない
私はここで、日本のサラリーマンが「仕事を怠けている」と言っているのではない。「自由を活かすことを怠けている」のではないかと言っているのだ。私たちはそれこそ残業の日々である。うつ病が社会問題化するほど、ストレスもさまざまに抱えている。その面ではよく働いている。しかし、私たちが気づかねばならないのは、その働き過ぎは、フロムの指摘する“自由の重荷から逃れた新しい依存と従属”によって引き起こされているものではないかということだ。
私たちは、自分の仕事の在り方を決める自由を手にしている。そして、組織の在り方、事業の在り方、資本主義の在り方も自分たちで決められる自由を持っている。しかし、その正しい解を見つけ出し、実現するには相当の努力が要るので、それは敬遠し、誰かがやってくれるだろうことを期待して、とりあえず目先の自己の利益確保だけを考えて、現状体制に依存と従属をするわけである。
多少の愚痴や問題はあるけれど、その依存と従属の仕事で、毎月、お給料が振り込まれ、なんとなく生活が回っていくのであれば、ことさらに自由を使いこなす必要もない。まさに丸山の言う「アームチェア」的な居心地に身を置くことができれば、そこから立ち上がりたくなくなる状態が生まれる───私には、「あこがれモデル」を探せなくなった社員たちの姿をそこに見るような気がする。
かといって、私はこうしたことを批評するだけで終わりたくはない。私の目の前には、そうした問題の解決に身を投げる大海原が広がっています。だから私は、守られた環境のサラリーマン生活にピリオドを打ち、独立して教育事業への道を歩み始めた。自分の自由をもっと活かすべきと思ったからだ。
「世の中を悪い方向に変えるには、マス情報で事足りるが、世の中を善い方向に変えるには、1人1人の内面を粘り強く掘り起こしていかなければならない」───この教訓は私が大手出版社に勤めて得た最大の収穫の一つである。
そうしていまは、日本の企業・自治体の第一線で働く1人1人と、学びの場を通して対話や思索を交える仕事をやっている。目下の課題の一つは、「あこがれを抱けなくなりつつある若年層社員に、どうすれば思考の刺激を与えられるのか」。そもそも『あこがれモデルを探せ』は、働く目的を考える補助ワークだったが、その補助ワークの補助ワークが必要になってきたという状況でもある。しかしそれもやりがいのある仕事である。
いまの仕事は、日本のサラリーパーソンの「心持ちの先端を感じ取る」仕事だが、同時に、教育を通して、そうした人たちの「心持ちの先端をつくる仕事」でもある。
* * * * *
【補足】
『小林秀雄 全作品21~美を求める心』(新潮社)の中に「自由」と題された小稿がある。そこにおもしろい記述があった。英国人は、「自由」を意味する言葉を2つ持っているというのだ。すなわち、「リバティー(liberty)」と「フリーダム(freedom)」だ。
「リバティー」は市民の権利のように制度上で与えられている自由をいう。他方、「フリーダム」とはそういう社会的な外部から与えられる自由ではなく、まったく個人的な態度をいう。フリーダムとは、各自が所与のリバティーを努力して生かしながら、いかに、なにを行うかという自由を指すというのだ。だから、たとえば、芸術家の創造のフリーダムとはいうが、創造のリバティーとはいわない。リバティーはフリーダムという価値の基盤になるととらえてもいい。小林はこう書く───
「日本には自由という一語しかないのだが、(中略)別段不便も感じていない様である。自由主義者になるのには、自由という一語しかない方が余程便利かもしれない。原論の自由を与えよ、というプラカードの下に、いくら沢山な人が行進しようと、自分の苦心創作になる言論をだれも持っていなければ、自由の死骸を求めて、歩いている様なものだろう」。
この考察は、本文のエーリッヒ・フロムの箇所で触れた、2つの自由と符合する。つまり、「~からの自由」はリバティーであり、「~への自由」はフリーダムということだろう。いずれにせよ、後者の自由は難題である。