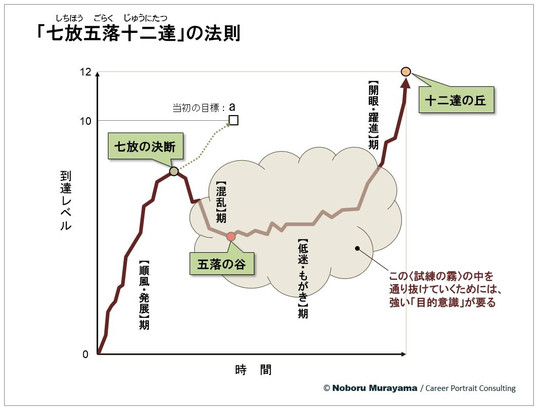セレンディピティ~チャンス感度の鋭いラジオになる
3.6.1
「チャンスは、心構えした者の下に微笑む」。
Chance favors the prepared mind.
――――ルイ・パスツール(細菌学者)
◆執念がチャンス感度を鋭くする。
科学の世界での偉大な発明・発見というのは、偶発の出来事がきっかけとなることが多いという。……ある日、徹夜明けのP博士は、ぼーっとしてA液の入ったビーカーにあろうことか、飲もうとしていたコーヒーを注いでしまった。すると、A液とコーヒーのカフェインが反応して思わぬ物質が発見された!とか、そんなような偶発である。
だが、それは本当に偶発なのだろうか? 「いや違う。そういったチャンスは自分が呼び込んだものなのだ!」―――こう主張するのが細菌学者パスツールだ。冒頭に挙げた彼の言葉を、科学者の多くは身で読んでいる。
2002年にノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊先生も自著『物理屋になりたかったんだよ』の中でこう書いている───
「たしかにわたしたちは幸運だった。でも、あまり幸運だ、幸運だ、とばかり言われると、それはちがうだろう、と言いたくなる。幸運はみんなのところに同じように降り注いでいたではないか、それを捕まえるか捕まえられないかは、ちゃんと準備をしていたかいなかったの差ではないか、と」。
私はこうしたことを次のように解釈している。
世の中には、実はチャンスがいっぱい溢れている。目に見えないだけで、そこにもあるしここにもある。それはたとえば、この空間に無数に行き交う電波のようなものだ。電波は目に見えないが、ひとたび、ラジオのスイッチを入れれば、いろいろな放送局からの音声が受信できる。感度のよいラジオなら、少しチューニングダイヤルを回しただけでいろいろと音が入ってくる。逆に感度の悪いラジオだと、ほとんど何も受信できないか、不明瞭な音声でしか聴くことができない。
一つの仕事に執念を持って取り組んでいる人は、その仕事課題に対する感度がいやおうなしに鋭敏になってくる。すると、チャンスをさまざまに受信しやすい状態になる。逆に、漫然と過ごしている人は、いっこうに感度が上がらない。だから、チャンスはそこかしこにありながら、それらを素通りさせるだけで何も起こらない。性質(たち)の悪い人になると、「自分にはいっこうに運がないのさ」と天を恨んだりする。
◆偶然をとらえて幸福に変える力は鍛えられる
こうした予期せぬチャンスを鋭くつかみ取る能力を表す単語が「セレンディピティ(serendipity)」である。「セレンディピティ」は、オックスフォード『現代英英辞典』にも載っている単語だが、まだ簡潔に言い表す訳語はない。
東京理科大学の宮永博史教授は、『成功者の絶対法則 セレンディピティ』の中で、セレンディピティを「偶然をとらえて幸福に変える力」としている。「ただの偶然」をどう幸福に導き、「単なる思いつき」をどう「優れたひらめき」に変えることができたのか、古今東西の科学研究の現場や事業の現場での事例を集めて説明してくれている。
また、セレンディピティを「偶察力」(=偶然に際しての察知力で何かを発見する能力)と紹介しているのは、セレンディピティ研究者の澤泉重一さんである。澤泉さんは、人生には「やってくる偶然」だけではなく、「迎えに行く偶然」があると言う。
つまり後者は意図的に変化をつくり出して、そこで偶然に出会おうとする場合のものだ。その際、事前に仮説をいろいろと持っておけば、何かに気づく確率が高くなる。基本的に有能な科学者たちは、こうした習慣を身につけ、歴史上の成果を出してきたと、彼は分析している。
さらに、パデュー大学のラルフ・ブレイ教授によれば、セレンディピティに遭遇するチャンスを増やす心構えとして、「心の準備ができている状態、探究意欲が強く・異常なことを認識してそれを追求できる心、独立心が強くかつ容易に落胆させられない心、どちらかというとある目的を達成することに熱中できる心」らしい(澤泉重一著『セレンディピティの探究』より)。
いずれにしても大事なことは、セレンディピティは「能力」という意味合いを含んでいることだ。これは能力だから強めることができるという発想にもつながる。単に「棚からボタ餅」でぼーっと幸運を待っている状態ではないのだ。
〈Keep in Mind〉
執念が「チャンス感度」を鋭くする