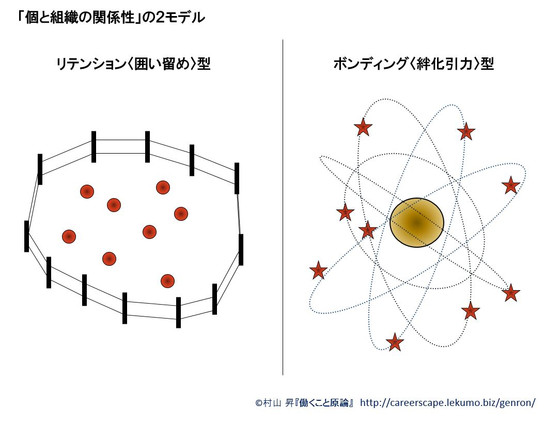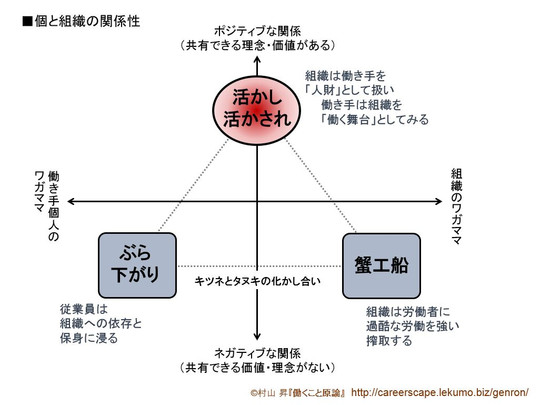ヒトを全人的に育てる思想~ホンダのOCT
4.3.2
◆「やりたいやつは手をあげろ!」「はいっ!」
あるとき、ホンダ(本田技研工業)のマネジャークラスの方にお会いしたとき、“OCT”なる言葉を聞いた。
―――「OCT(オン・ザ・チャンス・トレーニング)」
「人は育てられるのではない、自ら育つ」というスタンスに立ち、会社側はそのための環境とプロセスを整えること、これがホンダの人財育成の根本思想であるという。
確かに、ホンダの歴史をみても、たとえば、1959年(創業11年目)、伝説の「マン島TTレース」参戦では、メカニックもライダーも全員20代。人選も「やりたいやつは手をあげろ!」「はいっ!」で決まった。同じく59年、本田と藤澤の経営陣は、鈴鹿工場建設のすべてを30代の一人の課長(白井孝夫氏)にあっさりと一任した。白井課長は、その勉強のために「おまえ、しばらくヨーロッパに行って来い」と言われたそうだ。
また、ホンダの有名な文化として、
『三現主義』:
・現場に行け
・現物、現状を知れ
・現実的であれ
『自己申告主義』:
研究や開発は、アイデアを出した人がそのテーマの責任者となる。いわゆる“言い出しっぺ”がリーダーを張るのだ。年次は関係ない。
こうしたことがベースになって、「チャンスの中でヒトは勝手にしぶとく育っていく」というホンダのOCTが、人づくり思想として組織の中に深く根を張っている。これは思想であって、人財育成戦略とか、施策などという表層で移り変わるものではなく、組織員一人一人の気骨に染み込んだDNAになっているように感じる。
その大本である本田宗一郎も、
・「創意発明は天来の奇想によるものではなく、
せっぱつまった、苦しまぎれの知恵である」
(だから、人を2階に上げておいて、はしごをはずせば、いい知恵がわく)
・「見たり聞いたり試したりの中で、試したりが一番大事なんだ」
・「やりもせんに」
(やりもしないで、机上の知識でものの可否を断ずるな)
など、いろいろな語録を残している。
◆全人的・全体的に仕事を任されることで「自分の仕事」になる
私は新卒で最初、文具・オフィス用品メーカーに入り、商品開発を担当した。入社直後からいきなり担当商品を割り当てられ、プロダクトマネジャーとして、企画立案から試作品づくり、デザイン検討までを行い、製造、流通、広報・広告、アフターサービスそれぞれの工程の専門スタッフをチーム化して、夢中(霧中)で働いた。この会社には3年弱在職し、いくつかの商品を世に送り出すことができた。結果的に、ここでの経験がその後の私の仕事上の姿勢や考え方のほとんどを育ててくれたといっても過言ではない。
私の場合、職業人として何年も経ってから、ようやく財務の読み方やマーケティング、戦略論の勉強をした。「SWOT」だの「5 Forces」だの、そうした思考フレームは、どうも現実味の迫力に乏しく、ひとつひとつの知識が「ギスギスとやせて」いて、腹ごたえがないように思えた。後になってそれらは、物事を体系的に整理し、関係者一同が共通了解を得るために必要な道具・方便であるとことに気づいた。
他方、ひとつの完結するプロジェクトなり、大きな仕事単位をどっさり任されることは、全人的に、全体的に取り組まねばならない奮闘であって、それは格好の体験学習、コミュニケーション機会、修羅場、歓喜の瞬間を与えてくれる。その意味で、実に「ふくよか」なのだ。こうしたふくよかな機会をもらってこそ、断片的な知識や技術も真に活きる。
現在、世の中のさまざまな研修プログラムや教育施策は細分化の流れにある。これはビジネスがどんどん高度に細分化(分業化)し、専門的な業務処理能力が欠かせないことに呼応している。だから会社側も、テーマが細分化されたスキル研修や知識セミナーに多くの従業員を行かせる。しかし、業務処理能力を即効的に身につけさせるという対症療法的な教育に偏っていると、「知識でっかち」「技能でっかち」の人間ばかりを増やす結果となり、全人的・全体的に仕事を動かせる人間が出てこなくなってしまうことを意識しておかねばならない。
できるだけ若い年次のころに、仕事を包括的に任されることを経験しておいたほうがよい。断片的な知識と技術をある程度身につけさせ、一人前半になったころに丸ごとを任せるという順序ではない。全体的に仕事を動かし責任を持つという経験は、早ければ早いほど、その人の成長を早め深める。20代のころのほうが、丸ごと任せるにしても仕事規模が小さいので、実際、組織としてもやりやすいだろう。ともかく、その任された丸ごとの仕事を「自分の仕事」として引き受けることを肚に覚えさせることが肝心なのだ。
まだ20代だからといって、部分部分の仕事を切り売り的に任せることでは、結局、部分しか考えられない肚の器の小さい人間ができてしまう。任された仕事を「自分の仕事」としてではなく、「それは会社の仕事」として、どこか第三者的に処理すればいいとする肚構えになってしまうきらいがあるのだ。私は働くマインドや観の醸成研修を主に実施しているのでよくわかるが、年齢が30を超えるころには、人はマインド・観が相当に固まってしまっていることが大半で、そこからの意識変革は難しいことを実感している。
◆全体論的な視点からのヒトの育成
還元論(あるいは機械論)と全体論というのが科学の概念にある。
還元論は、物事を基本的な1単位まで細かく分けていって、それを分析し、物事をとらえるやりかたである。人間を含め、自然界のものはすべて、部分の組み合わせから、全体ができあがっているとみる。西洋医学は基本的にこのアプローチで発展してきた。胃や腸などの臓器を徹底的に分解することで、さまざまな治療法を開発するのだ。
他方、胃や腸など臓器や細胞をどれだけ巧妙に組み合わせても、一人の人間はつくれない、全体はそれ一つとして、意味のある単位としてとらえるべきだというのが全体論である。東洋医学が主にこのアプローチである。
この両方は、どちらかが良い悪いではなく、バランスが必要だ。
専門特化された技能研修や知識セミナーは、還元論アプローチである。一方、ホンダの『OCT』は、全体論アプローチである。医療の世界では、東洋医学への見直しが高まっているように(ガンと共生する考え方や、漢方薬、ヨガなど)、人財育成も、全体論的な角度からの見直しが必要である。それは小難しいことではなく、どんとチャンスをどんと与えることである。チャンスを与えられ目をかけられたときの10代や20代の能力発揮、そして成長には驚くべきものがある。