ルイス・マンフォード『現代文明を考える』
◆smartばかり増やし、thoughtfulを増やさない教育
現代が変化・スピードの時代であることは誰しも否定しようがない。
そのため、変化に押し流されないよう個人も組織も常に最新の情報の摂取に忙しい。
そして何事もスピーディーに行動することを求められる。
時代の先を読み、迅速に反応できる人間が、優秀だと評価される。
(MBA学生をしていたとき、席を並べた同級生たちもそんな類の人財たちだ)
確かに彼らは時代の先読み感覚はあるし、頭の回転も行動も早い。
知識や技術もハイクラスのものだ。
しかし、彼ら(私自身も含めて)の弱いところは、
「史観」を持って自分たちの置かれた状況を見つめ、物事を解釈することだ。
経営者・ビジネスパーソンに限らず、第一級の人間は、独自の史観を内面に醸成している。
そして、表層の波のごとく変化する現在の出来事を長い時間軸から俯瞰してとらえ、物事を判断する。
いまの教育は、
時流に対応できる「smart=利口な」人間を増やしてはいるが、果たして、
時流がどうあれ、どっしりと思索のできる「thoughtful=思慮深い」人間をつくっているだろうか。
史観というものは易々と教育できるものではないし、
そもそも「史観はこうあるべきだ」という正解もないから、教育すべきでもない。
しかし、大人たちは、若い世代にさまざまな刺激や啓発を与える任務を負っている。
そのために大人ができることは、歴史的視点から考える材料や機会を若い世代にどんどん与えることだ。
(どのような史観を醸成させるかは、あくまで本人による)
私はMBA教育にはさほど感動はしなかったが、
それでも「経営哲学」という科目で、渋沢栄一の『論語と算盤』や
マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などを教材として
資本主義を歴史の視点から再考させてくれたことには、いまもって感謝している。
(*そのことについては下の記事をご参考に)
「伊丹先生が試みたもの・・・MBA教育の中の“徳育”」
ああいった学びがなければ、いまだに私は、資本主義を無条件に漫然と受け入れるだけで、
資本主義に使われる人間になっていただろうと思う。
資本主義の毒の部分を知って、その上で肯定する―――その理解次元に立てたことは大きな成長だった。
* * * * *
◆人類の最初の恩人はプロメテウスかオルフェウスか
さて、そんなところから、この「滋養本」のカテゴリーでは以降数回にわたって
文明的視座から書かれた本を紹介していく。今回は、
ルイス・マンフォード『現代文明を考える』
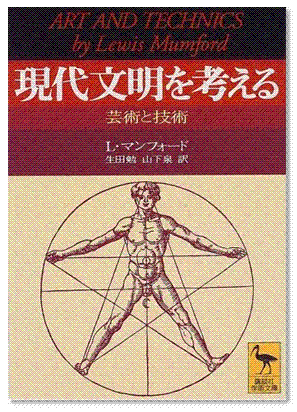
(生田勉・山下泉訳、講談社) である。
本著は、米国の文明批評家であるマンフォード(1895-1990)が、
1951年にコロンビア大学で行った講演をまとめたものである。
原題が『Art and Technics』とあるとおり、
芸術と技術の2つから文明をとらえていく。
マンフォードはそこで、
ギリシャ神話に出てくるプロメテウスとオルフェウスを比喩として用いる。
大方の見解として、プロメテウスは、
人間に最初に火をもたらした神であり(火は総じて道具や技術の意味を含む)、
人間が野生動物から分離していく発展の源をつくったとされている。
それに対し、マンフォードは
「いや、オルフェウス(竪琴の奏手、ここの文脈では芸術・表象の意味)こそ
人間の最初の教師、恩人であったのだ」と反論をする。
人間を最初に人間たらしめたものは、道具を使うという技術(プロメテウス)であったのか、
それとも、形態や意味を表象する芸術(オルフェウス)であったのか、
それは大いに議論が出るところだが、いずれにしても、
人類の文明の発展(あるときには、後退とか停滞とか破壊があるだろうが)には、
2つの推進力―――プロメテウス(技術)的な推進と、オルフェウス(芸術)的な推進が絡んでいる。
同時に付け加えるならば、この2つの推進力は一人の人間の内にも同居する。
◆人間を置き去りにして技術だけが勝利した
マンフォードはどちらの力が優で劣か、ということを論じない。
かつてその二つは表裏一体となって睦まじい関係にあったが、いつしかその二面は剥ぎ裂かれてしまい、
双方が均衡を欠いていることが現代の危機であると指摘する。
均衡を欠くとは、すなわち、プロメテウス(技術)の肥大化・暴走化と
オルフェウス(芸術)の衰弱化・病弊化だ。
「機械の誇りとする能率にもかかわらず、
またエネルギー、食糧、素材、製品がありあまるほど豊富なのにもかかわらず、
質の面では今日の日常生活はそれらに見合った改善がなされず、
文明のなかで充足し栄養十分な大衆が、
情緒的不感症と精神的冬眠、無気力と萎びた願望の生活を送り、
近代文化の真の潜勢力(ポテンシャル)に背を向けた生活をしているのです。
まさに『芸術は貶(おとし)められ、想像力は拒まれ、戦争は国民を支配した』
(注:ウィリアム・ブレークの言葉) のです」。
人間性を失くした技術の肥大と暴走は、同時に、芸術の衰弱と病弊を呼ぶ。
「社会が健全なときには、芸術家は社会の健全性を強めますが、
社会が病んでいるときには、同じようにその病弊を強めます」。
マンフォードも各所で指摘しているのだが、
技術と芸術は単純な二元論で片付けることができない。
もし、これらが単純な二元対立でとらえられるなら、
一方の技術の暴走は、もう一方の芸術の復興によって修正することができるはずだ。
―――しかし、残念ながらそうはならない。
芸術はいったん崩壊の流れに乗るや、みずから崩壊の度を強めていくのだ。
「その(芸術の)運動自体は、崩壊作用をみずからの栄養分としており、
まさにその崩壊作用に著しく規定されているため、精神の根底から変化しないことには、
その運動が新しい平衡と安定を私たちの生活にもたらすことはできまい」。
これは、いみじくもゲーテが「文学は人間が堕落する度合いだけ堕落する」と喝破したことと共鳴する。
確かに、昨今の芸術――ここで言う芸術とは、芸術家による創作活動だけではなく、
すべての人が情念の発露として行う表現活動まで含める――において、
表現する道具や手法などがそれこそ技術の発達によって洗練されたにもかかわらず、
出来あがってくるものは、神経質でギスギスと痩せたものばかりだ。
道具や手法などが未発達で粗だった時代のほうが、芸術ははるかに健やかさとふくらみをもっていた。
また、真の芸術の衰退は、人びとがそれを求めなくなることで加速される。
「真の芸術家はやむにやまれぬものを描き、書き、作曲するもので、
同時代人を喜ばせることは、二次的な問題にすぎないのですが、
かれは同時代人のかれへの興味、悦び、直観的反応によって、いっそう努力するよう促されるのです。
私の親しい友マシュウ・ノヴィッキが建築についてよく言っていたことですが、
『偉大な依頼者こそ偉大な建物の制作に不可欠である』という言葉は、
他のどんな芸術形式にもあてはまるように思われます」。
私たちは、技術を「富」の増幅と獲得に用いるばかりである。
確かにそのことによって、先進国では物が増え、娯楽が増え、平均寿命は延びた。
現代において、技術だけが勝利しているように思える。
芸術は縮み、人間は技術の配下に置かれる状況が生まれている。
この事態を健全な状態に切り返す手立てはいったい何なのか?
マンフォードは言う――――
「救いの道は、人間個性を機械へ実用的に適応させることにあるのではなく、
機械はそれ自体、生活の秩序と組織の必要から生まれた産物ですから、
機械を人間個性に再適応させることにあるのです。
つまり人間類型、人間的尺度、人間的テンポ、とりわけ人間の究極目標が
技術の活動と進行を変革しなければなりません。…(中略)
人格のない技術によっていまやまさに枯渇させられた生気とエネルギーとを、
もう一度芸術のなかに注ぎなおさなければならない」。
結局のところ、人間が技術を司るのである。
結局のところ、人間が芸術を司るのである。
技術の自己肥大化、芸術の自己病弱化に人間が振り回されているのが重大問題なのだ。
そのために、私たち人間は、技術の主人となれ、芸術の主人となれ、
そのために叡智を集結させて文明の流れを修正せよ、これがマンフォードのメッセージである。
* * * * *
◆大きなシステムの中で部品化する人間
しかし、技術の主人となる、芸術の主人となることは、そう簡単な話でない。
私たちは今日、標準化、大量生産、大量消費、分業、カネがカネを生む経済システムに
よって“生かされている”。
もっと多くを欲し、もっと多くを生産する。
もっと速く生産し、もっと速く消費する。
そうして工場を稼働させ続け、拡大再生産回路を絶たないようにする。
これこそが社会を潰さず、企業を潰さず、個人の生活を潰さないための唯一の方法―――
現代文明は、ブレーキもハンドルもなくアクセルしか付いていない暴走車に
いまや何十億人という人間を乗せて走っているのだ。
大量生産・大量消費・拡大成長・競争原理を前提とした経済は、
必然的に、仕事の分業化を押し進める。
仕事の分業化は、働く個人の技能的部品化・知能的部品化を意味する。
チャーリー・チャップリンの映画『モダンタイムス』(1936年)は、
工場労働者が単純作業にまで分解された仕事を黙々とこなし、
生産機械の一部になっていくことを痛烈に批判したものであるが、
これをいまのビジネスパーソン(ナレッジワーカー)たちが観て、
「かわいそうになぁ、そりゃあんな単純な肉体労働を歯車のようにさせられちゃ
人間疎外にもなるよ。昔はひどかったな」と思うかもしれない。
しかし、よくよく考えてみるに、
チャップリンが描いた当時のブルーカラーも、
現代の大企業オフィスで知的労働に関わるホワイトカラーも問題の本質は変わっていない。
単純な肉体作業が多少複雑な知的作業に取り替わっただけの話であって、
依然一人の働き手が、大きな利益創出装置の中の歯車であることには変わりがない。
私は主に企業の従業員を対象に研修をしているが、
新入社員であっても、3年目、5年目社員であっても、そして部課長ですら、その多くがが
「(生計を立てるため、というほかに)働く目的を明確に持っていない」、
「夢・志を描けない」、「働きがいが見出せない」、
「10年後どうなっていたいか、特に想いはない」……という状況だ。
このことは、過度に進む仕事の分業化と関連がある。
自分のやっていることが、全体とどう結びついているかが見えにくい、
自分のやっていることが、末端のお客様とどうつながっているかが実感しにくい、
自分のやったことで、直接お客様から「ありがとう」を言われたことがない、
自分のいまやっていることは、会社からの異動辞令が出ればまた変ってしまう、
自分に任された範囲のことをきちんとやっていれば、月末に給料が振り込まれる……
そんな状況で働いて、
働く目的や意味を見出せ、将来を描けというのは、酷な話かもしれない。
人間は、自らの仕事に全人的に関わらないかぎり、
そこに働きがいや意味を付与することは難しい。
◆手仕事の職人という理想形
マンフォードは労働者の理想、そして技術と芸術のよき均衡を19世紀中葉までの手仕事の職人に見る。
―――「かれ(職人)は自分の仕事に時間をかけ、自分の身体のリズムに従ってはたらき、
疲れれば休息し、経過をふり返っては工夫し、
また興がのったところでは、ためつすがめつ、あれこれ手をかけていました。
ですから仕事はあまりはかどりませんが、かれがそれに費やした時間は、真に生きた時間でした。
職人も、芸術家とおなじように、
自分の仕事に生き、仕事のために生き、仕事によって生きたといえます。
はたらく報酬も、そうした活動そのものにもともと備わっているもので、(中略)
かれ自身が製作工程を支配する親方であるという事実は、
人間的尊厳の大きな満足であり、その支柱でもあったのです。
手仕事のもうひとつ報いられた点は、
職人がさらに技術的に熟達すれば、仕事の操作から仕事の表現という面に移行できたことです」。
私自身、大企業の管理職を辞め、自営で独立した。
個人事業は苦労も多いし、障壁も多いが、仕事には格段の充実を得るようになった。
それはとりもなおさず、自らの仕事の全体を掌握する主人になったからだ。
コンサルタントという知的サービス業ではあるが、それは職人的手仕事と似ている。
自分を全体的に使って、仕事を全体的に動かしていく。
自分の信ずるところの想いを事業という形に変えるという営みは、
技術と芸術の相互の掛け合わせなしには実現されない。
技術は芸術を高め、芸術は技術を刺激する。
そして技術と芸術は、自分の想いをどんどん進化・深化させてゆく。
そのやり応えを一度でも知ったなら、とてもサラリーマンには戻れない。
私は周囲の骨のある人間には、常にこう勧めている―――
ともかく生涯に一度でも、自分の事業をやってみなさいと。
ちなみに、19世紀中葉に活躍し、アーツ・アンド・クラフツ運動の中心的人物だった
ウィリアム・モリスも職人的手仕事を理想的な労働とした一人であるが、
彼は著書『ユートピアだより』の中で、
有用な仕事は3つの希望を与えると言っている。
その3つとは―――
「休息という希望」、「生産物という希望」、「仕事自体楽しいという希望」である。
確かに、自らの意志の下で行う職人的手仕事という労働はひとつの理想形ではある。
しかし、この現代社会において、
そして地球人口が70億人を超えそうな状況において、
すべての人間が職人的手仕事に従事して世界経済を回していくわけにはいかない。
私たちはやはり大量生産・大量消費、分業制、企業組織、金融システムといったものを
利用しながら人類を食わせていかねばならないのだ。
しかし人間がそれらの下僕になってしまってはいけない。
その解決のための決定打は何なのか―――!?
◆1人1人が1日1日の小さな決断をたくさん積み重ねた結果、流れが変わる
マンフォードはきちんとそのことについて言及している。
しかし、その決定打というのは、起死回生の一発逆転満塁ホームラン!のような
即座の劇的な方法ではない。
それは、一人一人が“人間味”を取り戻すこと、
生物全体、人間全体へと関心を方向転換させること、
内なる自分を見つめ、耳を傾け、心中の衝動と情動に応える習慣を身につけること―――
だと彼は言う。なぜなら、文明の流れの全面的変化は、
「ある独裁的命令で即座に生じるのではなく、
新しいアプローチや新しい価値観の傾向や新しい哲学などから生じる
一日一日の小さな決断をたくさん積み重ねた結果」もたらされる(されてきた)からです。
そしてマンフォードは、絶対神を崇めるキリスト教思想よりも、
自然と共生し、個々の人間の自制的生活を促すという意味で東洋思想への期待をにじませている。
……そう聞くと、
「なんだ、結局は一人一人の人間が慎ましく変われということか。平凡な答えだ」と
思う人が多いかもしれない。
しかし、そうした答えを大勢が見くびっていく先には、文明の衰退があるだけだ。
「一人一人の人間が叡智を湧かせて変わる。それこそが世界をよく変える唯一確実な道」
―――平凡だがこれほど偉大な答えはない。
超一級の学者が常にそうであるように、ルイス・マンフォードは、
大きな問題に独自の視点を与え、表現を凝らしてそれを照らし出す。
そして、一貫して人類の叡智を信じ、強い楽観主義に基づいて聴衆の心に呼びかけをする。
この本には、部分部分でいろいろなことを考えさせてくれる指摘や考察があるので、
是非一度読んでみてください。





