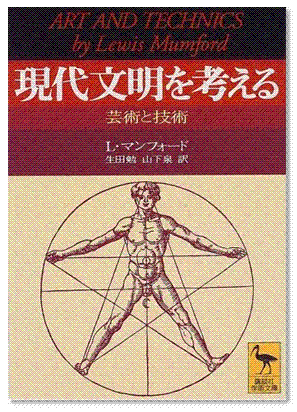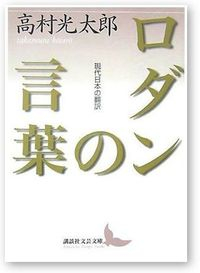ノーマン・カズンズ『人間の選択』
その道の「よきロールモデル」を持つことが欠かせない。
私は20代後半から30代初めにかけてビジネス誌の編集部で
記者・編集者として精力的に仕事をした。
雑誌名や自分の名刺には「日経」の冠が付いていたので、
取材のアポイントはどんな企業でも簡単に取れ、
日経のビジネスジャーナリストとして、半ばもてはやされ、日々面白く記事を書いていた。
記事の企画を立て、取材をし、締め切りまでに原稿を書く。
そのことにおいては、私はそこそこうまくできた記者であったと思う。
しかし、ただそれだけであった。
日々、月々、社会の表層に浮き立つ波(ときに泡)を追って、
それを経済・経営の切り口から読者に受けるように面白く書く。
それはそれで熱中できる仕事だったのだが、
5年経ったある日、過去の自分の記事をいろいろと見直してみた。
……バブルが起こればバブルを助長するような記事を書き、
バブルがはじければ誰が悪いんだと犯人探しの記事を書く。
ヒット商品が出れば、後付け分析のような形で賞賛記事を書き、
倒産会社が出れば、後付け分析で「失敗の研究」記事を書く。
あぁ、自分が夢中になってやってきたことはこんなことだったのか。
“情報狩り”の仕事が、「いい/わるい」という問題ではない。
ただ、私はそれ以上そうした狩りを仕事として続けたくなかった。
私は一角(ひとかど)のジャーナリストになる前にキャリアのコースを変えた。
結局その出版社には7年間勤めたのだが、考えてみれば、当時、
ジャーナリストとして「よきロールモデル」のような存在を持っていなかった。
きょう紹介するノーマン・カズンズという人物を知ったのはそれから随分後のことになる。
彼を早くから知っていれば彼をロールモデルとして、
もっとジャーナリズムの道で精進のしようがあったのではないかといまでも思う。
* * * *

さて、それでは今回の本;
ノーマン・カズンズ『人間の選択~自伝的覚え書き』
(原題:“Human Options”)
松田銑訳、角川選書、1981年
ノーマン・カズンズ(Norman Cousins、1915-1990年)は
米国でもっとも著名なジャーナリストの一人である。
1934年に『ニューヨーク・イブニング・ポスト』紙に入社した後、
1939年、文学評論誌『サタデー・レビュー』に移り、
1942年から1971年まで約30年間編集長を務めた。
彼の手腕により、同誌は米国内で最良の書評欄を誇る総合雑誌へと成長し、
発行部数は2万部から65万部までに飛躍した。
カズンズは「ペンの人」であると同時に、行動の人でもあった。
ケネディ大統領やローマ法王ヨハネス23世の依頼で
フルシチョフをモスクワに訪ね東西間の意志疎通を助けたり、
広島の原爆乙女たちやナチの生体実験に供されたポーランドの女性たちを
治療のためにアメリカに招いたり、
世界連邦協会の会長として国連強化運動の先頭に立つなど、
反戦平和主義者、コスモポリタン(世界市民)として生涯さまざまに駆け回った。
広島市特別名誉市民。「アルバート・シュバイツァー賞」受賞。
本書は、題名のとおり、人類がこのかけがえのない地球上で生き残るために
どのような選択をするか、もっと厳密に言えば、
どのような選択を生み出していこうとするのか、を問うものである。
カズンズの言葉の底流にあるのは、
力強い楽観主義と人間の英知を最終的に信頼する心である。
世を覆うペシミズム(悲観主義)、シニシズム(冷笑主義)の風潮を徹底的に嫌った。
○「進歩は、進歩が可能であるという考えから始まる。シニシズムは、退却と敗北が不可避であるという考えから始まる」。
○「要するに、自由の大きな問題は、自分自身を歴史的な意味で軽視する個人である。自由の敵は誰か。それは世界征服のイデオロギーと核兵器で武装した全体主義の大国だけではない。敵は大勢の人たちである。それは、世界について考えることがあるとすれば、自分の生きている間、世界が無事にこわれずにいてくれることだけというような人たちである。敵はまた、自分自身が無力であることを信ずるだけでなく、さらにその考えを宗教のように信仰する人である。……そういう人は良心を呼び覚ます人ではなくて、良心の鎮痛剤を売る薬剤師である」。
○「我々アメリカ人は、必要な物はみな持っているが、一番大切な物を欠いている。それは、考える時間と考える習慣である。思考は人間の歴史の基本的なエネルギーである。文明を組み立てるのは、機械ではなくて、思考である」。
○「権力と無神経と無知とが一つになると、人類の運命はいつも危機に瀕する」
○「我々は破壊性よりも、むしろ感覚麻痺を特色とする時代に生きている。人々は不合理なものと妥協する癖がついてしまった」。
カズンズは、歴史を成り行きやあきらめや鈍感で形成させるな、
思考や意志で形成していけ、と強く叫ぶ。
その思考や意志は少数のリーダーだけが持てばよいのではなくて、
地球上に生きる1人1人の人間が待たねばならない。そうすることで、
人類自らの歴史の運命をつくる選択肢は、人類自らがつくり出せるのだと言う。
そしてそれには忍耐を伴う。
○「新しい選択を創造し、その選択を行う能力こそ、人間の独自性の主要な一つである」。
○「大局から見れば、歴史の動きは将来も常に人間の願望に結びついているであろう。大きな原動力となるのは、我々の夢であって、我々の予言ではない。夢は人間を動かす。本当にいい夢ならば、偶然とパラドックスに打ち勝つことができ、その終局の成果は、心に詩を持たない人々の現実的な計画よりも、はるかにゆるぎないものであろう」。
○「歴史は冷厳な事実だけによって作られるものではない。むしろ感知できない、無形のものによって作られる」。
○「もし万一核戦争が起こるとしたら、それが不可避だからではなく、十分な数の人々がそれを避ける努力を払わなかったから起こるのである。その時になって嘆かれるのは、歴史の非情さではなくて、我々が一つしかない命につけた値段の安さであろう」。
○「人の命を支える品物や、人生を高貴にし、拡大しようとする企てにくらべて、銃はずっと手っ取り早く目的を達成することができる」。 「英知の発揮は、力の発揮ほど手っ取り早くはいかない」。
カズンズは、2つの世界大戦の時代を生きている。
彼は反戦主義者であり、戦勝国アメリカを賛美しなかった。
義援金を募り、広島の原爆乙女たちを治療のために訪米させたことは冒頭に述べたが、
彼は終戦4年後に広島を訪れ、被災地・被爆者を取材し、
『サタデー・レビュー』誌にルポルタージュ「4年後の広島」を掲載した。
その取材の際の写真が本書にも何枚か掲載されている。
彼は人間に視点を置く、コスモポリタンであった。
○「国家に属していれば、国家という代弁者がいてくれる。宗教に属していれば、宗教という代弁者がいてくれる。経済的、社会的体制に属していれば、経済的、社会的体制という代弁者がいてくれる。しかし人類に属しているという点では、人間の代弁者はいない」。
○「歴史家たちが何と言おうと、人間の時代はこれまで一つしかなかった。それは原始人の時代である。もし文明人の時代が訪れるとしたら、その始まりのしるしは、自分が全世界の人類の一員であり、その人類は、世界的に何が必要であるかを知り、その必要を充たす世界的制度を作りたいという願望と、それを実現する能力を持っているという政治的、思想的、精神的自覚であろう」。
○「宇宙の他の場所に生命が存在する可能性の話になると、我々は目を輝かすが、地上の生命の持つ可能性の話になると、目隠しをする」。
○「生命が貴重なのは、それが完全性に達し得るからではなく、人類が完全性という観念を理解できるからである」。
○「自分の道徳的能力を完全に発揮し切らない人は、心の安らかさを得ることはできない」。
『サタデー・レビュー』誌は、元々、
『サタデー・レビュー・オブ・リタラチュア』といい、文学評論誌であった。
したがって、カズンズの評論も文学に向けたものが多い。
○「我々は、人々が自分自身になることを恐れ、心の奥底の感情の純粋さよりも、ドライな、派手な外見を好むらしい時代に生きている。技巧的であることが持てはやされ、素直な感情は嫌がられる。善意の人と呼ばれるほど、沽券にかかわることはないというように見える。今日の文学には、人間本来の善性に関するテーマが驚くほど欠けており、人間がまじり合って生きる上の、もっとも力強い事実に何らのドラマティックな力も認めてはいない。現代の価値は見せかけだけのたくましさ、野放図な暴力、安っぽい感情に傾いているが、そのくせ我々は、若者たちが人をいじめ殺しておいて、面白いからやったとか、別に悪いと思わずにやったとか告白すると、ショックを受ける」。
○「現代の重大な病弊の一つは、ソフィストケーション(技巧化)が常識よりも尊重されるらしいことである。言葉は本来の率直な意味を失って、飴細工のよういへし曲げられる。観念の細工の方がまともな内容よりも重大なことであるらしい」。
○「言葉は単なる手段ではなくて、環境である。それは社会の哲学的、政治的条件付けの不可欠の一部である。言葉には崇高にする力、非難する力、増大させる力、迷わせる力、賛美する力、貶(おとし)める力があるが、人の態度はそういう力と結びついている。否定的な言葉は、人が初めて話すことを覚える時から、人間の潜在意識を毒する。偏見が社会の血流に溶け込んで循環する」。
○「小説というものは、創意と精神の養分を吸いつくす貪欲な胎児である。しかし一方で、それは養分を供給し補充してくれる。そういう風にして、小説を書くことは、作家自身にとって成長と変化の過程となる」。
○「わたしはこの頃、速読と速解を信用しなくなった。巧みな人物描写を熟読し、名文をゆっくりと味わうことほどの心の楽しみは稀である。『絶対にものを学ぶことのない人々がいる……それは何でもすぐに理解しすぎるからである』とアレグザンダー・ポープ(1688-1744年。イギリスの詩人・批評家)が言った」。
○「書物はいまだに、人間の知っている最良のポータブルな大学である」。
○「書物にどんな限界があるにせよ、それにはすばらしい防音装置が備わっており、しかも心の耳にははっきりと聞きとれる。ただし、いい書物の効能は、その無音という性質を、はるかに越えるものである。いい書物は共有の体験であるが、同時にすこぶる個人的な体験でもある。それは実りの多い孤独を与えてくれる--時には群衆の真ん中で」。
○「医学の助けを借りないで、簡単に寿命を延ばす方法がある。それは“書物”という名の方法である。それによれば、我々は一回の人生の中で数百回の人生を生きることができる」。
○「すべての人が金持ちになる幸運に恵まれるとは限らない。しかし言葉については、誰しも貧乏人になる要はないし、誰しも力のこもった、美しい言葉を使うという名声を奪われる要はない」。
○「もし我々が偉大な詩を望むのなら、偉大な読者が必要である」。
その世界を離れると、その世界のことが客観的によくみえることがある。
私もいまとなってはメディア(特に出版)界のことがよく観察できる。
日本にはそれこそ多くのジャーナリスト、記者、編集者、評論家がいて、
さまざまにメディア・コンテンツをつくっている。
しかし、カズンズ級の人物がこの国のメディア界にどれほどいる(いた)だろうか。
大衆の好みを取りいって、おもしろおかしく、ベストセラーをつくるプロはいる。
また、テレビのニュースバラエティ番組などで
骨の抜けた当たり障りのないコメントをするタレント的なプロもいる。
しかし、深く高い言葉を持ち、
大きな良識・良心をもって創造、発信しているメディアのプロフェッショナルとなると、
残念ながら出会うのに苦労をする。
強い志を持ち、とてもよい記事を書くジャーナリストや、よい本を出す編集者は
確かに少なからずいる。しかし、そうしてつくられた意欲作は、
地味で真面目でつまらないということで読まれないのだ。
まさにカズンズの指摘したように、
「ソフィストケート(技巧化)された飴細工」を大衆は好むのであり、
質素な外見の「まともな内容」のものは素通りされる。
私たちがこの国で、カズンズ級のメディア人を持とうとすればどうすればいいのか?
―――それはカズンズがすでに教えてくれた。
「もし我々が偉大な詩を望むのなら、偉大な読者が必要である」と。
そう、偉大なメディア人を欲するのであれば、
視聴者・購買者である私たち1人1人が、
強くじっくりとよい本、よい記事、よい書き手・作り手を求めていくことだ。
私はもはやジャーナリストとしての道を歩んでいないが、
ものを書いて何かを世に訴えるという意味では、カズンズと同じ仕事に就いている。
だから私のロールモデルの一人として、ノーマン・カズンズを加えたいと思う。
彼の生き様・働き様を模範とするに遅すぎることはないのである。

志賀高原の一沼(上)と四十八池(下)。
私は登山よりも山歩きを好みます。
登山となると登頂という至上目的が課されるので一心不乱に登ることになりますが、
山歩きは、言ってみれば“逍遥”なのでいろいろと考え事
(深刻な考え事ではなく、夢の大風呂敷を広げる楽しい空想)ができるからです。
もちろん、登山にはそれとは別のすばらしい楽しみがあります。