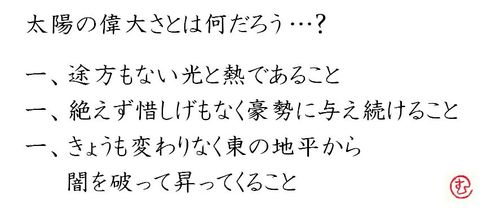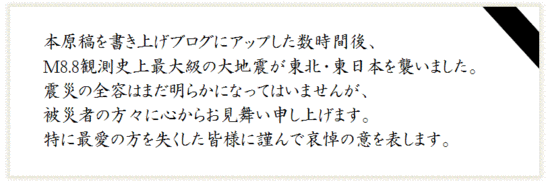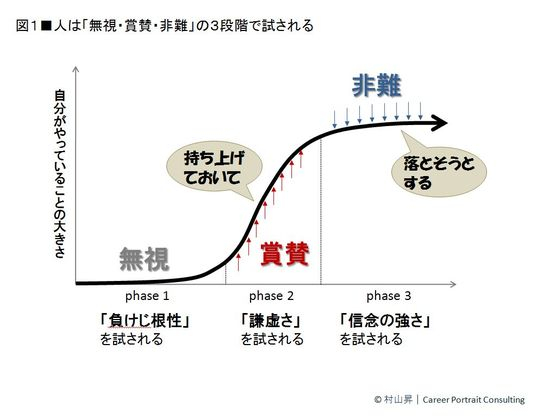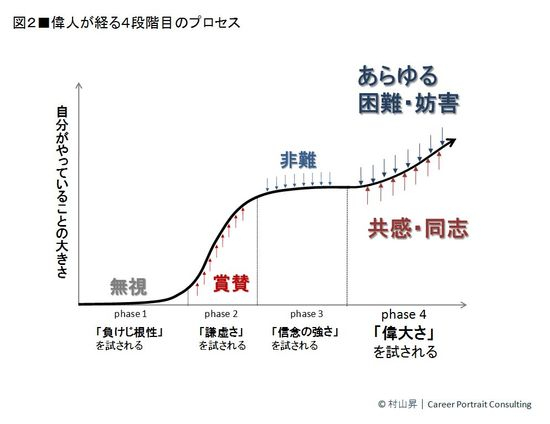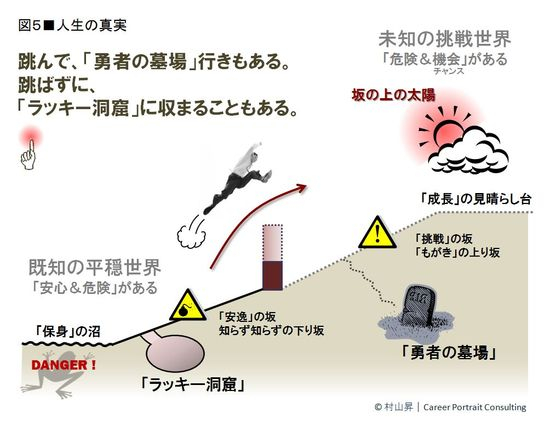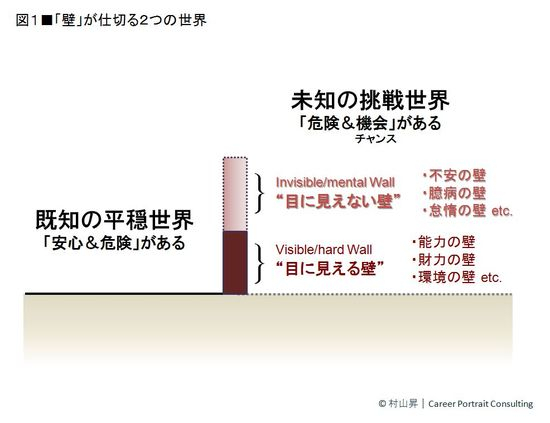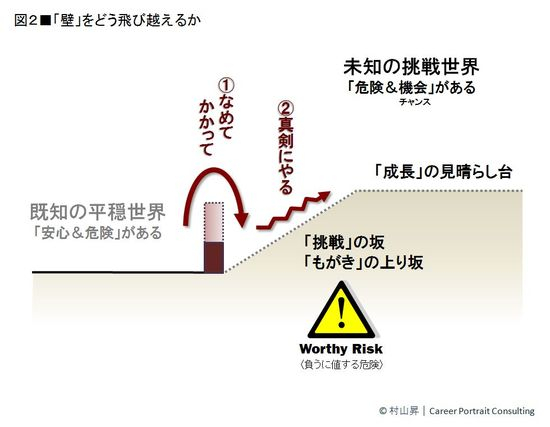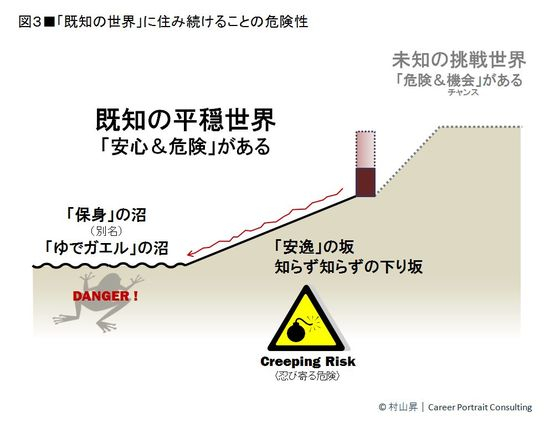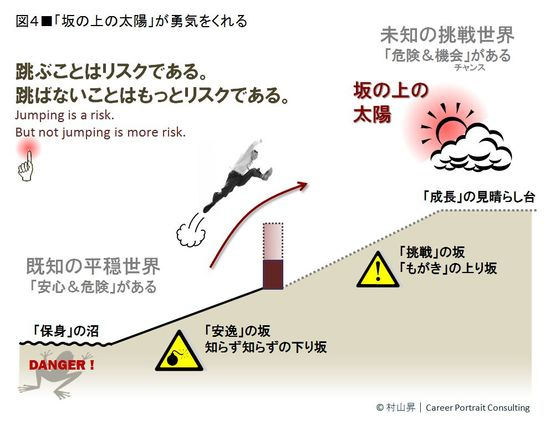自然の容赦ない圧倒的な力に思ふ
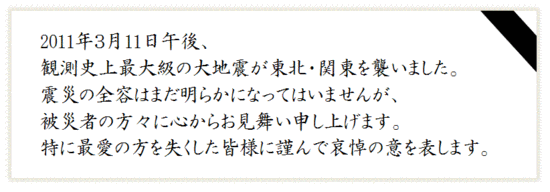
3月11日の午後、地震発生の2時間ほど前ですが、
私はこのブログに「太陽の偉大さ」というテーマで記事をアップしたところでした。
太陽の偉大さは何だろう……?
一、途方もない光と熱であること
一、絶えず惜しげもなく豪勢に与え続けること
一、きょうも変わりなく東の地平から闇を破って昇ってくること
この日の早朝、いつもどおり近くの雑木林に散歩に出て、
あまりに春の到来を告げる日差しが穏やかだったものですからこう書きました。
そして、その数時間後に地震は起きました。
東京の私のオフィス部屋も恐ろしく揺れました。
そしてテレビ画面に刻々と入ってくる映像……。
* * * * *
それにしても、こうした自然の巨大な力を目の当たりにするとき、
私たちは自然・宇宙のなかに、
あくまでちょこんと生きさせてもらっているのだということを感じます。
一昨日の巨大地震・巨大津波は、
善人だろうが悪人だろうが、
金持ちだろうが貧乏だろうが、
男だろうが女だろうが、
子どもだろうが年寄りだろうが、
また、船だろうが車だろうが家だろうが工場だろうが、
それらを分け隔てなく、根こそぎのみ込んでいきました。
……その容赦のない圧倒的な力。しかしそれは意図ある暴力的な力ではない。
自然の容赦のない圧倒的な力は、太陽がまさにそれで、
太陽は地球上の生きとし生けるものに滋養のエネルギーを与えると同時に殺傷もする。
(例えば紫外線は殺菌・殺傷能力があります)
太陽は何を生かし、何を殺すか、といった意図は持たないように思える。
ただただ、容赦なく、平等に、無関心に圧倒的に与え続けるだけです。
私たち人間ができることは、そうした圧倒的な力の一部を借りて、
最大限に生きさせてもらうことです。
また、その力の背後には、もしかして大いなる意図・法則があるのではないかというふうに
叡智をはたらかせて強く生きることです。
人間が持つ物理的な力は大自然の力に比すれば極微たるものですが、
私たちの思惟は全宇宙をも包含することができます。
私たちは、古来、自然・宇宙に畏怖を抱いてきました。
この原初的な信仰心の根っこである畏怖の念は、
いろいろな意味で傲慢になりすぎた人間をよい方向へ引き戻す作用として大事なものです。
こうした自然災害が起こるたび、
畏怖をベースとして生きること、運命ということについての観を見つめ直すことができれば、
それはひとつの被災をプラスに転じたことにもなるのでしょう。
「地に倒れた者は、地を押して立ち上がる」―――これからの復興は、やはり自然の力を借りて、
自然とともにあるわけです。
人間はこれまでもそうして何度も立ち上がってきました。
まずは救出・救援と最低限の生活環境の復旧です。
がんばろう、東北(関東含め)!
私たちも我が身のこととして、復興支援にどんな形であれ加わっていきたいと思います。
震災からまる2日が経ちました。
何事もなかったかのように、太陽はきょうも天から光を降り注いでいます。