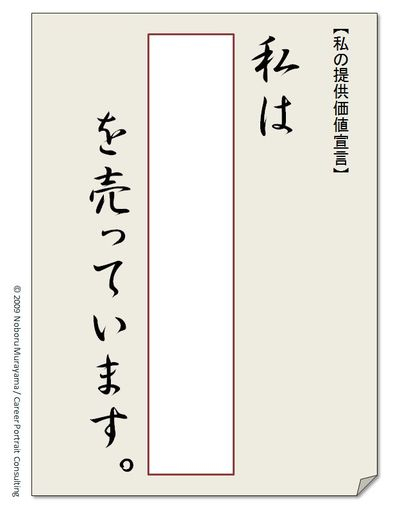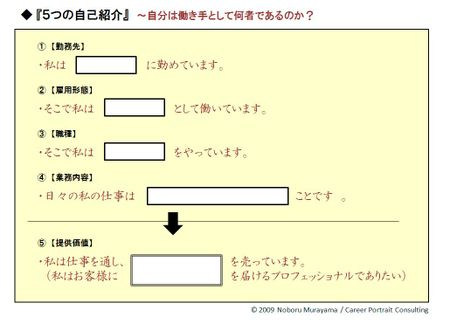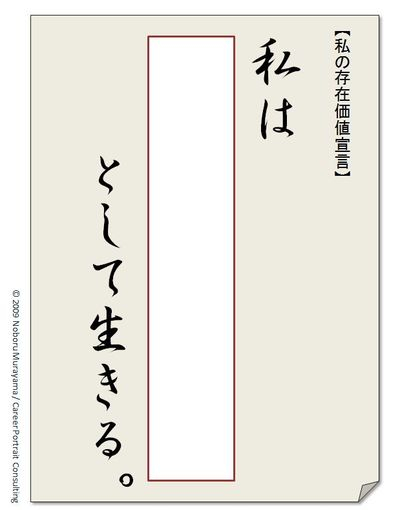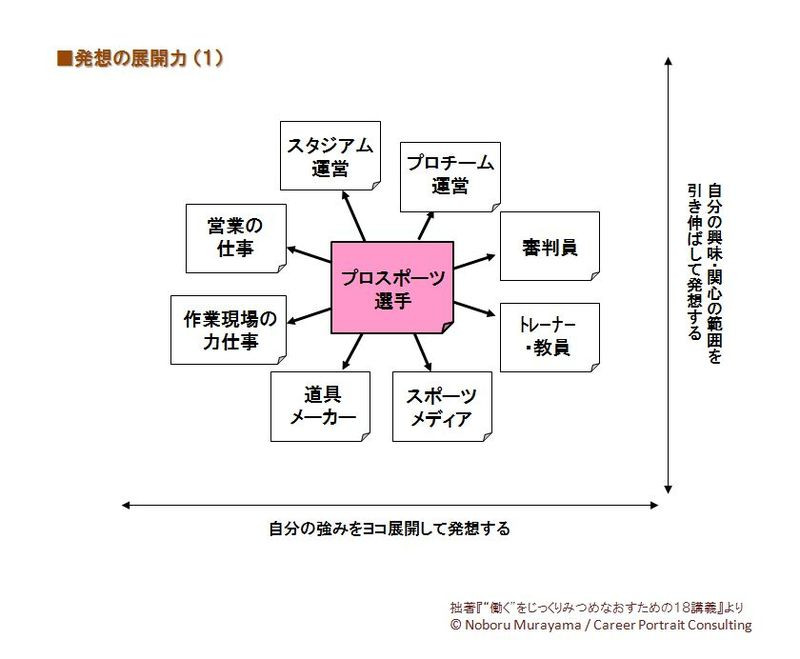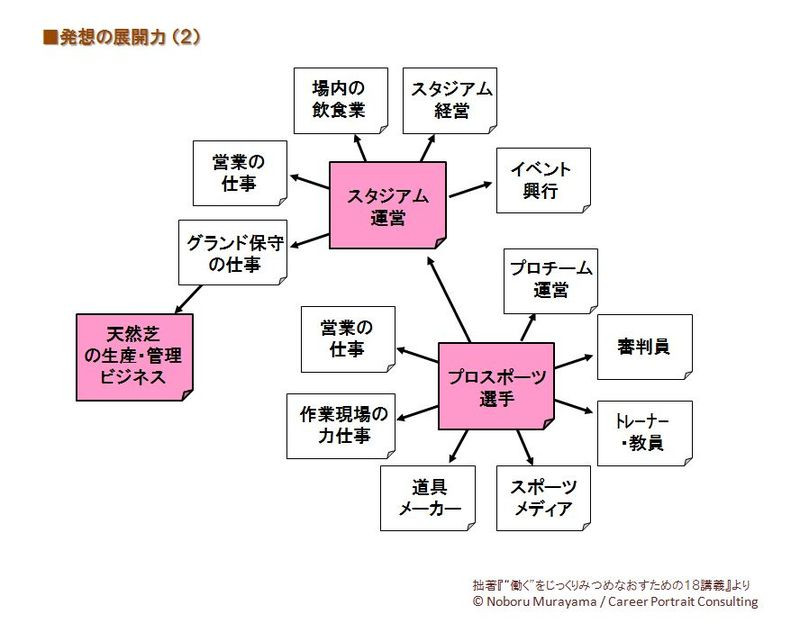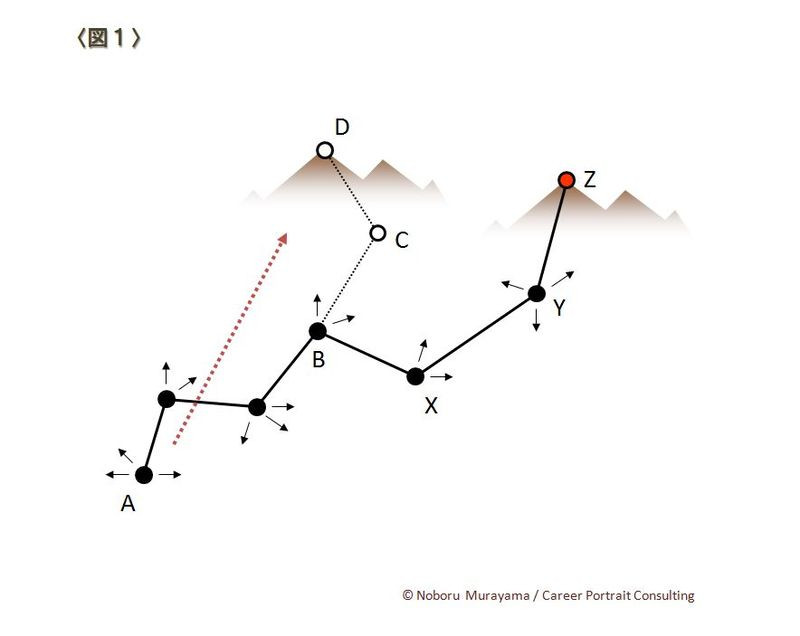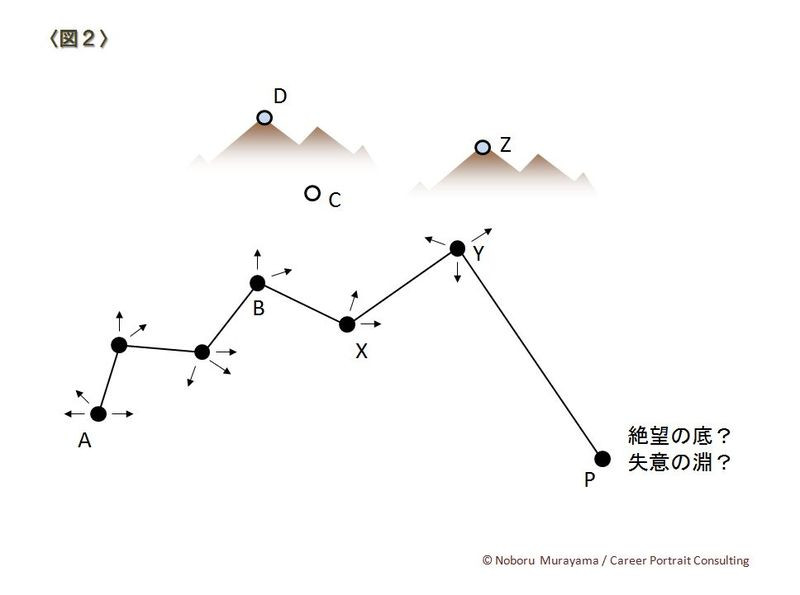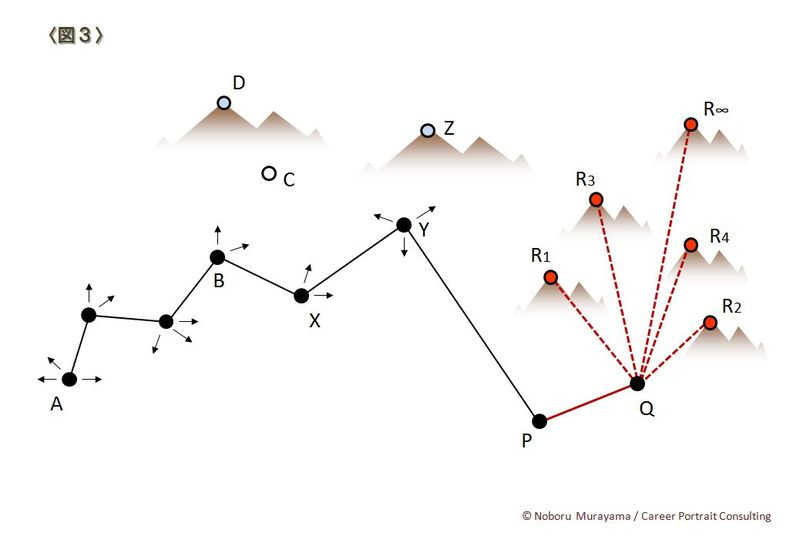やさしく・ふかく・ゆかいに・まじめに

奥鬼怒にて1
「むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに
ゆかいなことをまじめに」
―――井上ひさし
私は自らの職業の定義を「“働くこと/仕事とは何か?”の翻訳人になること」として
6年前に独立し、今に至っていますが、
常に頭の中の下地に敷いているのが、この井上ひさしさんの言葉です。
むずかしいことをむずかしいまま言う、あるいは
むずかしいことをまじめに言う、ことは簡単ですが、
むずかしいことを
「やさしく、ふかく、ゆかいに、まじめに」という経路を通して、
受け手に染み込ませるように伝える(そして結果的に、じゅうぶんに伝わっている)
―――それは生涯を通じて追求せねばならないことだと思います。
ともすると、私の生業とする企業研修サービスの分野、ビジネス書出版の世界では、
「やさしく」が、お手軽なハウツーの披露、
「ふかく」が、感覚的に鋭い切り口を見せながら、実は表面をすくうだけのコンテンツ、
「ゆかいに」が、オモシロオカシクの演出、
「まじめに」が、重くならないよう適当に茶化しを入れる・・・
などにすり替わっていることが多々あります。
それは、より多く売るために、発信側が行うある種の迎合によるものですが、
私はそれらを固く排していきたいと思っています。
(たとえ、不器用で不格好で、非効率で、地味であっても)
で、今週、ン十年ぶりに夏目漱石の『坊っちゃん』を再読しました。
まさに、
「むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに
ゆかいなことをまじめに」書いた最良のお手本だと思いました。
奥鬼怒にて2