神谷美恵子『生きがいについて』
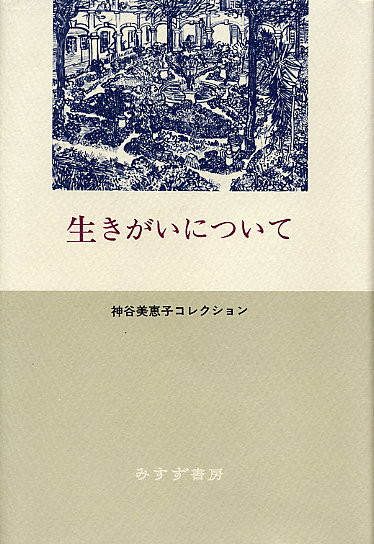 このブログは「職・仕事を思索する」ことをメインテーマにしています。
このブログは「職・仕事を思索する」ことをメインテーマにしています。
その中で、「働きがい」はどうしてもはずすことのできない重大なテーマですが、
「働きがい」を考えるには、
そのもうひとつ奥にある「生きがい」を考えねばなりません。
きょうは、その「生きがい」を真正面からみつめた名著
神谷美恵子の『生きがいについて』(みすず書房)を紹介します。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
神谷美恵子(1914-1979)は、
生涯をハンセン病患者の治療に捧げたことで知られる精神科医です。
彼女は、ハンセン病の治療施設で数多くの患者と接し、
その病ゆえに絶望に打ちひしがれて生きる意欲をなくしている人々をみる一方、
それとは逆に、何らかの目的や望みをもって積極的に生きようとする人々をみた。
この本の冒頭部分で彼女はこのように書いています。
「平穏無事なくらしにめぐまれている者にとっては思い浮かべることさえ
むつかしいかもしれないが、世のなかには、
毎朝目がさめるとその目ざめるということがおそろしくてたまらないひとが
あちこちにいる。・・・・(中略)
いったい私たちの毎日の生活を生きるかいあるように感じさせているものは何であろうか。
ひとたび生きがいをうしなったら、
どんなふうにしてまた新しい生きがいをみいだすのだろうか。・・・・(中略)
同じ条件のなかにいてもあるひとは生きがいが感じられなくて悩み、
あるひとは生きるよろこびにあふれている。このちがいはどこから来るのであろうか」・・・
精神科医である神谷が、
「生きがい」という茫漠としながら、しかし極めて重大なテーマについて著すことの
動機を語った部分です。
私がこの本を他の人に薦めたい理由は、神谷美恵子という一人間が、
・張り詰めた臨床の場で全身全霊で受け止めた情報を
・哲学や科学の世界からの英知をたくみに組み合わせつつ
・慈しみ溢れる人間性で包み込んで
書き出した一冊であるからです。
「生きがい」などという甚大なテーマは、
“何が”書かれたかは、確かに大事ではありますが、それ以上に
“どんな人物”が書いたかが、決定的に重要です。
要領よく世間を成り上がった者が、「生きがい」「働きがい」について語ったところで、
何の説得力も出ませんし、
また、象牙の塔にこもった学者などが
学術的な理論のみできれいに語った「生きがい論」等もどこかパワー不足に陥ります。
その点、この本は書くにふさわしい人が、書くべき内容を、ずっしり書いたものです。
「キレのある本」、「面白い本」、「情報が濃密な本」など本にはいろいろな特徴が出ますが、
この本は、「強く賢い母性の本」であると思います。
そして「じーんと迫ってくる本」であるとも思います。
正直、地味で、読み解くのに力が要りますが、
自分が真剣に読み解こうとぶつかった分だけ、何かしらを与えてくれる本でもあります。
(名著とはそういうものです)
サクサク読めるお手軽な世渡りハウツー本が巷には溢れていますが、
こういった本を、突っ掛かり突っ掛かり、
著者の思想の壁をよじ登りながら読んでいくことが、実は
「生きる・働く」に悩む人に本当に必要な作業ではないでしょうか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
神谷は、現代人が雑多な用事に忙しくし、
本当に大事なことを考え抱こうとする暇(いとま)を持たないことを危惧した。
そして、そんな中で生きがいの重要性やその難しさを述べる。
「日常の生活は多くの用事でみちているし、その用事を次々と、
着実にかたづけて行くためには、「常識」とか「実際的思考力」などという名の、
多分に反射的、機械的な知能の処理能力さえあればすむ。
あまりにゆたかな想像力やあくことなき探究心やきびしい内省の類は、
むしろ邪魔になるくらいであろう」。
「人間から生きがいをうばうほど残酷なことはなく、
人間に生きがいをあたえるほど大きな愛はない。
しかし、ひとの心の世界はそれぞれちがうものであるから、
たったひとりのひとにさえ、
生きがいを与えるということは、なかなかできるものではない」。
「生きがいというものは、まったく個性的なものである。
借りものやひとまねでは生きがいたりえない」。
神谷は、生きがいを理解していくために、生きがいに似たものとして、
よろこびや充実感、使命感などのようなものの考察から始めていく。
そして、生きがいを生きがいたらしめるもの、よろこびをよろこびたらしめるものとして、
苦労や苦難、障壁など「負の力」を指摘している。
「さまざまの感情の起伏や体験の変化を含んでこそ生の充実感はある。
ただ、呼吸しているだけでなく、生の内容がゆたかに充実しているという感じ、
これが生きがい感の重要な一面ではないか。
ルソーは『エミール』の初めのほうでいっている。
“もっとも多く生きたひとは、もっとも長生をしたひとではなく、
生をもっとも多く感じたひとである“と。
・・・・あまりにもするすると過ぎてしまう時間は、
意識的にほとんど跡をのこさない」。
「人間が真にものを考えるようになるのも、自己にめざめるのも、
苦悩を通してはじめて真剣に行なわれる。・・・苦しむことによって
ひとは初めて人間らしくなるのである」。
「ベルグソンはよろこびには未来にむかうものがふくまれているとみた。
たしかによろこびは明るい光のように暗い未知の行手をも照らし、
希望と信頼にみちた心で未来へ向かわせる。
・・・・(中略)よろこびというものの、もう一つきわだった特徴は、
ウィリアム・ジェイムズも気づいたように、
それがふしぎに利他的な気分を生みやすい点である。
生きがいを感じているひとは他人に対してうらみやねたみを感じにくく、
寛容でありやすい」。
「使命感というものは多くの場合、はじめは漠然としたもので、
それが具体的な形をとるまでには年月を要することが少なくない。
・・・(使命感とは)「自分との約束」をみたすものであったのだ。
もしその約束を守らなかったならば、
たとえ世にもてはやされても、自己にあわせる顔がなくなり、
自分の存在の意味を見うしなったであろう」。
ひとたび生きがいを見出し、そのよろこびを獲得した人は、
静かであれ、急激であれ、心の世界の変革が起こる。
それは多分に宗教的体験に似ている。
そのとき人は、深い次元で平安となり、利他的となり、「おおいなるもの」の存在を感じる。
神谷はそのあたりを例えばこのように記しています。
「小さな自我に固執していては精神的エネルギーを分散し、
消耗するほかなかったものが、
自己を超えるものに身を投げ出すことによって初めて
建設的に力を使うことができるようになる。
これはより高い次元での自力と他力の統合であるといえる」。
「変革体験はただ歓喜と肯定意識への陶酔を意味しているのではなく、
多かれ少なかれ使命感を伴っている。
つまり生かされていることへの責任感である」。
“シューキョー(宗教)”なるものが、ネガティブにとらえられている昨今、
私個人も、小生意気で不遜だった20代のころは、
「我々は生かされている」とか「摂理に通じる感覚」とか、
そんな言い回しがどうも抹香臭くて、素直に納得できない時期がありました。
(若い読者の中には、そう思われる方が多いかもしれません)
もちろんここで言っている宗教とは、
特定の形をもった宗教(教義、組織)ではなく、
万人が共通に感受しうる宗教的体験を指します。
(*「5段階欲求説」で有名なエイブラハム・マスローも、このあたりを
「至高体験」(peak experience)と名づけています)
そんなことを充分知っているのでしょう、神谷は慎重に言葉を選びながら、
古人の叡智を引用しながら、あるいは実験結果のような具体的な証拠を示しながら
この本の最終部分のペンを進めています。
生きがいのたどり着く先は、
利他的な使命観であり、おおいなるものと自己とが統合される体験である。
その体験は、人に心的な変革をもたらし、
人は真の心の平安を得ることができる。
真の平安とは、苦労や苦難がなくなることではなく、
たとえどんな苦労や苦難に直面しても、自分を能動的に支配し進んでいけるという
心的状態である――――私がこの本から得た結論はこうまとめられるでしょう。
神谷もこう言っています。
「結局、人間のほんとうの幸福を知っているひとは、
世にときめいているひとや、いわゆる幸福な人種ではない。
かえって不幸なひと、悩んでいるひと、貧しいひとのほうが、
人間らしい、そぼくな心を持ち、
人間の持ちうる、朽ちぬよろこびを知っていることが多いのだ」。





