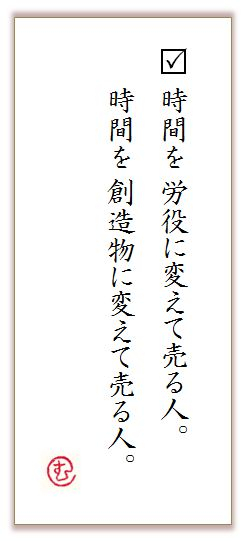原研哉『デザインのデザイン』

おかげさまで私はこれまで自著を出版する機会を何度か得てきた。そして今後もそうした機会をいただきながら、世の中にぶつけていきたいと思っている。
仕事でやっていることが人事・組織・経営関連であるので、書く本はビジネス書・自己啓発書の類として出版することになるのだが、本の企画を練ったり、アイデアを湧かせたりするときに、私は書店のビジネス書コーナーや自己啓発コーナーにほとんどいかない。
私はむしろ、哲学・思想とか芸術とか科学の分野の棚にいって、ぶらりぶらりしながら本を手に取り、必要に応じて買い込みをする。そして一冊の本を読んでいくと、その巻末に記されている参考文献のところからさらに数冊を芋づるで読みたくなり、それをアマゾンかどこかで注文し、どんどんその世界を深めていく。振り返ってみると、人事・組織・経営関連とは直接関係のないそうした読書からこそ、良質のヒントやアイデアを得ていることが多い。
今回紹介する一冊も、ある日、書店のアート・デザインの書棚で出会ったものである。
原研哉 『デザインのデザイン』 (岩波書店)
原氏は、日本のグラフィックデザイン界の重鎮的存在である。どの職業の世界も同じだが、その道を長い時間かけて高い次元まで上っている人は、世の中を統合的にとらえ、「理」(ことわり)のようなものを見据えている。そして、それをみずからの「観」として築きあげている。
(→参考ブログ記事:『一徹理視』 )
その道で超一級の仕事をする人の「理」や「観」を学びとるというのは自分の偏狭な考え方に修正を加えたり、補強したりするためにとても大事なことだ。
特にいまビジネスパーソンと呼ばれる人たちは、ものごとの判断のしかたがどんどんビジネス目線のものに染まっている。つまり経済合理性というひとつの物差しで「よい/わるい」を決める思考習慣に偏っているのだ。私たちは、もっと複眼的で統合的で、ふくらみのあるものの見方を養わなければならない。
例えば、「ユニクロ」と「無印良品」を比べたとしよう。私もビジネス雑誌の編集に長く携わっていたので、「ユニクロVS無印」というような記事は書いてみたいとも思う。
間近の数値をみてみると、
良品計画(2009年2月決算)は、
・売上高:1628億円(前年比100.5%)
・当期純利益:69億円(前年比64.9%)
ユニクロを展開するファーストリテイリング(2009年8月決算)は、
・売上高:6850億円(前年比116.8%)
・当期純利益:480億円(前年比114.4%)
この数値をみて、やっぱりユニクロは勢いが違うな。価格競争力もスバ抜けてるし、製品開発力もスピードもある。ヒット商品も矢継ぎ早に出す。その点、無印のほうは見劣りがする。値段はそんなに安くないし、食品とか家とかまでやってる。採算の悪いものまで手を広げ過ぎだな……もっと選択と集中をしないと。
とまぁ、たいていはこうした見方でユニクロに軍配を上げる。たぶんビジネス雑誌の記者も、証券アナリストも、一般株主も、はたまた末端の消費者も、そうした表に見えやすい経営情報を集めてユニクロはイイ!ユニクロはスゴイ!ということになるのだろう。
私はここでユニクロがよくないというつもりはない。私もユニクロはいいと思うし、すごいと思う。しかし、数字に見えないところで、もっと多面的に(経済尺度以外から)見つめてみると無印は違った次元で優れた企業であることが見えてくる。またユニクロはある面、脆弱な企業であるともいえる。(安さでのし上がった者は、その世界から次元を移さないかぎり、安さに破れることは往々にして起こりえる。ダイエーがそうであったように。もちろんユニクロが「安さ」以外の機軸を出そうとしていることは承知している)
無印良品の広告コミュニケーションに携わった原氏は、この本の中で無印のことに触れている。
○「無印良品の思想はいわゆる「安価」に帰するものではない。コストを下げることに血眼になって大切な精神を失うわけにはいかない。また、労働力の安い国でつくって高い国で売るという発想には永続性がない。世界の隅々にまで通用・浸透する究極の合理性にこそ無印良品は立脚すべきである。したがって、現在では、最も安いということではなく、最も賢い価格帯を追求し、それを消費者に訴求しなくてはならなくなった」。
○「(幾多のブランドが「これがいい」「これじゃなきゃいけない」というような強い嗜好性を誘発するような方向性を目指すのであれば)無印良品は逆方向を目指すべきである。「これがいい」ではなく、「これでいい」という程度の満足感をユーザーに与えること。「が」ではなく「で」なのだ。しかしながら、「で」にもレベルがある。無印良品の場合は、この「で」のレベルをできるだけ高い水準に掲げることが目標である。…「で」の次元を創造し、明晰で自信に満ちた「これでいい」を実現すること、それが無印良品のヴィジョンである」。
無印良品は、もともと、田中一光、小池一子、深澤直人、山本耀司ら、錚々たる大人のデザイナー・アーティストによって支えられてきたブランドである。そこには相応に太い製品開発の思想が流れている。日本の工業製品ブランドとしては稀有な存在といっていい。
よき製品、よきメーカー、よきものづくりビジネスを考えるにあたって、どれだけのビジネスパーソンが、損益計算書のトップラインとボトムライン以外のものを見つめて評価しているだろうか。また、陣取り合戦の巧みさ以外で評価しているだろうか。
そして消費者としての私たちも、価格の安さを離れて、その企業の事業の奥に流れるものを見つめて応援してやることができるだろうか。(事業の奥にさしたるものがない企業も世の中には多いのだが…)
経済やビジネスがますます利益獲得というマッチョな得点ゲームになりつつある今日、ビジネスパーソンの思考はますます経済合理性に引っ張られる。そして、消費者も(デフレが手伝って)、何でも安いものに流れる。
ものづくりを民族コンピテンシーとして立国してきた日本にとって、ここは極めて重大な問題だと思う。だから、今後の日本経済をつくり、かつ日本経済に依って立たねばならないビジネスパーソンたちは、経済原理一辺倒のビジネスの世界にどっぷり浸かっていない人たちの考え方をもっと学ぶべきなのだ。その人たちの方がよっぽどものが正しく見えている。
さて以下に、この本の中で私がピンときた箇所を抜き出しておく。こうしたふくよかで広がりをもった考え方の人びとがビジネス現場でもどんどん増えることを願っている。
○「人間が暮らすことや生きることの意味を、ものづくりのプロセスを通して解釈していこうという意欲がデザインなのである」。
○「新奇なものをつくり出すだけが創造性ではない。見慣れたものを未知なるものとして再発見できる感性も同じく創造性である」。
○「時代が進もうとするその先へまなざしを向けるのではなく、むしろその悲鳴に耳を澄ますことや、その変化の中でかき消されそうになる繊細な価値に目を向けることのほうが重要なのではないか」。
○「時代を前へ前へと進めることが必ずしも進歩ではない。僕らは未来と過去の狭間に立っている。創造的なものごとの端緒は社会全体が見つめているその視線の先ではなくて、むしろ社会を背後から見通すような視線の延長に発見できるのではないか。先に未来はあるが、背後にも膨大な歴史が創造の資源として蓄積されている」。
○「元来、ラスキンやモリスにしろ、バウハウスにしろ、デザイン思想の背景には、少なからず社会主義的な色彩があった。…それは純粋であるほどに経済原理の強力な磁場の中ではその理想を貫く力が弱かった。経済の原理は明白である。近代社会の生活者を消費へと向かわせるべく、次々と新しい製品を生み出し、また、それを欲望の対象として流通させるために、メディアは様々な発展をとげ、広告コミュニケーションもしたたかに進化した。経済発展の流れにデザインは見事に組み込まれていくのである」。
○「民衆の生活にもとづいて発生した日常工芸に日本のプロダクトデザインの原像を見出す『民藝』の運動はひとつの思想としての簡潔さを持ち、西洋のモダニズムに対置できる独特な美学を持っていた。すなわち短時間の「計画」ではなく、生活という「生きた時間の堆積」がものの形を必然的に生み出し磨きあげるという発想である」。
○「デザイナーは受け手の脳の中に情報の建築を行っているのだ」。
○「自然とつきあうということは「待つ」ということであり、待つことによって自然の豊穣が知らぬ間に人間の周囲に満ちる」。
○「これまではグラフィックデザイナーと言えば、ポスターをつくったりマークをデザインしたりする職能だと考えられてきた。しかしながら、元来、デザイナーはそのような単機能の職能ではない。(グラフィックデザイナー自身も自分たちをアピールする際にポスターやマークを多用し過ぎたきらいもある)だから社会がデザイナーに求めるものは「ポスター」と「シンボルマーク」に集約されてしまう。そしてそれらが新しい時代のコミュニケーションにそぐわなくなったとき、グラフィックデザイナーも一緒に色褪せて見えるのだ。
…デザイナーは本来、コミュニケーションの問題を様々なメディアを通したデザインで治療する医師のようなものである。…「頭痛薬」を売ることに専念しているデザイナーは安価な頭痛薬が世間に流通すると慌てることになる」。
○「僕はデザイナーであるが、この『ナー』の部分は優れた資質があるという意味ではなく、デザインという概念に『奉仕する人』という意味である」。