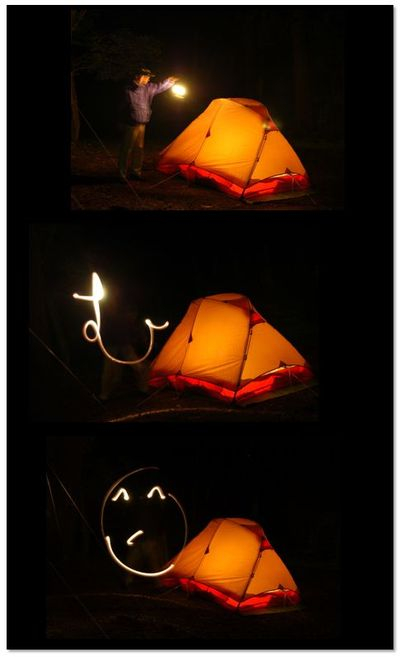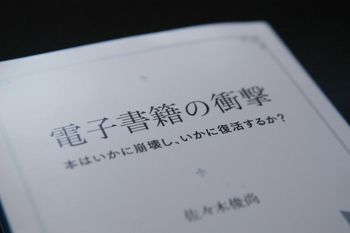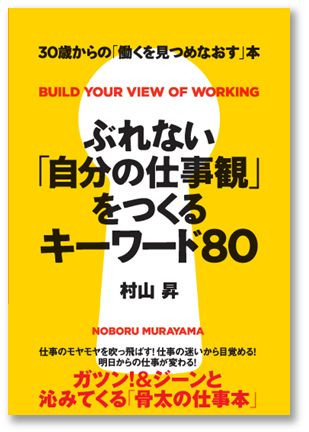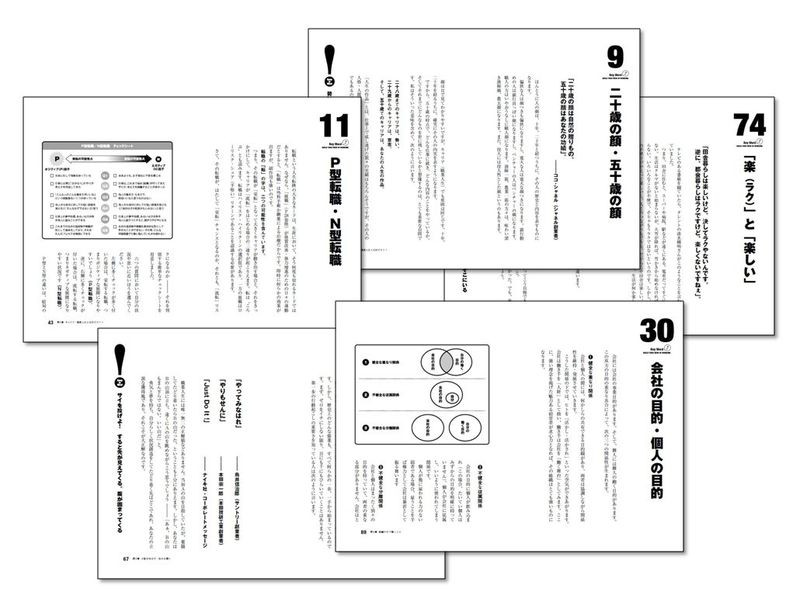W杯サッカーが終わって〈2〉

その2◆結局は基本の力
90分のサッカーゲームは、「パス・トラップ・ドリブル」の織物である。
強いチームを見て惚れ惚れと感じることは、
パス・トラップ・ドリブル、この3つの基本動作のうまさが違うことだ。
その単独の行為だけ見ていても十分に魅了される。
ゲームを決するシュートも、結局、この3基本動作の組み立ての結晶である。
スペクタクルなゲームという豪華な反物は、すべてこの基本動作によって織られている。
仕事もそうだ。
よい仕事をする人は、例外なく基本がきちんとできる。
私が最も重要だと考える基本動作は次の5つである。
読む。 ―――インプット
考える。 ―――スループット
書く。 ―――アウトプット
決める。 ―――方向づけ
はたらきかける。 ―――人とのつながり
これら5つの基本動作で、私たちは仕事という織物を自分なりに織っている。
私はいまだこの5つの基本を大事にし、鍛錬を怠らないようにしている。
その3◆ライバルとの死闘は究極のコラボレーションである
「今夜の勝利にふさわしいのはスペインのほうだった」―――
準決勝戦で敗れたドイツのレーブ監督は試合後のコメントでこのような内容を語り、勝者を称えた。
私は(サッカーに限らないが)、監督・選手の試合後のコメントに聞き耳を立てることが多い。
特に、敵に対してどうコメントするかを聞いている。
スポーツの試合には当然ながら相手がいる。強い相手がいるからこそ、自分も強くなれる。
本大会も息詰まるカードがいくつもあったが、
それはどちらが勝ったにせよ負けたにせよ、後世に見事な作品として残る。
前記事でサッカーゲームは織物だと言ったが、
見事な織物作品は、見事なタテ糸と見事なヨコ糸によってこそ出来あがるものである。
そういった意味で、私は、
「ライバルとの死闘は究極のコラボレーションである」と思っている。
で、それを知っている人間は、
試合後のコメントを求められたときに、相手を称えることを忘れない。
今年の春の選抜高校野球で、ある野球名門校の監督が1回戦敗退の後に
「21世紀枠に負けて末代までの恥」と発言したことが世間でも話題となった。
その悔しい心情はわからないでもないが、残念な発言ではある。
名勝負という作品の半分は、「よき敗者」によってつくられているのだ。
*
ちなみに、ラグビーの場合、試合終了を「No Side」という。
これは、試合が終わって「もう敵・味方の区別をなくしましょう」という意味だ。
ラグビー専用の球技場では、シャワールームも1室しか設置せず、
両軍の選手が一緒に汗を流すというつくりになっているところも多いという。
その4◆戦うモチベーションは「誇り」
W杯という頂点レベルのサッカーは、人のやることの研ぎ澄ましだから、
いやがうえにも民族の精神性や身体特性、社会性が浮き彫りになる。
だから、ニッポンのサッカーとサッカー選手の有り様は、日本の伝統と時代性の影響下にある。
その点を考えると、
この平和な平成ニッポンに生まれ育ち、身体特性も華奢(きゃしゃ)な日本人選手たちが、
よくぞここまで世界で健闘しているなという思いを持つ。
だから私は、W杯に出場というだけで(本戦での勝ち負けはともかく)、
ジャパンイレブン(監督・コーチ陣や、控え選手、サッカー協会など含む)に
「W杯という楽しみを与えてくれてありがとう」と言いたい。
私がサッカーをやっていた少年時代(70年代前半)などは、
日本がW杯に出るなんぞは実現不可能なことで想像もしなかったし、
またサッカー番組などは放映もされなかった。
唯一、三重テレビ(テレビ東京系)が『三菱ダイヤモンドサッカー』というのを放映していて、
でも三重テレビはUHFチャネルで、特別なアンテナを立てないとうまく受像できないので、
私はしかたなく画面にサンド嵐が吹き回る中を目を凝らして観たものだ。
(私は解説者だった岡野俊一郎さんの声を聞くと、いつもこの時代のことを思い出す)
元日本代表監督のイビチャ・オシムは、
「日本という国は人をだまさなくても生きていける平和な国だ。
だからサッカーの世界で勝っていくことは難しい」
といったような意味のことを発言したと私は記憶している。
確かに国際レベルのサッカーで勝つためには、
ずる賢さや狡猾さ、そして強烈なハングリー精神が必要になる。
日本のサッカーは、ずる賢さや狡猾さ、ハングリー精神の面で言うなら、
相当その要素を欠いているのではなかろうか。
そのうえ体格だってハンディを負っている。
にもかかわらず、ベスト16までは行けたのだ。
(技術や規律性、団結力、「代表の誇り」といったモチベーションによって)
ともすると平和ボケしそうな社会のもとに生まれ育った若者が
モチベーションを高く維持してあれだけの戦いをしたのだから、とても敬服に値するし、
(たとえ1次リーグで敗退していたとしても)ありがとうと言いたい―――それが私の目線だ。
仕事部屋の窓から雲を眺める。
雲の変化をみているとヘラクレイトスの「万物は流転する」を思い出す 。