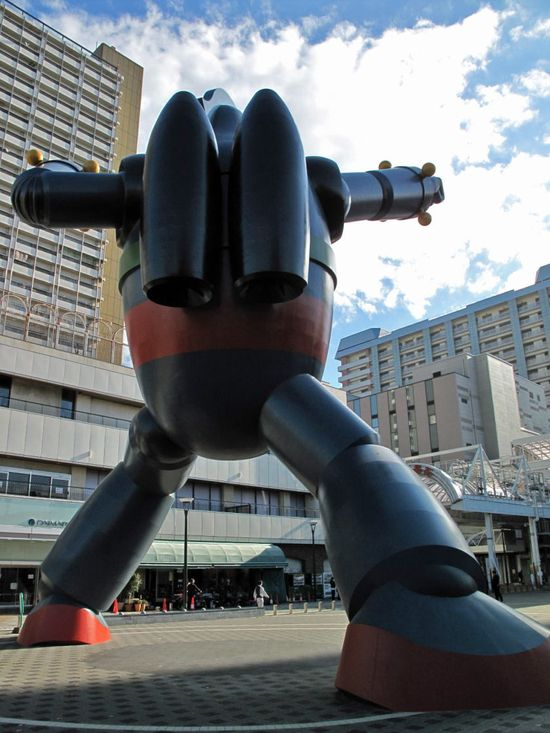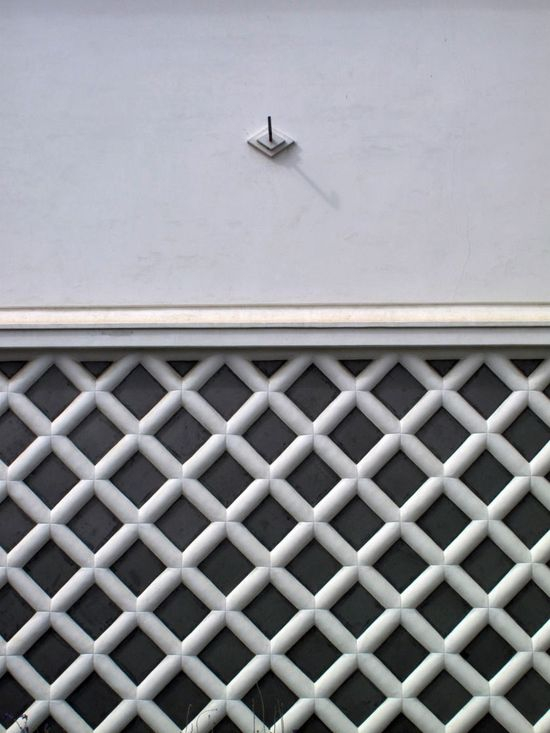NHK-BSは「非読書・超読書・非テレビ・超テレビ」

12月に入り、NHK衛星放送が『BSベスト・オブ・ベスト』をやっている。
面白そうなものがいろいろとあり、録画して少しずつ観ている。
改めてNHKの番組作りの底力を感じるとともに、
BS放送にますます期待を寄せるものである。
民放テレビ局の番組制作力も優れた部分はあるが、
そのほとんどはいまや大人の観るものではなくなった。
雑誌『広告批評』の創刊者である天野祐吉さんが
「NHK-BSは“平熱テレビ”であってほしい」と語っていたが、
確かにその裏返しで、民放はいかにも“高熱”なのだ。
あのテンションの高さ、せわしない画と音、
観る側に考えることをさせない内容、
必ずしも洗練されたとは言えないような表現で消費欲を煽るCMの数々……、
もちろん若い頃はそんな高熱の刺激物を面白がったし、気にかけず受容もできた。
しかし普通に成熟してくる大人にとっては、平熱で観られるものがよくなってくる。
私は年齢とともに民放番組から遠くなる一方だ。
今はテレビを観るうちの、どうだろう、民放率は2~3割くらいだろうか。
実のところ、少子高齢化(と地上デジタル化)はNHKにとって追い風と言っていい。
逆に言えば、民放局はこのままの“ドンチャカ娯楽”路線でいけば、
(メディアとしては依然大きな影響力を持ちつつも)長期に視聴率を失うのは必至だ。
「広告モデル=視聴率至上」できた民放局が、今後どんな変化対応をみせていくのか、
興味をもって注視したいところだ。
(たぶん優秀な人間も多いので、メディアとして何か進化をしていくと思う)
* * * * *
さて、よいNHK-BSの番組の特長は人それぞれに語れるだろうが、私はそれを
「非読書・超読書・非テレビ・超テレビ」という言葉で表したい。
つまり、BS番組はひとつの読書体験と同じくらいの
知的満足と情報吸収をかなえてくれるのだが、
やはり活字読書とは異なるし、活字読書を超えている部分がある。
その非読書であり超読書である部分は、やはり、映像と音があることだが、
よいBS番組というのは、番組というより作品に近いもので、
視聴後の感覚は映画を観終わったときに近い。
その意味で、テレビ的でなく、テレビを超えていると思うのだ。
例えば、私はここ数日、録画しておいた3本の番組を観た。
『輝く女 吉田都』、『強く 強く ~バイオリニスト・神尾真由子 21歳~』
『ロストロポーヴィチ 75歳 最後のドン・キホーテ』―――
いずれも音楽家のヒューマンドキュメンタリーだ。
3つのうち前2つの番組には、くどくどしいナレーションがない。
主人公のインタビュー返答(ところどころに画面外から制作側の質問の声が入る)と、
その他関係者との会話で構成されている。
あとは練習風景やコンサートの映像である。
特段音声のない“間”が幾度となくある。
(しかしそれは意味のある“間”である)
ともかく何か情報を詰め込んで、過度に演出をかけて、矢継ぎ早に展開をして、
というようなサービス満点の(でも考えなくて済むような)番組に慣れた人にしてみれば、
とても冗長なものに感じるかもしれない。
あるいは、「BSは低予算だから編集が手抜きだ」とすら思う人がいるかもしれない。
しかし、観る人が観れば、
これらは相当に吟味のかかった編集物であることが分かるだろう。
主人公はすでにその世界で厳しく闘って実力を示している人であり、
だからその次元にいる人でないかぎり発することのできない言葉とか、
インタビューの質問に対し言葉を探し当てるまでの表情とか、
あるいは、予定調和を壊す突拍子もない返答が出てくるとか、そんな点が面白い。
それはまさに、読書でいう味わい深い文章に引き込まれていく楽しみ、
行間を自分で読み取り補っていく楽しみ、
ページをめくるたびに驚きが出てくるような楽しみ、に通じる。
だから、BS番組は能動的に咀嚼する楽しみがあるという意味で読書に近いのである。
そして挿入される音楽演奏の映像。
これがうまく番組の格を上げる作用をしている。
NHK-BSでは以前から「映像詩」という表現に挑戦にしているが、
『ロストロポーヴィチ 75歳 最後のドン・キホーテ』はその意欲作でもある。
全編映像詩というわけではなく、前半部分をそのメイキングプロセスの
ドキュメンタリーとして組み立てているところが面白い。
それでいて、情報にも満ちており、一種の教養番組の要素もある。
で、主演が、かのロストロポーヴィチと小澤征爾であるから、
下手な役者を連れて来るよりもリアルな存在感がある。
全体的にみて、画や音のつくり方・つなげ方、そして
制作者側の想いの軸の通し方がどこか映画的であり、また映画的でない。
先ほどBS番組は、番組というより作品っぽいと言ったのはこのあたりのことだ。
BS番組のしっかりとしたものは、長さがたいてい90分とか2時間になる。
しかし私は、いま2時間という時間を使うのであれば、
DVDを借りてきてハリウッド映画を観るよりも、BSの良質な番組を観たいと思う。
* * * * *
さて、最後に仕事に関わる話を。
私はこうした番組を観るたび、「働くこと」はすばらしいなと思う。
ヒューマンドキュメンタリーであれば、もちろんそれはその人を追っているのだが、
実際は、その人の「働き様」を追っていることがほとんどだ。
つまり、その人のすごさは「働くこと・仕事」のすごさによってなのである。
また、『プラネット・アース』のようにネイチャーものであれば、
人は出てこないかもしれないが、あのすばらしい映像を観たとき、
こんな映像を撮る職業とはどんな職業なのだろう、
こんな仕事に没頭できる人生はさぞ幸せな人生だろうと、
やはりその裏にある「働くこと」を考えてしまう。
良質のBS番組は、大人が知的好奇心を満たすだけでなく、
親子で一緒に観てほしいと願うものである。
あるいは学校でも見せてほしいものである。
子供には少し内容が難しいだろうとか、そんなことは気にしなくてよい。
子供のころから大人のレベルの上質ものをどんどん見せてやるべきだ。
そしてさまざまな働き様・生き様があることを親や先生は語りかけてほしい。
それこそが何よりも優れたキャリア教育になるから。