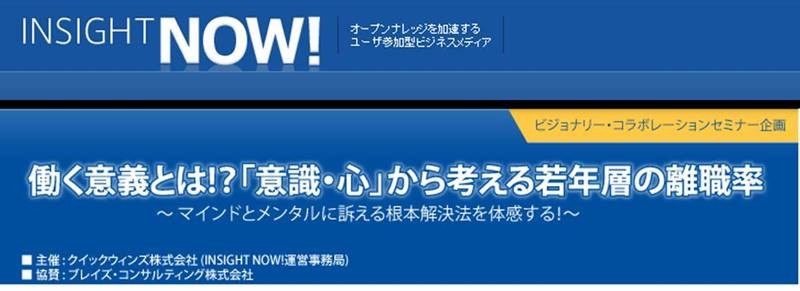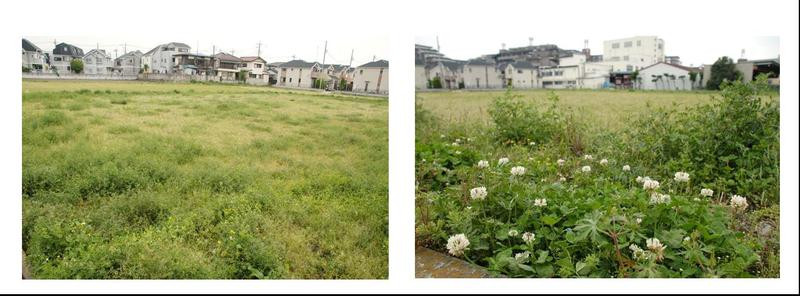ホンダF1撤退と「ゲームの三達者」
ホンダ(本田技研工業)が、12月5日付けで、F1の撤退をアナウンスしました。
世界最高峰のレースに参戦し勝つことは、
二輪・四輪を問わず、ホンダの創業以来、DNAレベルに強く染み付いたものですし、
さまざまな先行投資、裾野の広い関係者への影響を考えても
そう簡単に、そしてかくも火急に決断できることではありませんが、
よくぞ福井社長はそれを下したと思います。
F1に注いできた経営資源や人材を
環境関連などの新しい分野に振り向けるということですが、
その新しい分野の開発および製品化で
21世紀の「ホンダらしさ」をおおいに発揮してほしいと思います。
ホンダという企業のアイデンティティは、本田宗一郎さんのころから、
一にも二にも「独創性」(=人のものまねをしないこと)だったと思います。
であるならば、
ガソリン1リットルで100km走る乗用車とか
太陽電池で時速100km出せる乗用車とか
あるいはロボットだとか、
そういうことでナンバーワンになる、オリジナルなものを製品化するということで
今後もホンダがホンダらしくあり続けることが十分に可能なのではないでしょうか。
私は、実家が三重県の鈴鹿市に程近いところでF1レースは嫌いではありませんが、
それでも最近は、
このように物質をぜいたくに使い廃棄する興行イベントは
旧感覚・旧価値観のマッチョレースだと思うようになりました。
だから、むしろ日本のものつくりの雄であるホンダには、
F1レースというような
ヨーロッパの上流階級と旧時代のクルマ好きがつくったレースとはおさらばし、
全く異なった次元・発想のレース、あるいは市場をつくって、
そこで独自性や存在感を出してほしいと切に願います。
F1というレースの枠組みは、はっきり言って、もう古いです。
そんな中で、一等賞を目指す必要はもうないと思います。
『ホンダ・フィロソフィー』の中にある
「社会からその存在を認められ期待される企業になる」ことについて、
社会の私たちは、もはやホンダに期待することは、F1で優勝してくれではなく、
他のもっと大きな枠組みで何か人類の益となる画期的なことを成し遂げてくれ、なのです。
* * * * *
ゲームには“三人の達者”がいます。
○第一の達者:
「枠の中の優れた人」=「優者」・「グッド・プレーヤー」
これは、決められたルールの中で優秀な成績をあげる人です。
○第二の達者:
「枠を仕切る人」=「胴元」・「ルール・メーカー」「ゲーム・オーナー」
これは、ゲームのルールを決め、元締めをやる人です。
○第三の達者:
「新たな枠をつくる人」=「創造者」・「ニューゲーム・クリエーター」
これは、そのゲーム盤の外にはみ出していって、
全く違うゲームをつくってしまう人です。
日本人は民族のコンピテンシーとして、
「ものつくりの民」であり、
決められた枠の中で、一番の人を模倣して研究し、
やがて一番になることが得意です。
つまり、第一の達者タイプです。
一方、アングロサクソンやユダヤの民族は
「仕組みづくりの民」であり、
第二の達者、第三の達者としてコンピテンシーを発揮します。
* * * * *
01年9月11日のアメリカ同時多発テロ、そして今回の金融危機と
世界史的な時間軸でみれば、大きな時代が区切りを迎え、
次の新しい時代が始まろうとしています。
(どんな秩序になるかまったく見えませんが)
そんな大きな次の時代に、
ホンダに限らず、他の日本企業が、
そして日本という国自体が、そして個々の日本人がチャレンジすべきは
枠をはみ出し、枠をつくり出すコンピテンシーを養うことだと思います。
第一の達者を追求するだけでは、
もはや日本は世界経済の中ではうまく立ち行かなくなるでしょう。
日本人は狡猾さや政治力に欠けるので、第二の達者には永遠に向きませんが、
第三の達者にはなれると思います。
そういった意味では、
ホンダも、他者がこしらえたF1という枠組みの中での優等生から
みずから枠組みをこしらえることへの
一つの跳躍を試されているといえます。
私も、みずからの事業で、既存の枠組みからはみ出す努力を続ける決意です。