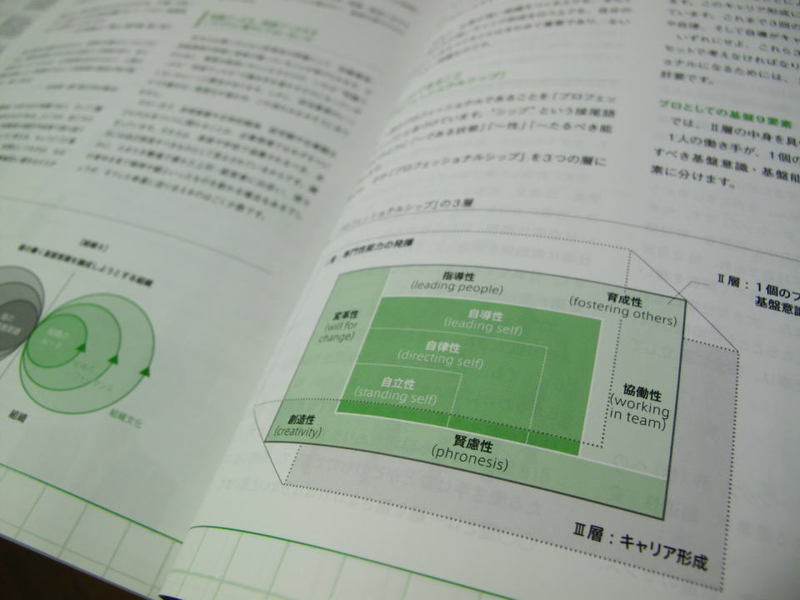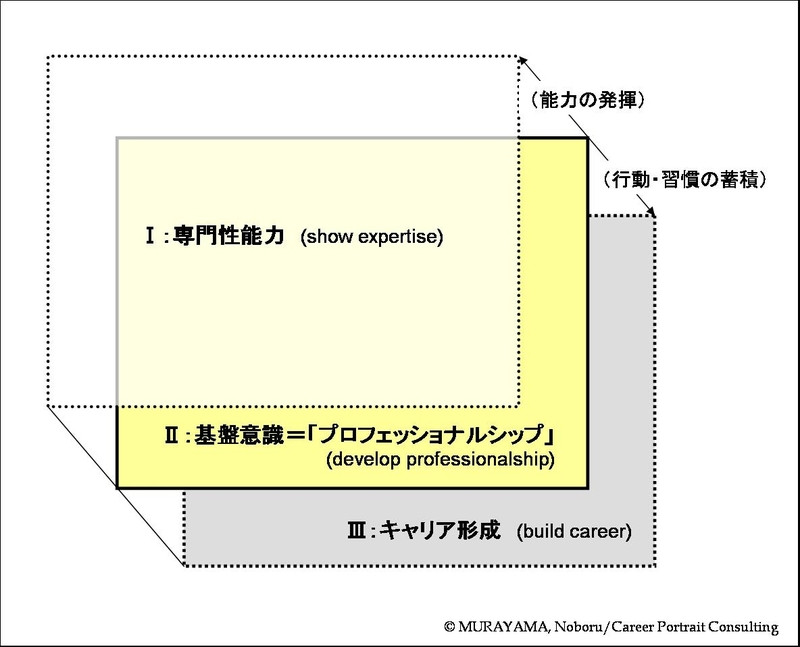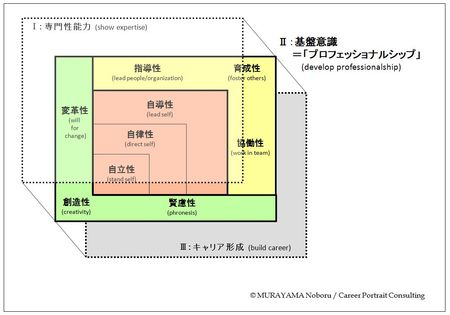『一徹理視』 ~3年ジョブローテーション再考

手元にビジネス雑誌『THE 21』09年6月号(PHP研究所発行)がある。
この中の、キッコーマン・茂木友三郎会長のインタビュー記事が面白かったので紹介します。
茂木会長のコメントを要点だけ抜き出すと、
○
毎年、新入社員に「いつでも会社を辞められる人間になれ」という言葉を贈る。
いつでも辞められる、どこにいっても働けるぐらいの人材でないと、
社内で思い切ったことができない。
自分の意見もおっかなびっくりでしか言えない、また、
上から睨まれて、クビにされるのが困ると思ってしまう人材に、
会社に長くいてもらってもいいことはない。
○
要は、“スペシャリティー”をもて、ということ。
スペシャリティーとは、「社内でこの問題はあいつに任せれば安心だ」とか、
「この問題に関してはアイツにはかなわない」というようなレベルではない。
「業界の中で、キッコーマンのアイツはスゴイよ」とか、
「キッコーマンにはあいつがいるからウカウカできないぞ」といった
業界内で名前が轟(とどろ)くようなスペシャリティー。
○
(企業では3年ぐらいでジョブローテーションをさせるのが一般化している。
そんな中でスペシャリティーを磨くのは容易ではないが、との問いに・・・)
これはもうとんでもない話。
一つの仕事を3年しかやらないなんてナンセンス極まりない。
そもそも3年サイクルのローテーションは、エリート官僚のための制度だった。
官僚の中のトップ5%くらいの人間が、そうやっていろいろな仕事をかじって、
全体をみる経験をしていく。
企業に入ってくる多くの大卒者はエリートでもなんでもない。
そんな人材が、短期間でグルグル仕事を変わるなんてことは意味がない。
3年ぐらいではとてもスペシャリティーなんて身につかない。
その世界では、まだまだ下っ端にすぎない。
○
私の理想論としては、最低でも一つの仕事を10年間やる。それくらいの経験が大事。
30歳までに一つの仕事。
そして40歳までにもう一つの仕事。
その二つの仕事でスペシャリティーになれば、どこへいっても通用する人間になる。
○
(40歳までに二つの仕事しか知らないのでは世界が狭すぎないか、との問いに・・・)
そんなことはない。
スペシャリストになると、仕事のコツや勘どころがみえてくる。
それはどんな仕事にも応用が利く。
40歳以降は、それまでに培った自分なりの“仕事の仕方”を全部の仕事に応用していけば、
どんなジャンルの仕事もこなせる人間になる。
* * * * *
能力開発・キャリア形成における時間レンジのとらえ方はいろいろあるでしょうが、
私は、3年・5年・7年・10年に重要な区切りがあると感じています。
3年は、その分野の「基本習得」に必要な期間。
5年は、その分野の「深耕」に必要な期間。
7年は、その分野に「根を張るため」に要する期間。
そして10年は、その分野の「プロフェッショナルとして自立・自律するため」に要する期間。
私も、茂木会長の持論には賛同します。
ジョブローテーション制度により、
言ってみれば「一畑三年」で、次々に異なる部署に動かされるのでは、
基本が身に付きはするものの、深耕や根を張るところまではいかない。
(この深耕や根を張るところでの負荷が、実は、人間を成長させる機会でもある)
ましてや、プロフェッショナルにはいつまでもなりきれない。
仮に、そうした中で、うまく仕事をやりこなしていく人間がいたとしても、
それは、やはり「組織内ジェネラリスト」「組織内エキスパート」の域を出ない。
ですから、20代と30代をかけて
「一畑十年×2ラウンド」 ―――という発想は、傾聴に値します。
組織が骨のあるプロフェッショナルを育てるには、10年レンジでのとらえ方が見直されるべきです。
たしかに、3年ほどでローテーションさせる制度にはメリットも多い。
ですが、最近、人事の方々とこの話をすると、
・ジョブローテーションの制度を謳わないと、新卒募集の人気に悪い影響が出る
・本当にミスマッチ配属なのか、本人の適応力のなさ・短気なのかは判別できないが、
モチベーションをなくした社員に対してローテーションは一つの刺激剤にはなる
・実際、3年を待たず、職場をかわりたがる社員が増加している
など、ローテーション制度が、本来もっていたポジティブ要因ではなく、
ネガティブ要因によって支持される傾向が強まっているようにも思えます。
* * * * *
私は、仕事上でいろいろなキャリアの姿を研究してきて、
そしてまた、ビジネス雑誌記者時代から幾百もの第一級の仕事人を観察してきて、
あるいは、自分自身が、
メディアの世界で情報編集畑の仕事を10年、
教育畑の仕事を10年やってきて、思い浮かんできた言葉(造語)があります。
それは―――
『一徹理視』
一つを徹すれば、理(ことわり)を視(み)る
つまり、一つのことを徹していけば、
全体に貫通する筋道・法則のようなものが視えてくる、ということです。
そしてこうした道筋・法則のようなものが視えてくると、変化が怖くなくなる。
自分の変えない信念や軸ができているので、
変えるのは技術や適応方法でよい、というように腹が据わるからです。
しかし、一つに徹するという「経験×時間」がなく、環境を頻繁に変える人は、
そもそも変えてはいけない信念・軸が醸成されず、
技術や適応方法を変えることに右往左往し、不安がる日々が延々続く。
(たぶん定年まで、そして定年以降も)
だから私は、働く個人に向けても、そして人事関係者の方々に向けても、
「十年一単位」という仕事期間を、もっと再考すべきだと投げかけたい。
* * * * *
最後に補足してもう1点。
この雑誌のインタビューで、茂木会長は、
リーダーシップを学ぶにはどうすればよいかとの問いに、
「小さい会社を経営してみるのがいちばんです。
企業の責任者というポジションを一度体験してみる。
人と組織はいかにすれば動くかということがよくみえてきます」と答える。
とすると、茂木式・経営プロフェッショナル人財の育て方というのは、
・20代から30代にかけて、「一畑十年」を2つの分野でやらせる
・そして、小さい組織でもよいので経営者の経験をさせる
ということになるでしょうか。
「2つの分野を10年ずつ+経営者経験」―――
単純なようですが、実はこの要素で十分な育成方法・育成思想たりえると思います。
3ヶ月後には、立派な実をつけた黄金の稲穂に。
---「寺家ふるさと村」(横浜市青葉区寺家町)にて