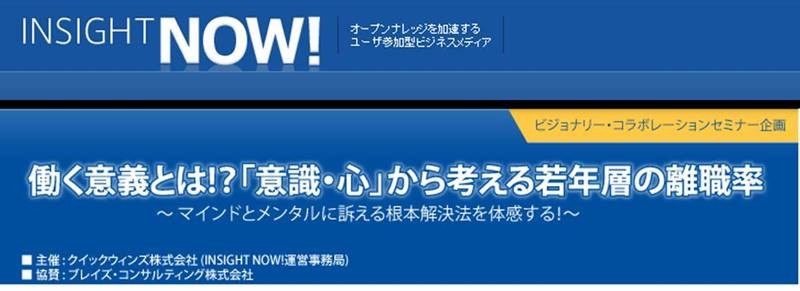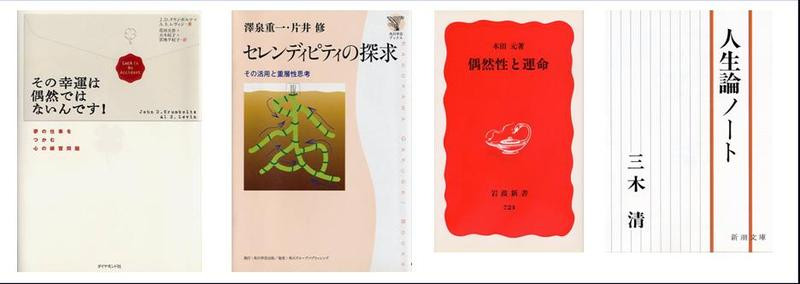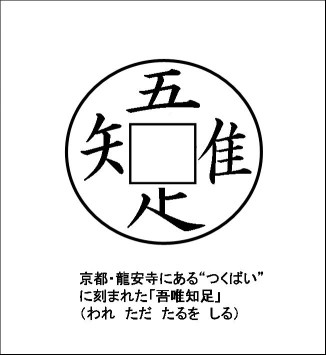サラリーマンの「3鈍」
平均株価が下がり始めると、人は「景気後退」といい、
自分の周辺でリストラが出ると、「不景気」と眉をひそめる。
そして、自分がリストラされると、「恐慌だ!」と騒ぐ。
・・・こんなような言い回しを以前どこかで聞いたようなことがあります。
確かに私たちはいま、大変な時に突入しつつあるのかもしれません。
(過度に悲観するのは賢明ではありませんが)
私などのように個人で事業をやっている者にとっては、
すでに今年前半からその下降トレンドはしっかり身で受け止めていましたし、
そうでなくとも、
この好景気といわれたここ3、4年においてすら、
気を緩めることはありませんでした。
しかし、大企業に勤めるサラリーパーソンにとって
現況はさほど深刻なものとして感じられていないのではないでしょうか。
(深刻に受け止めろ、と言いたいわけではありませんが)
私も、90年以降のバブル崩壊とその後の経済低迷期を
大企業のサラリーマンとして過ごしましたが、
世の中が深刻な状況にあるという実感が薄かったのを覚えています。
メディアのニュースでは耳と頭に入ってきても、
自分の給料が激減するわけでもなく、
日々の業務量が減るわけでもなく、
失業の脅威にさらされるでもなく、
株で大損をしたわけでもなく(そもそも株を保有していないので)
資金繰りに駆けずり回るわけでもなく・・・
もちろん会社の経営者は、ことあるごとに
「えー、昨今の経済状況・市場は厳しさを増し、わが社も・・・」と
社内に向かってアナウンスするわけですが、
しもじもの従業員にはあまり刺さっていかない枕詞のようで
日々のことをやりこなすことで時を過ごしていました。
* * * * * * *
私は、5年前に、晴れてサラリーマン業をやめ、
独立して事業をやっていますが、だからこそいま、
サラリーマンのことがよくわかるようにもなりました。
サラリーマン、特に大企業のホワイトカラー(加えて公務員)は、概して
「守られた働き人」であると思います。
中小企業の経営者や従業員、独立自営業者、ブルーカラーの人びと、
ましてや非正規雇用の人びとは、景気の荒波をほぼ直接的に受けますが、
大企業は、その事業体自身が防波堤となっていて、
そこで従業員は守られます。
従業員個人が受けるのは、防波堤で緩和された波風ですみます。
(もちろん、場合によっては企業という防波堤自身が壊れるときもありますが)
雇用組織が防波堤の役目を果たして、
その中で比較的安心して働けることは、もちろん望ましいことです。
人は雇用の安定保障やら収入保障があってこそ、
仕事に集中でき、内容のあるいい仕事を生み出すことができます。
しかし、人間というものは、環境の恩恵を活かすこともあれば、
恩恵に甘えて怠けることもします。
「貧すれば鈍する」とは昔から言いますが、
同じように、サラリーマンにおいて、
「安すれば鈍する」ことが起きると私は観察しています。
つまり、安心・安穏とした守られた状態に身を置き続けるうちに、
働く意識がいろいろと鈍ってくるという症状です。
私はこれを「サラリーマンの鈍化病」と呼んでいます。
あるいは「キャリアの平和ボケ」といっていいかもしれません。
きょうは、その鈍化病のうち3つを寓話を交えて紹介したいと思います。
サラリーマン諸氏にとっては、多少、耳の痛い内容かもしれませんが、
寓話の紹介だと思って、気楽に読み流してください。
私が感じる「3つの鈍」とは、
1)変化に鈍くなる
2)超えることに鈍くなる
3)リスクを取ることに鈍くなる です。
●鈍化病1【変化に鈍くなる】 “ゆでガエル”の話
生きたカエルを熱いお湯の入った器に入れると、
当然、カエルはびっくりして器から飛び出てくる。
ところが今度は、最初から器に水とカエルを一緒に入れておき、
その器をゆっくりゆっくり底から熱していく。
・・・すると不思議なことに、カエルは器から出ることなく、
やがてお湯と一緒にゆだって死んでしまう。
この話は、人は急激な変化に対しては、びっくりして何か反応しようとするが、
長い時間をかけてゆっくりやってくる変化に対しては鈍感になり、
やがてその変化の中で押し流され、埋没していくという教訓である。
窓際族とかリストラ組とか、それは嫌な言葉ではあります。
私はいま、会社(雇用組織)とも、そこで働く従業員ともニュートラルな立場で
人財教育サービスを行う身ですので、客観的に物事が見られるわけですが、
窓際やリストラを生む原因は、会社側にもありますし、働く個人側にもあります。
しかし、根本的には、働く個人が、働く意識を常に鋭敏にさせて
自己防衛・自己発展させていくしか、この手の問題の解決はないと思っています。
だから、私は、
「サラリーマンよ、ニブ(鈍)リーマンになるな。
環境の変化を感じつつ、変えない自分の軸を持って、自分を変えていけ」
と勇気づけるしかない。
ゆでガエルは、保守・安穏・怠惰・安住の行く末の象徴として
肝に銘じておきたい話だと思います。
*
拙著『ピカソのキャリア ゆでガエルのキャリア』は、
この話をモチーフにして書き上げました。
●鈍化病2【超えることに鈍くなる】 “ノミの天井”の話
ノミの体長はわずか数ミリだが、体長の何十倍もの高さを跳ぶことができる。
ビーカーにノミを入れておくと、当初、
ほとんどはビーカーの口から元気よく跳び出ていってしまう。
しかし、ビーカーにガラス板でふたをしておくとどうなるか。
ノミは何度もガラスの天井板にぶつかって落ちてくる。
これをしばらく続けた後、ガラス板をはずしてみる。
すると、ノミは天井だった高さ以上に跳ばなくなっており、
ビーカーの外に跳び出ることはない。
確かに組織にはガラスの天井がさまざまな形で存在します。
暗黙の制度であったり、経営幹部や上司の頭ごなしの圧力であったり、
あるいは(これが最もおそろしいのですが)自分自身で限界を設ける姿勢であったり。。。
ですが、サラリーマンは、結局のところ
自分の時間と労力をサラリーに換えている職業であり、
組織から言われた範囲で失敗なくやっていれば、
給料は安定的にもらえる(ことに慣らされる)。
だから自分を超える、枠を超える、多数決を超えることをしなくなる。
「なぜ、超えることをしないのか?」と問えば、
「組織がこうだから」「上司がこうだから」など批判や愚痴をこぼすだけ。
それはまさに鈍化病の症状です。
・・・さて、ちなみに、上のノミの天井話には続編があります。
いっこうにビーカーの口から出なくなったノミたちを
再び外に跳び出るような状態に戻すにはどうすればよいか?
―――普通どおり跳べるノミを1匹そのビーカーに混ぜてやること。
(ナルホド!)
*注)
なお、ゆでガエルとノミの天井の話は、ビジネス訓話としてよく用いられるものですが、
科学的に根拠があるかは定かではありません。
●鈍化病3【リスクを取ることに鈍くなる】 “落とした鍵”の話
ある夜遅くに、家に帰る途中の男が、
街灯の下で四つんばいになっているナスルディンに出くわした。
「何か探し物ですか?」と男が尋ねたところ
「家の鍵を探しているんです」とナスルディンが答えた。
一緒に探しましょうということで、二人が四つんばいで探すのだが、見つからない。
そこで、男は再び尋ねる。
「ナスルディン、鍵を落とした正確な場所がわかりますか?」
ナスルディンは、後ろの暗い道を指し示した。
「向こうです。私の家の中」。
「じゃあ一体なんでこんなところで探しているんです?」
と男は信じられないといった口調で尋ねた。
「だって、家の中よりここのほうが明るいじゃありませんか」。
―――(『人を動かす50の物語』M.パーキン著より抜粋)
ナスルディンはなんともトンチンカンな人間だと思いませんか。
しかし、これはサラリーマンのひとつの姿をよく表していると思います。
自分が求める解はたぶん向こうの
「暗い・未知の・想定外の展開を覚悟しなければならない・リスクのある所」に
あるかもしれない―――こう思いつつも、
サラリーマン組織にいると、
「適当に見えている範囲で・既知の・想定の範囲内で済む(予定調和の)・リスクのない所」
で、仕事をやろう(やり過ごそう)とします。
サラリーマン鈍化病の3つめは
「リスクテイクして何かをつかみ取る」ことをしなくなることです。
その暗い未知のゾーンで、もがけば何かつかめるかもしれないことはわかっていても、
混乱や葛藤や迷路を背負い込みたくない。
傷つくことの怖さ、見えないことの不安、もがくことの煩わしさ、
やっても所詮ムダという冷めた達観、などがあるのでしょうか。
そのくせ、酒の場では、「ここは俺のいる場所じゃない!」と大見栄を切ったりもする。
しかし、翌日には、
また、街灯の下で鍵を探す(探すふりをして忙しく振舞う)・・・。
何事も見えている範囲で、リスクを負わず、
組織が求める想定内の結果を出すことで、
身を忙しくし、仕事をやっている気になる。
しかし、永遠に真に自分が求めているものを見出すことはない。
・・・それでも、給料は毎月きちんと振り込まれ、生活は回っていく。
だから、余計にサラリーマンはリスクを取らなくなる・・・。(沈黙)
* * * * *
ちょっとサラリーマン業を揶揄しすぎかもしれませんが、
私は、サラリーマンの味方です!
だからこそ、どういう「働き観」を持って仕事に臨んでいけばいいのか
それを一緒に考えましょうというのが私の生業ですから。