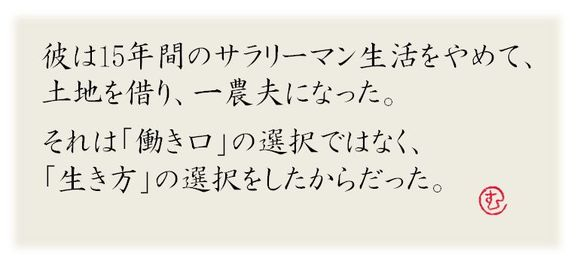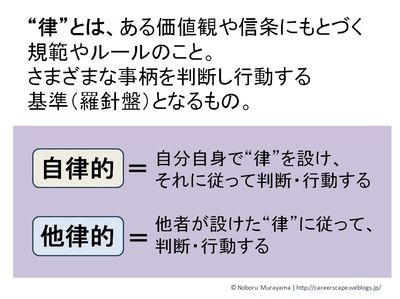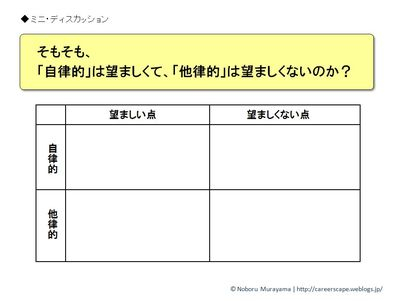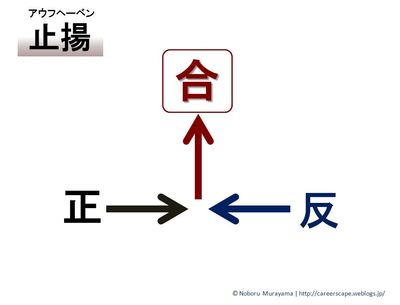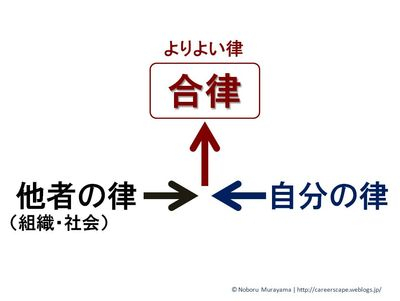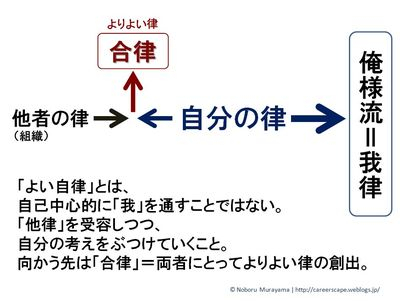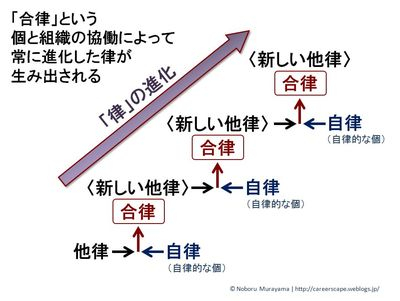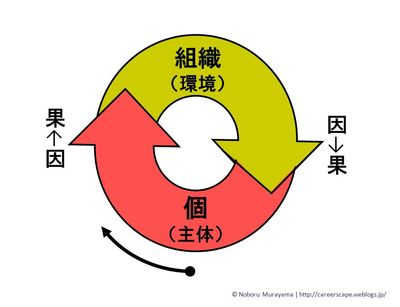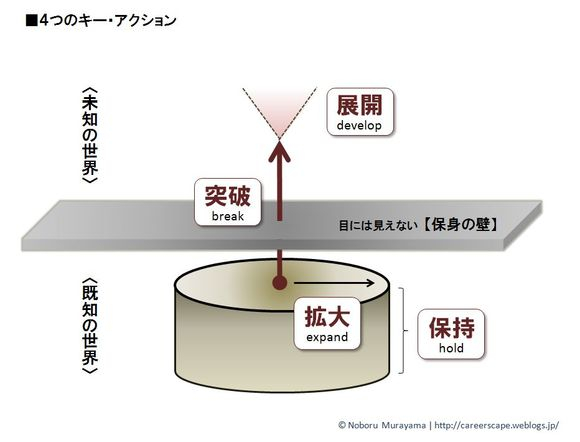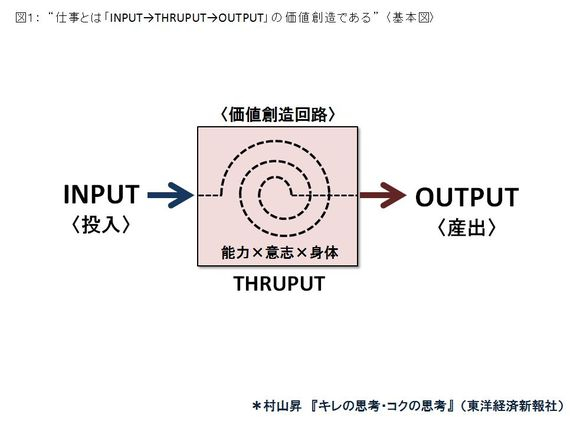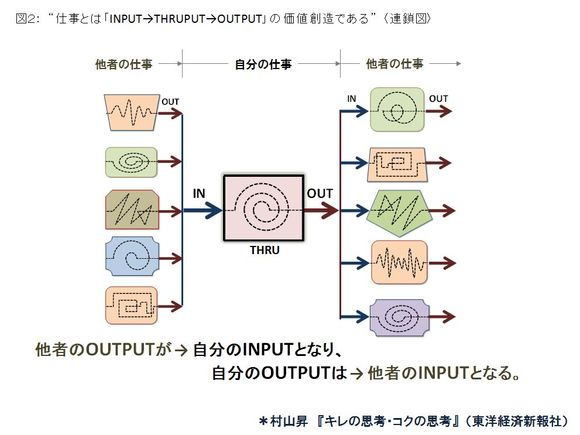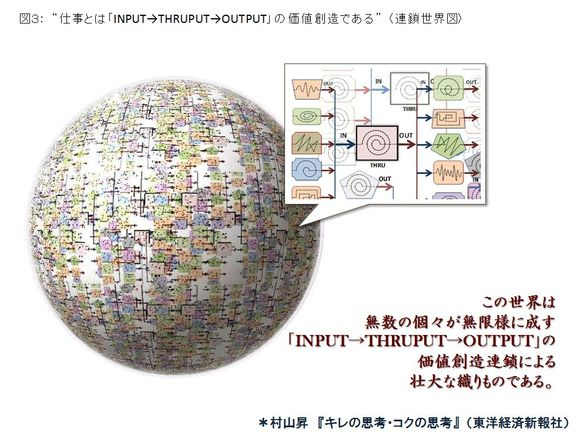留め書き〈030〉~生き方の選択としての職業
彼は15年間のサラリーマン生活をやめて、土地を借り、一農夫になった。
それは「働き口」の選択ではなく、
「生き方」の選択をしたからだった。
先日、都心である中華料理店に立ち寄り一人食事をしていた。
横のテーブルには、団塊の世代らしき男性3人が、紹興酒をちびりちびりやりながら話をしている。
どうやら3人は同じ会社の同僚らしく、
間近にやってくる定年後の再雇用契約について語り合っている。
「あの給料だと小遣いが減る」「外回りの営業に回される」
「貸与されるパソコンが古くて使いにくいらしい」などと、
会社に恨みがましく愚痴を連ねていた。
雇われ根性が染みついたサラリーマンの成れの果ての会話はこんなものかと、
気分が悪くなった。
このような意識の大人が、社員として、親として、市民として伝染させる悪影響は計り知れない。
不景気の時勢であるから、「働き口」を見つけることが難しいときではある。
ただ、幸運にも何かの「働き口」にありついたとして、
そこにしがみつくだけの意識でいてよいものか。
いったん仕事を得たなら、そのなかで、能力を上げ、人とのつながりを築き、興味を拡げていく。
リスクを負って、既存の殻を破っていく挑戦を続ける。
そうして自分が選べる進路の幅を拡げていく。
それをしなければ、
いつまでも「働き口」に使われるだけの身になる。
私たちは、保身という名の怠慢・臆病を排し、
みずからの職業を「生き方」の選択として昇華させていきたい。