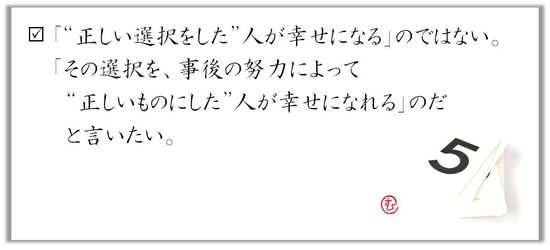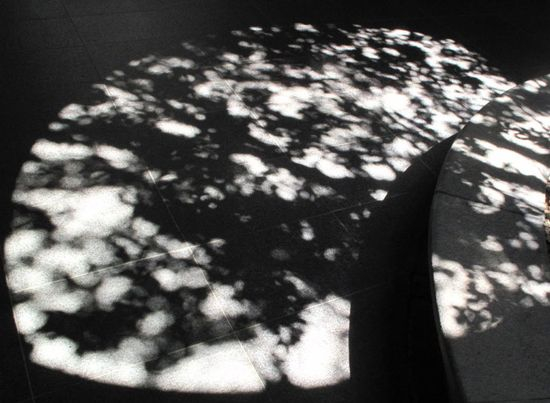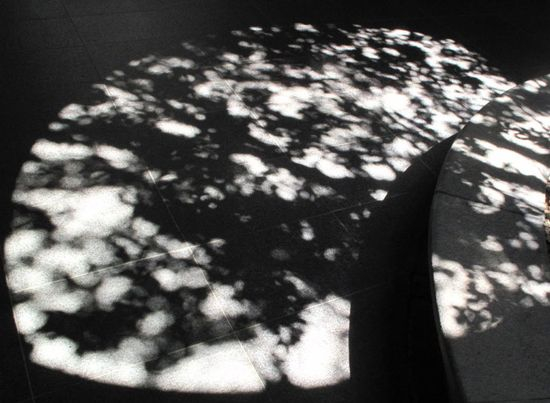
(→前記事から続く)
米国スタンフォード大学『d.school』の「d」とはデザインのことである。
ビジネス・スクールの「b.school」に対抗するものだ。
ここでは物事をクリエイティビティ、デザインの思考から横断的・統合的にとらえ、
イノベーションを事業の変革・創出、社会起業、行政の世界に展開できる人財をつくりだすことを
目的にしている。
『d.school』のウェブサイトをみると、その先行ぶりに驚かされる。
この『d.school』のコアコンセプトは「Design Thinking」(デザイン思考)である。
以下、そのサイトの「Our Vision」のページの記載を簡単に書き出してみる。
〈私たちのビジョン〉
○“We believe great innovators and leaders need to be great design thinkers.”
(偉大な革新者・指導者は、偉大なデザイン思考者である必要があると私たちは信じる)
5年前、私たちはスタンフォードのなかに、デザインの場所『d.school』をつくろう
という夢を持ってスタートした。そして、
『d.school』は、各学部(エンジニアリング、医学、経営、人文学)で学ぶ学生と教官とを
つなぐ“ハブ”のようなものになり、
大きな問題を解決するために「デザイン思考」を学び合い、協働する場所になった。
○“We believe design thinking is a catalyst for innovation and bringing new things into the world.”
(デザイン思考は、イノベーションと新しいことを世の中にもたらす触媒であると私たちは信じる)
『d.school』は、デザイン思考の“プロセス”を学ばせることに焦点を当てている。
教室で出される課題を解決するプロセスでは、
エンジニアリングやデザインの世界から方法論を引き出したり、
そしてそれらを、人文学から得たアイデアや、社会科学から得た思考道具、さらには
ビジネスからの洞察と組み合わせたりすることが要求される。
そのプロセスは、各学問分野から集まったチームメイトたちを
共通の目的の下につなげる、言わば“糊(のり)”のようなものになるだろう。
デザイン思考は、行うこと(doing)によって最もよく学ぶことができる。
デザイン思考のプロセスにおいて大事なことは、
熱意を持ち、人と協同して、いち早く試作品をつくり、フィードバックを得て、
また試作を繰り返す―――そういう態度である。
この『d.school』で重要なことは、
あなたが「どう行うか」であり、「結果を出すこと」ではない。
なぜなら私たちは、イノベーターを育てることに主眼を置いており、
特定のイノベーションを獲得することではないからだ。
○“We believe high impact teams work at the intersection of technology, business, and human values.”
(高い効果をあげるチームは、テクノロジー、ビジネスおよび人間の価値の交差する場で働くと私たちは信じる)
『d.school』はスタンフォードの諸研究活動を結び付け、
異なるバックグラウンドをもった人びとによる多様性のあるチームを結成させる。
私たちのクラスでは、“multidisciplinary”のアプローチが取られており、
例えば「哲学の観点を取り入れたコンピューター科学」のように
複数の学問分野をミックスさせた形で鍛錬が行われる。
○“We believe collaborative communities create dynamic relationships that lead to breakthroughs.”
(協働的な集団は、活動的な関係性をつくり、そしてそれがブレイクスルーを導くと私たちは信じる)
『d.school』は、常にキャンパス内と産業界から横断的に人を集め、
異なる観点を取り入れている。これこそがこの場を活気づかせている要因である。
私たちの文化は、平板なアイデアを超えるために、
(たとえそれが不便なことであっても)素早く徹底的に
相互で協働的にアイデアを出し合うことにある。
積極的なコラボレーション―――これが『d.school』のイノベーションを生む文化の基である。
大学教育のみならず、行政も企業現場も、“専門分化”が問題となっている。
スピード化や効率化を求め、すべてを細分的に分業化してきた結果、
全体を見失い、タコツボ化や縦割り化、分断化の弊害が顕著になってきた。
そのため、世は「新しい統合」のあり方に関心を集めている。
その「新しい統合」のあり方は、社会、組織のみならず、一個人にも当てはまる。
一個人が「全人的」に自分の存在を使う、活かすことがますます求められている。
そうした「新しい統合」への教育分野のチャレンジとして、
この『d.school』はとても野心的である。
開設されている科目も面白いものが並んでいる。
- Design Thinking Bootcamp
- Entrepreneurial Design For Extreme Affordability
- Cross-Cultural Design
- Personal and Interpersonal Dynamics
- Prototyping Change in Entrepreneurial Firms
- Transformative Design
- From Play To Innovation
- Media + Design
- Designing Liberation Technologies
- Designing for Sustainable Abundance
- Creativity and Innovation
各科目のカリキュラム概要はウェブサイトに上がっているので
興味のある読者の方は見ていただきたいのだが、
全体に共通する特徴は、先ほどのビジョンのところにあったとおり
“multidisciplinary”(複合的な分野の鍛錬)であること、
そして米西海岸シリコンバレー地域特有のベンチャー精神が脈打つこと、
さらにはそのベンチャー精神の向けどころがソーシャルビジネスであることだ。
例えば私が最も感心したのは、
2番目の「Entrepreneurial Design For Extreme Affordability」である。
うまく訳せないのだが「極めて資金的に可能な起業のデザイン」というような科目である。
同科目の導入部分には次のような一文がある。
「農業用の灌漑網を整備するには何十万ドルも費用がかかる。
送電線を張り巡らせるには何百万ドルもの資金が要る。
しかし、30ドル以下の送水ポンプや電灯を供給することで
貧困への問題を再考できるとすれば、それは極めて“値ごろ感のある”ものだ」。
発展途上国の貧困問題を考えると、その解決のための方策の規模が大き過ぎて、
誰しも気が遠くなり、現実味のある思考と行動が鈍る。
しかし、この科目は、そうした貧困を救うための起業は十分に可能であり、
しかも莫大な資金でなく30ドル以下のモノからでも始められることを学ぶものである。
これまでに実際、このクラスでは、
簡単に安く作ることのできる農業用の送水ポンプや
太陽電池を用いたLED電灯をメーカーと一緒に開発して現地に普及させている。
科目の案内にはこうある―――
What's our mission? To treat the poor as customers, not as charity recipients.
(私たちのミッション;それは貧困の人びとを施しを受ける人としてではなく、
お客様としてとらえること)
貧困に陥る地域の人々にも購入することのできる“値ごろのモノ”を供給し、
彼らの自立的生活を助けるビジネスをデザインする。
それがこの「Entrepreneurial Design For Extreme Affordability」という科目だ。
* * * * *
私はかれこれ16年前に「情報デザイン・情報の視覚化」を学びに米国に留学した。
当時、出版社に勤め、私費留学したいので休職させてほしいと会社に要請したのだが、
会社の人間は誰しも「情報のデザイン???を勉強しに???」のような感じだった。
私は情報のネット流通や電子書籍の時代を見越してその勉強が必要だと直感したのだが、
国内にはそれに適合する科目を設置する教育機関はなかった。
米国にはすでにいくつかの大学が取り組んでいて、その中から結局私はシカゴにある
イリノイ工科大学のInstitute of Designのマスターコースに入学した。
いまでは「情報デザイン」と検索すればいろいろと出てくるし
美術系大学ではそのコースや科目を設置するようにもなった。
また「図で考える」というような本もさまざまに刊行されている。
時代の変化、時代の要請に教育があっぷあっぷで後追いしているのが日本の現状だ。
それこそ日本の教育界には、横断的統合的にデザイン・シンキングをして、
時代が要請する教育プログラムをいち早くプロデュースできる人間が求められている。
米国がその点でいつも先進的活動的でいられるのはなぜか?―――
私は(自身の留学時代の観察も含めて)次の4要因が揃っているからだと思う。
〈1〉教育を柔軟的かつ革新的に創造できる「学びの作り手」たちがいる
〈2〉アクティブな「学び手」がいる
〈3〉教育プログラム・サービスを支える「パートナー企業」がいる
〈4〉多様な修学経験をキャリア価値として評価する「文化」がある
まず1番目、「学びの作り手」とは教育者、教授たちに限らない。
米国の特に大学院の現場では、産業界のリーダー(CEOたち)や
行政からのプロフェッショナルらがどんどん入ってきて教育サービスの作り手に回る。
『d.school』の場合、「デザイン・シンキングの学校を作ろう!」と提唱したのは、
米国で最も有名なデザインファームのひとつIDEO社の創業者デイビッド・ケリー氏だったし、
巨額の創設資金を提供したのが元SAP CEOのハッソ・プラトナー氏だ。
私には、学外からのこうした人物たちが純粋な熱意を持って、
アイデアを出し、カネも出し、手も出しながら、
理想の学び舎をつくろうとしている光景が容易に想像できる。
そして2番目、アメリカ人は良くも悪くも、キャリアパスが短期で変わることが多い。
それは社会全体が終身雇用を前提にしていないこともあるのだが、
その分、就職と修学を交互に繰り返すという行動習慣も生まれる。
次の職を見つけるまで、また大学に戻って何かを学ぼうというのはごく普通の感覚だ。
その意味で、米国の大学は再就職意欲に燃える人たちが集うアクティブな場なのである。
日本などは、いったん会社に入り定年まで安定的に雇われてしまうと、
ついぞ大学には縁がなくなる。
これはある意味、日本の大学を弱くする一因でもある。
そして3番目、企業の協力だ。
先ほど紹介した貧困国を救うための送水ポンプやLED電灯のプロジェクトには
協力企業が付いている。
米国が新種の教育プログラムを立ち上げることを積極的にできるのは、
産学が活発に結びついていることによる。
もちろん企業側は事業の種を見つけることを目的としているのだが、
将来的に儲けられそうかどうかは別にして、
そういうことを面白がる、社会的使命と感じるという企業・経営者が多い。
最後に4番目、これは2番目とも関連するのだが、
キャリアに意欲的なアメリカ人は生涯のうちで就職と修学とを往復する。
途中途中でどんな修学経験をしたかというのは、
職務履歴と同様に自分のキャリア価値を表す重要な事項になる。
どんなにマイナーでどんなにヘンテコな学問でもそれを修学すれば、
それはひとつの立派な個性・自律性として評価しようとする社会全体の文化がある。
当然、再就職の際に、人材採用側もそうした評価眼で見てくれる。
(特定の大学・学位・資格に人気が集中し、そこに評価する眼も集中する―――
そんなところが日本にはないだろうか)
私もいま教育ビジネスに身を置いている。
もちろん時代の要請を感知し、先取りするようなプログラム開発をやりたいと思っている。
(いまだ発展途上ではあるが)キャリア教育プログラムを
『プロフェッショナルシップ研修』として開発したのは、
私なりの「理の人・目の人・愛の人」育成への解のひとつである。
いずれにせよ、商品・サービスというものは、「よい顧客」によって鍛えられる。
今後もよい顧客企業・受講者と結びつきながら、よいものを提供していく決意である。
【関連読書】
『デザイン思考が世界を変える』ティム・ブラウン著(千葉敏生訳)早川書房

「リゾナーレ」は、オリベッティ社のタイプライターのデザインなどで知られる
イタリア人建築家マリオ・ベリーニ氏の設計によるものです。
開業時(たぶん20年ほど前)、なにかの建築誌で
「建築が実際に出来上がってみてどう思うか」との問いに、ベリーニ氏は
「まだ終わっていないよ。蔦(ツタ)が伸びるまではね」というような答え方をしていた記事を思い出します。
確かに建ったばかりのころはコンクリートの寒々しい印象があったのですが、
今では柱や壁面に蔦が不規則に伸び、味わい深い趣きを与えるようになりました。
静的な建造物に、「蔦が織りなす自然のリズムの生長」という面積・時間を取り込んで作品とする
ベリーニ氏の企てに、今さらながらいたく感心します。
読書や散歩をしていて発想が湧きやすい場所というものがありますが、私にとってここはその一つです。
開業のころからたびたび訪れていますが、一時期は閑散とした状況になったものです。
ですが最近は、経営が星野リゾートに変わり、その再生によって見事に活気が戻りました。
経営の力というものをまざまざと見たという感じです。
そして軽井沢の「丸山珈琲」も小淵沢に進出 (Welcome!)