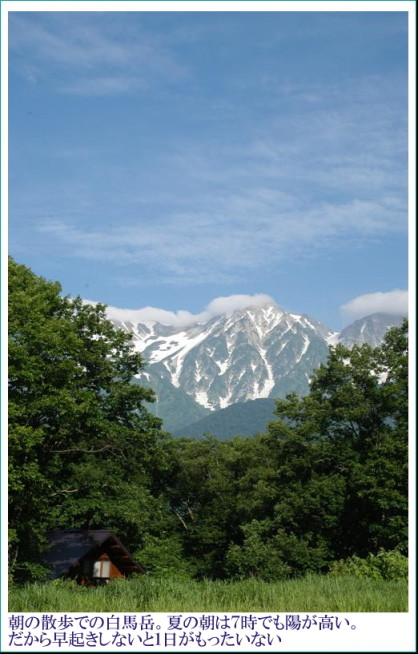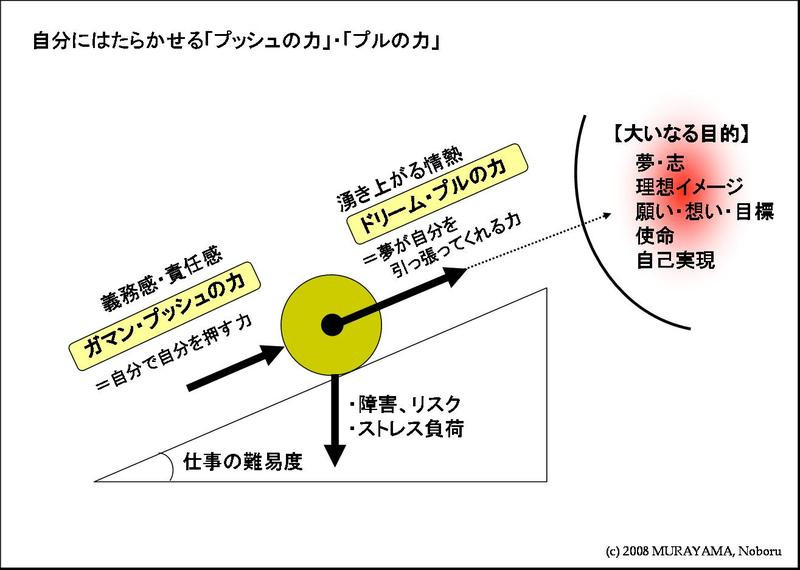いまや朝青龍関をめぐる横綱品格論議は、世間を二分するほどの話題になりました。
街の声は、
「結局、真剣に反省していないんじゃないの。横綱として問題あり」というものと、
「やっぱり強い横綱がいればこそ場所が盛り上がる」というものとで、
完全に分かれています。
私個人の中でも、
やはり横綱たる者、相応の品格を備えてほしいという思いと、
多少破天荒で逸脱したキャラであっても
強くて魅力的な取組を観せてくれるならそれでよし、という思いが微妙に交錯します。
(いずれにしても私は、朝青龍関より相撲協会と現行の相撲システムを問題視します)
巷においても、また一個人の中においても
これら2つの相反する思いにかられるのはなぜでしょう?
◆求めるものが異なる「道」と「ゲーム」
それは、相撲という日本の伝統競技を
相撲道=「道」とみるか、
相撲スポーツ=「ゲーム」とみるか
の観点で思いが違ってくるからだと思います。
(*ここでの「ゲーム」とは、遊興としてのゲームよりももっと広い意味です)
「道」とは、
・真理会得のための全人的活動であり、
・そこには修養・鍛錬・覚知があります。
・最上の価値は「観を得る」ことにあります。
・道を行なうには、明快なルールはありません。
しきたりや慣わし・型・格・美を重んじ、
その過程における世俗超越性・深遠性が行者を引き込んでいきます。
他方、「ゲーム」とは、
・他者と勝敗を決するための能力的(知能・技能)活動であり、
・そこには競争・比較・優劣があります。
・最上の価値は「勝つ」ことにあります。
・ゲームには、ルールがきっちり設定されています。
そのルールの下で合理的、技巧的、戦略的なやり方を用い、
客観的に定量化された得点を他者よりも多く取ったほうが勝者です。
そのときの優越感、征服感がプレイヤーを満足させます。
道とゲームとは、微妙に似通っていながら、
よくよく考えると両極のものであるようにも思えます。
朝青龍をめぐる二分する思いも
「道としての相撲」観点からすると、横綱失格→残念・けしからんとなり、
「ゲームとしての相撲」からすると、強いプレイヤーの存在→ガンバレ!となるわけでしょう。
今後、朝青龍関が相撲道を究めて、品格を備えた横綱に成熟していくのか
単に強い力士として相撲ゲームを面白くするプレイヤーに留まるのか
(それともK-1など他の格闘ゲームに戦場替えするのか)
そこは本人次第といったところでしょうか。
ところでその一方、
毎度の場所でひときわ人気を集めているのは角番大関・魁皇です。
相撲ファンが魁皇関を応援するのは、もう勝ち負けということより
カラダがボロボロになってもひたむきに相撲「道」を求めようとする
その姿だろうと思います。
ボロぞうきんになるまで現役にこだわり続ける。
それは、三浦カズ、桑田真澄、野茂英雄もそうです。
彼らはすでに肉体的なピークを過ぎ、
ゲームプレイヤーとしての最上価値である「勝つこと」からはどんどん遠ざかっています。
しかし彼らは、サッカー道、野球道を求めてやまない。
そんな姿もまた、日本人の心のヒダに染み入ってくるものがあります。
◆「よい経営者」とは?
さて、ここからがきょうの核心部分です。
「道」なのか、それとも「ゲーム」なのか・・・
それは“経営”にもいえることだと思います。
(ここでの“経営”とは、特に企業・ビジネスの経営をいいます)
私がかつて出版社でビジネス雑誌の編集をやっていたころ、
年間で100人近い経営者やビジネスのキーパーソンにインタビューをしていました。
そこで感じたのは、
経営を「ゲーム」(=利益獲得競技)ととらえている人がとても多いということでした。
経営は「道」であるとハラを据えてとらえている人はきわめて少ないと思います。
(もちろん一人の経営者の中で、経営は道かゲームかというのは、
白か黒かという立て分けではなく、あいまいなグレー模様でとらえるわけですが)
「よい経営者」とは、どんな経営者でしょうか?
・・・・この問いの答えは、千差万別に出てくるでしょう。
(それは、「よい横綱」とはどんな横綱ですかと問うのと同じように)
「経営はゲームである」という観点に立てば、
斬新な経営手法を考えつき、利益をどんどん創出し、
その会社を勝ち組にしてくれる経営者がよい経営者でしょう。
ただ、その金儲けの際、法律スレスレの手を使っている、あるいは、
従業員を大事にしない、社長室がやたら豪華で私的に交際費をつかう、
などの状況だったらどうでしょう、、、
相撲ゲームの世界においては、「ともかく強けりゃイイ・許せる」といって、
私たちはやんちゃな横綱・朝青龍関を見守ることができます。
では、経営というゲームの世界において、
人格的資質やその経営手法に問題のある経営者をして
「ともかく利益を出せりゃイイ・許せる」となれるかどうか。。。
私はビジネス雑誌の取材で、ときどき、中小企業も訪れました。
確かに、金儲けはヘタかもしれないけれど、
堅気に自分の商売を貫き、時代に対応する努力を惜しまず、
従業員の雇用を守ることに一所懸命な経営者も世の中にはいます。
「経営は道である」との観点に立てば、
それはひとつの「よい経営者」であると思いました。
◆経営がゲーム感覚に偏ることの弊害
私は、経営の勉強もしましたし、現在も自らのビジネスの経営を行なっている身ですので、
「経営は道なり」という美辞麗句で利益志向を排除するつもりはありません。
ただ、経営者の利益志向が、利己的な拝金主義に陥っている状況を気にかけるものです。
昨今の企業の不祥事の数々、
チキンゲーム化するマネー投機合戦、
陣地取りゲームに堕するM&A、等々、
これらはいずれも、経営が「ゲーム感覚」となり、
「儲けりゃいいんでしょ」「勝てば官軍でしょ」のような思想が蔓延しているところに起こっています。
加えて、経営の内実を問わず、
結果的に儲けた経営者をビジネスヒーローとして簡単にあおるメディアの軽率さも目に付きます。
さらには、投資家・株主の間断なきプレッシャーもあります。
経営者に品格があろうとなかろうと、
ともかくゲームに勝て、株価を上げろ、配当を上げろ、のプレッシャーです。
真に優れた経営者というのは、
経営を「ゲーム」と「道」との間で適度なバランスを保つことができる人だと思いますが、
現在のビジネス世界においては、
そのバランスが不健全に「ゲーム」に偏っているように感じます。
資本主義経済という一大システムが織り成すゲームは、実に複雑で巧妙です。
だからこそ経営というゲームは面白くてたまらない。
勝てば勝つほどに、富が手に入り、その富は(このシステム下では)また富を生む。
富はさまざまな欲望も満たしてくれる。
逆に言えば、貧はますます貧を呼ぶ。
資本主義下のゲームは、その意味で“暴力的”といえるでしょう。
ゆえに、経営には一方で「道」というものがいる。
◆資本主義に徳はあるか?
アンドレ・コント=スポンヴィル著の『資本主義に徳はあるか』(紀伊国屋書店刊)は、
きょうのこうした点を考えるにあたっては、是非おすすめの1冊です。
ソルボンヌ大学で哲学の教鞭をとる彼は、同著で道徳と経済の関係を省察していますが、
著書タイトルに対する彼自身の答えを紹介しましょう。
「価格を決定するのは道徳ではなく、需要と供給の法則の役割です。
価値を創出するのは、徳ではなく、労働です。
経済を支配するのは、義務ではなく市場です。
・・・・(中略)・・・
『資本主義に徳はあるか?』という私の問いに対する解答は、
“否”ということになります。
資本主義は道徳的ではありません。
ましてやそれは反道徳的ではありません。
資本主義は、―――全面的に、徹底的に、決定的に―――非道徳的なのです」。
すなわち、
資本主義のメカニズムは、それ自体、悪徳のものでも善徳のものでもない。
それは本来、冷たくも熱くもなく、無機質に無関心にはたらく機能システムである。
だから道徳的であるかどうかとは無関係である。
資本主義を道徳的に使うか、反道徳的に使うか、
結局、それは経済を行なう人間の問題であるとの指摘です。
「経済」の語源は、「経世済民」(けいせいさいみん)です。
それが示すとおり、民を救うことが経済の原義としてあります。
その意味で、経営はある部分、大義を目指す「道」であってほしいものです。
経営においても、相撲においても
「強いから横綱である」というのではなく、
「強いからこそ横綱になる必要がある」のだと思います。