留め書き〈038〉~創ることと受けとることについて
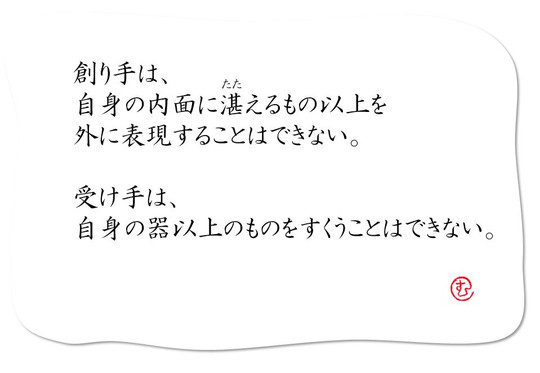
創り手は、
自身の内面に湛えるもの以上を外に表現することはできない。
受け手は、
自身の器以上のものをすくうことはできない。
だから、もっと豊かに湛えよう。
器を大きくしていこう。
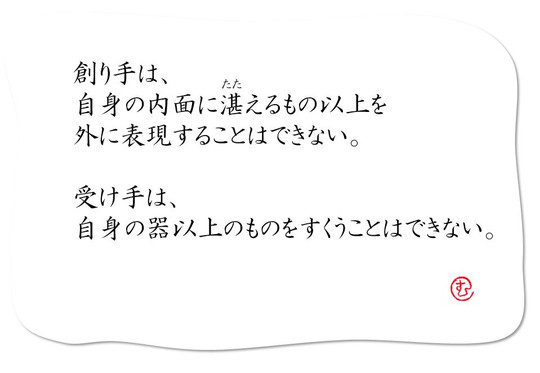
創り手は、
自身の内面に湛えるもの以上を外に表現することはできない。
受け手は、
自身の器以上のものをすくうことはできない。
だから、もっと豊かに湛えよう。
器を大きくしていこう。
◆室伏選手の描いた3段ピラミッド図
あるときテレビの番組で、ハンマー投げの室伏広治選手がボードに絵を描いてインタビューに応じていました。その絵はこんなものでした―――
彼はアスリートとして必要な鍛錬は3段だと言います。
一番上が「skill」(技術)。
次に「strength」(強さ)。
一番下にくるのが「fundamental」(基礎)。
で、理想形は図の左に書いたようなピラミッド形。ところが右のように「fundamental」が小さい状態では、上の2層をいくら鍛えてもパフォーマンスが上がらないと言う。ヘタをすると、2層の「strength」を強めようとするあまり、ケガをするリスクも高める。
37歳になった自分は「skill」や「strength」の伸びシロは限られてきたかもしれないが、身体をどう使うかといった基本・基礎の部分はまだやりようがいくらでもあるような気がすると。だから、いま自分は最下層にある「fundamental」を見つめ直している。そのために、例えば赤ちゃんをじっと観察して体の動きを研究している、と語っていました。
その成果あってか、この番組の翌年(2012年)に行われたロンドン五輪で、室伏選手は見事銅メダルを獲得。私はこのインタビューを観ながら、道を究める超一級の人物の飽くなき探求心に感心するとともに、熟達は常に基礎の継続鍛錬によって進んでいくことを再認識しました。そして奇遇にも室伏選手の3段図は、私が考える「仕事を成す・キャリアをつくる4要素〈3層+1軸〉」と通底するとも思えました。
私がとらえる3層とは、
1層目に、業務をこなす「知識・技能」
2層目に、成果を出す力である「行動特性」
3層目に、評価や判断、動機づけの基となる「観・マインド」がくる。
昨今のビジネス現場では、ともかく目の前の業務処理、目に見える短期的な成果への要請が強いために、本人の意識も組織の教育意識も1層・2層に偏っていきます。3層が放置されたままになります。すると、上の室伏図の悪い例のように1層・2層でっかちの状態になってしまいます。仕事成就・キャリア形成においても、やはり、最下層に敷かれる基盤が強くなければ1層・2層は十全に活かされないと私は考えます。本田宗一郎もこう言っています。
「私の哲学は技術そのものより、思想が大切だというところにある。
思想を具現化するための手段として技術があり、
また、よき技術のないところからは、よき思想も生まれえない。
人間の幸福を技術によって具現化するという技術者の使命が私の哲学であり、誇りである」。
―――本田宗一郎(『私の手が語る』グラフ社)
また、北大路魯山人は書についてこう語っています。
「要するに人物が出来ておらなければならぬ。
手習いでなく人物をつくる方が根本問題であって、
これが一番書道の上にも肝要なことであります。
(中略)人物の値打ちだけしか字は書けるものではないのです。
入神の技も、結局、人物以上には決して光彩を放たぬものであると思います」。
―――北大路魯山人(『魯山人著作集(第二巻)』五月書房)
◆全人的な育成が図られてこそヒトは「人財」となる
ピーター・ドラッカーは『現代の経営〈下〉』の「人を雇うこと」という章の中でこう述べています。
「働く人を雇うということは、人を雇うということである。
手だけを雇うことはできない。手の所有者たる人がついて来る」。
「今日の訓練プログラムの多くは人を柔軟にするよりも硬化させている。
理解を与えるのではなく小手先のスキルを教えている」。
昨今、40代社員のキャリアクライシス問題が顕在化しつつあります。40代に向けたキャリア開発研修ができないかというご相談もしばしば受けるようになりました。20代から30代半ばまで、ひたすら現場の業務戦力として手だけ(つまり知識や技術だけ)を磨いてきたものの、やがて旬の技術を必要とする仕事を若手に引き渡すようになり、けれども管理職の道があるかといえばそうでもない。道があったとしても部下を率いることに向いていない。いわゆる非管理職ミドルたちがどう仕事と向き合い、組織の中で自分の存在意義をつくり出せるかという問題です。
40代のキャリア研修がとても難しいことを、私は経験上知っています。働くことに対する観・マインドが硬直化してしまっている人が多いからです。30代でも難しいところがあります。自律的に自分を開くように固まっているならよいのですが、「自分のキャリアをどう開いていけばいいかわからない。会社がきちんとキャリアパスを用意すべき」といった他律的で環境依存の強い観で固まってしまった場合は、もはや単発の研修ではどうすることもできません。
ドラッカーは別の箇所で、組織がヒトを最大限に活かしていくために真に必要なのは、訓練プログラムではなく、教育プログラムだと言います。すなわち手だけを訓練するのではなく、全人的に教育せよと。「人の成長ないし発展とは、何に対して貢献するかを人が自ら決められるようになることである」と彼が指摘するように、職業人としての在り方を自律的に考えられるのは、若いころから観・マインドがそのように涵養されてこそです。
企業が人を雇い、雇った人の教育に関し、どこまで面倒をみるべきでしょうか。手だけを訓練し、いわば取り替え可能な資源として育てることでよいのでしょうか。それとも、全人的な教育を施し、その人でなければならない価値を生み出す資産として育てるべきでしょうか。前者は「ヒト=資源・人材」のとらえ方、後者は「人=資産・人財」のとらえ方です。それこそまさにその企業の「ジンザイ観」が問われるところです。
◆観・マインドは教育できるか
・「仕事観なんてものは仕事にもまれて修羅場のいくつかをくぐれば自然にできてくるものだ」
・「仕事の哲学は上司が背中で教えるべきこと」
・「そもそも価値観は個人個人で多様なものだから一律に教育すべきものではない。自己啓発にまかせればいい」
・「自律心を教えること自体が自律に反する」
・「そもそも観や働く意識を教えることができるのか。(上から下へ)教えるという形が妥当なのか」
……観・マインド次元の教育には、いろいろな意見があります。それに対して私の考えをいくつかまとめます。
〇観は教えられない。ただ気づきの材料を与えるのみ
一人一人の内面の底に横たわる観・マインドを醸成する研修においては、何かを“教える”というより、何かを“気づかせる”というものになるべきでしょう。私が研修の中で受講の皆さんによく言うのは、講師が短い研修時間の中でせいぜいできることは、“酵母菌を撒く”ことぐらいだということです。つまり、酒や醤油の醸造において、みずから熱を発し、質的変化をしていくのは主原料である米や大豆です。しかし、その醸造変化のためには、“酵母菌”という触媒がなくてはならない。その意味で、講師は酵母菌となるような思考の材料、思索のヒント、行動の刺激を講義やワークの中に収めてプログラム化するのみです。
そのとき受講者によって反応の早い人、遅い人などの違いは出てくるでしょう。いずれにせよ、そうした考える材料を若い時期に与えられたかどうかは、その後の仕事人生において大きな差になります。「あのひと言を聞いておいたから、人生の転機が生まれた」ということは往々にしてあるものです。
〇事業組織においては、共有すべき観があるほど強い
観は人それぞれ多様だから一様に縛ることはよくないというのは、社会全体には言えることですが、こと事業体にあっては、むしろ観を共有できる人が集まって、強い思いの製品・サービスをつくるほうが望ましい姿といえます。共有できる理念・バリュー・文化が土壌としてあって、その上に多様で強力なアイデアが出る。昨今、顧客に強く支持される企業の共通点はそういったところにありはしないでしょうか。
〇上司の背中は語ってくれるか
仕事観は上司の背中から学び取るものである、はそのとおりだと思います。私もサラリーマン時代、上司の言動からさまざまなことを学びました。ですが、そうした背中で語ってくれる上司に巡り会える確率はむしろ低いと言えるかもしれません。私は研修プログラムで「ロールモデル探し」というワークをやりますが、身近の上司をあげる人は実は少数派です。また、仮に上司の考え方が偏向していて影響力が強い場合、それに感化された部下は、ある種、子飼いのような存在になり、派閥形成に荷担することも起こります。観の醸成を上司の背中に任せきりにすることにはリスクがあります。
〇観から湧くエネルギーこそ最強
従業員のほんとうのやる気を引き出そうと思えば、経営者や管理職、組織は、一人一人と観の層で対話せざるをえません。組織側は、まず自らの観を差し示し、それについて従業員も観のレベルで耳を傾け、意見したり、共鳴したりする。そのレベルから起こるエネルギーこそ最強のものです。今期はいいボーナスがもらえたとか、業務がうまくこなせたといったときに起こる喜びよりもはるかに強い力がそこにはうずまいています。個人の観には立ち入れないからというのではなく、観のレベルの話(就労観、事業観、人材観、キャリア観、社会観、理念、コアバリューなど)を真正面からぶつけて、ふだんの職場でも研修の場でも侃々諤々やろうという姿勢こそ大事ではないでしょうか。
◆入社3年~5年次フォローアップ研修で行うこと
ここからは私が新卒入社3年~5年次社員に向けたフォローアップ研修において、どんな観・マインド醸成プログラムを行っているのか、その内容をいくつかの観点から説明します。
〈1:根源的なテーマを考えさせる〉
観・マインドとはここでは、思考や感情、記憶をつかさどる意識基盤、単純には、ものの見方・とらえ方として考えています。自分が対面するものごとにどんな価値(善悪、美醜、真偽、是非、損得、意味、優先順位など)を与え、どう反応するかを決めるものです。こうした観・マインドは、根源的な問いを考えさせるほど、その醸成度合いや向きがわかります。例えば、研修ではこんなテーマの問いを投げかけます。
・「仕事とは何か?」「事業とは何か?」
・「仕事・事業の目的は金(給料・利益)を得ることか?」
・「成長とは何か?」
・「自分は世の中に何の価値を提供する職業人か?」
・「自律的な働き方とはどういう状態をいうか?」
観・マインドを強く醸成している人ほど、「仕事とは何々である」「成長とは何々することである」といった定義づけを自分の言葉で豊かに表現できます。そしてなぜそう考えに到ったのかと問われれば、具体的な経験や材料をあげて説明することができます。すなわち、観・マインドは、具体と抽象の両輪によって醸成されるわけです。
入社数年も経てばすでにさまざまな経験を積んでいます。しかし、その経験を抽象化してものごとの本質や原理をとらえられるかどうかは人によってかなりの差が出ます。観・マインドの醸成は多分に抽象化能力の影響を受けるので、こうしたものごとの根っこを考えさせる習慣が必要です。
具体的な体験から本質・原理を抽象化し、観として肚に据えることがなぜ重要なのか?───それは、ものごとを個別具体的にとらえるレベルに留まっていると、永遠に個別具体的に処置することに追われるからです。そのことを次の例で説明しましょう。
下に並べたのは英単語の問題です。それぞれのカッコ内には前置詞が入ります。1つ1つ答えてください。
・a fly[ ]the ceiling
(天井に止まったハエ)
・a crack[ ]the wall
(壁に入ったひび割れ)
・a village[ ]the border
(国境沿いの町)
・a ring[ ]one’s little finger
(小指にはめた指輪)
・a dog[ ]a leash
(紐につながれた犬)
……さて、どうでしょう。
正解は、すべて「on」です。ところで、私たちは前置詞「on」を「~の上に」と習ってきました。習ってきたというか、暗記してきました。そうした暗記的なやり方で英語と接してきた人は、「天井にさかさまに止まった」とか「壁に入った」とか、「国境沿いの」などの言い表しに思考が発展しないので、それぞれの問題に戸惑ったことでしょう。そうして正解を見て、また1つ1つ、「on」の使い方を丸暗記していくことになる。
これに対し、いま私の手元にある一冊の英和辞典『Eゲイト英和辞典』(ベネッセコーポレーション)の帯には、こんなコピーが記載されています───
「on=『上に』ではない」と。
さっそく、この辞書で「on」を引いてみる。すると、そこに載っていたのは、下のような図でした。
「on」は本来、縦横・上下を問わず「何かに接触している」ことを示す前置詞だといいます。確かにこの図をイメージとして持っておくと、さまざまに「on」使いの展開がきく。この辞典は、その単語の持つ中核的な意味や機能を「コア」と呼び、それをイラストに書き起こして紙面に多数掲載しています。10個の末梢の意味を覚えるより、1つの「コア・イメージ」を頭に定着させたほうがよいというのが、この辞書づくりのコンセプトなのです。
まさにここで出てきた「コア・イメージ」に基づく学習が、ものごとを抽象化して押さえることにほかなりません。
私たちは、ものごとの抽象度を上げて大本の「一(いち)」を本質・原理として肚に据えれば、以降はそれをいかようにでも具体的に展開応用することができる。逆に言えば、抽象化によって「一」をとらえなければ、いつまでたっても末梢の出来事をその都度まちまちに対応することになります。観・マインドが醸成されていないと、場当たり的・感情的に、情報や環境に振り回され、判断や行動が安定しないのです。こういう働き方では周囲からの信頼も得られませんし、第一、本人が疲れます。
具体的な体験をたくさん積めば自然に観が養われるというのは誤りです。抽象化させて「一」をつかませる思考態度を身につけさせないかぎり、いつまでもモグラたたき状態で事に当たることになります。
〈2:比喩(メタファー)で考えさせる〉
「働くこととは何か」「仕事をつくりだすこととは何か」「キャリアをひらくとはどんなことか」……こうした曖昧模糊とした問いに対して、「あ、そうか、そういうことだったのか!」と腹にすとんと落ちてくる答えをみずから得るためには、比喩による思考材料を与えることが有効です。
例えば、「自立」と「自律」の違いを、あなたの会社の社員はどう理解しているでしょうか?(一般的にはそもそも、両者を一緒くたにとらえているほうが多いですが)
私は、これを「航海」という比喩で説明しています。すなわち、「キャリア・人生は航海」であって、
●「自立」とは;航海に耐えうる「船」を造ること
●「自律」とは;ぶれない「羅針盤」を持つこと
●「自導」とは;地図に描いた目的地に船を進めること

こうした比喩を使うことで、受講者の理解はすとんと進みます。さらに私は、レゴブロックの創作ゲームを加えています。創作に使うブロックや文具の数を増やしたり減らしたりして進んでいき、最終的に受講者が次のことをキャリア観として肚に落とせるように意図するものです。
●「自立」を高めるとは、能力の手駒を増やして船を大きく堅固にすること
●「自律」を高めるとは、創作物に自分なりの視点、コンセプトを付与すること
●「自導」を高めるとは、自分の作品群に世界観を打ち立てること
そしてこのゲームプログラムでつかんだ比喩による本質を、次は現実の仕事・キャリアにどうつなげ、明日から行動をしていくかに誘っていきます。
3〈古今東西の名言・箴言を紹介する〉
1番目の箇所でも触れたとおり「大本の一」を肚に据えることは、長き職業人生にあってとても大事なことです。世の中にはその「大本の一」を言い得た言葉があります。私は研修コンテンツの中に、古今東西の偉人、哲人、達人が遺した名言・箴言をふんだんに盛り込みます。
それらは哲学の言葉です。昨今のビジネスパーソンに決定的に欠乏しているもの、それは哲学の心です。科学の心によって、分析したり戦略を立てたりすることは大事ですが、それと同時に、その科学の心をつかだどる哲学の心も磨かねばなりません。
「よき仕事」をつくるものは、最終的に「よき哲学」です。
「強きプロフェッショナル」をつくるものは、「強き哲学」です。
「心が変われば、行動が変わる。
行動が変われば、習慣が変わる。
習慣が変われば、人格が変わる。
人格が変われば、運命が変わる」。
―――これは、星稜高校野球部の部室に張ってある指導書きです(ヒンズー教の言葉と言われる)。米国メジャーリーグで活躍したゴジラこと松井秀喜さんは、野球人として第一級のプロフェッショナルに成長しましたが、その過程には、高校の野球部監督であった山下智茂氏から受けたこの言葉の影響が大きくあったといいます(松井秀喜著『不動心』より)。
いまの職場に知識や技能を教える人はいても、哲学を与えてくれる人は少ないものです。かく言う私も講師として独自の哲学を与えることはできないかもしれません。しかし、古今東西の哲人たちの「強く深き」言葉を紹介することはできます。受講者の一人一人が、具体的にどの言葉に響くかはわかりません。ただ、ひとつでも多くの言葉を耳に入れておいてあげたいと思っています。あるときに聞いたたったひとつの哲学的な言葉が、人間を根本から変え、生涯にわたって彼(女)を支えることは珍しくありません。
* * * * *
入社3年~5年次におけるフォローアップ研修をどんな内容でやるかを考えるとき、さまざまなことが考えられるでしょう。私はこのときこそ、同期入社が集って、働くことの根っこを考え合い、観・マインドを醸成する場にすることがよいと思っています。
いずれにしても、ビジネス社会のスピードが増し、複雑化するにつれ、働く人びとの手(=技術)やアタマ(=知識)は大きくなっています。けれども、心や肚はおざなりになっています。そのことが、働く人びとの漂流感や不安感、倦怠感、あるいは、不正や不祥事などモラルハザードの問題として陰を落としているようにも思えます。また、深い次元でのやる気・動機が起きてこないという問題にも通じています。
「働くこと」についての観・マインドの醸成教育は、業務課題に対する即効的な効果を生むものではありません。しかし、個々の仕事・キャリアにおいて、そして組織全体の強さにおいて、根本的な効果を及ぼすものです。
*セミナー終了しました
** 人事・人財育成ご担当者向けセミナー開催のご案内 **
下記の単独セミナーを開催いたします。
「観・マインド」を醸成する研修に関心のあるご担当者はぜひご参加を検討ください。
■「観・マインド」をつくる人財育成研修の導入
~知識・スキル習得を超えて自律的な意識基盤を醸成する教育とは?
■日時:2015年5月14日(木)13:30~15:10
■場所:コンファレンス東京(東京・新宿)
■参加料:無料
■定員:先着15名(1社複数名のご参加可能)
■講師:村山 昇(キャリア・ポートレートコンサルティング 代表)
■対象者:
・全社の人事部門で人財育成を担当される方
・事業部/カンパニーの人事部門で人財育成を担当される方
*本セミナーは、人財育成にかかわる研修委託の検討材料にしていただく内容です。一般ビジネスパーソン向けの自己啓発セミナーではございません。
■ご担当者の課題意識として:
・新入社員向けの研修は基本技術やマナー習得だけでいいのだろうか
・入社3年目フォロー研修に「自律マインド」醸成の内容を施したい
・20~30代前半までの若年層社員の就労意識を活性化させるための任意研修を考えたい
・中間管理職向けに「意味・価値」次元からの部下との対話力を向上させたい
・シニア世代(50代以降)社員にもうひとふんばりしてもらうための意識強化研修を考えたい
・恒常的に「働くとは何か?」を考えさせる学びの場を社内に設けたい
……これらの課題に対し、導入事例を紹介しながらご説明する予定です。
→ 詳細・申し込みはこのサイトからどうぞ (ここをクリックしてください)
* * * * * * * * * * * * * * * *
組織における「ヒトづくり・人財育成」を考えるときに、ヒトの何を鍛え、育むのか。それを比喩的に言うなら、
「頭」=知識であり、
「手」=技能であり、
「足」=行動力です。
そのための社内研修や社外セミナーのプログラムは世の中にたくさんあります。
しかしながら、
「肚(はら)」=仕事観・就労マインドを醸成したり、
「胸」=志を育んだりする教育プログラムはあまり多くありません。
個々の肚や胸は、価値観の次元に踏み込む領域であり、組織側がとやかくできる問題ではない。価値観は多様化しているのだから教育の施しようがない、と考えられているからかもしれません。
しかし考えてみれば、ほんとうに個々が自信を持って躍動し、強い製品を生んでいる企業というのは、個と組織が同じような観を共有して求心力を持っているところではないでしょうか。社会全体としては価値観は多層・多様であっていいのでしょう。ですが、同じ事業船に乗り合わせた企業のメンバーたちにとっては、むしろある層の観を共有しながら、その上で多様な観にもとづくアイデアを放ち合うというのが理想ではないでしょうか。
個々の働く人びとが「強い肚」と「強い胸」を持って、知識や技術、行動力を真に生かしていく。組織と観を共有していく。今回、そんな肚と胸にかかわる研修プログラムの導入について、みなさまと意見交換するためのセミナーを開催いたします。ご参加をお待ちしております。
今年も新入社員を迎える季節がやってきました。新入社員研修も始まります。会社の人事部門としては、とにかく必要最小限のスキル&マインドを整えて、配属現場に送り出さねばなりません。私は主に「観・マインド」を醸成する研修プログラムをつくっていますが、本稿ではその観点から、入社から半年後くらいのタイミングで行うフォロー研修について書きたいと思います。
◆自信喪失・ミスマッチ感をどうフォローするか
新入社員たちが最初の研修を終えて配属現場に散り、半年くらい経ったとき、どんな点をフォローアップしていくか、それはさまざま考えられます。私は彼らを観察していて、次の3つの点にフォローが必要だと感じています。それは───
1)「自信喪失感」へのフォロー
2)「ミスマッチ感」へのフォロー (ここを中心に書きます)
3)「自立から自律への意識醸成」のフォロー (本稿では割愛します)
1つめのフォローについて。半年後、新入社員たちの少なからずがさまざまに自信をなくし、落ち着かない気持ちでいることでしょう。先輩のようにてきぱきと仕事がこなせない。社外とのやりとりで緊張しすぎてしまう。電話を取るのが怖い。失敗を恐れるあまり能動的に動けない。上司との人間関係がうまくつくれない……など、アンケートではいろいろと不安を訴える声が出てきます。
これに対しては、個別の面談と、OJTではまかないきれない追加の技術研修、例えばコミュニケーション研修やプレゼンテーション研修、フォロワーシップ研修などの対応があります。実際、現況のフォロー研修はこのようなメンタルケアの面談とスキル補強型が中心となっています。
2つめは「ミスマッチ感」へのフォローです。半年間、実際に仕事をやってみると、入社前の期待や理想と、現実の仕事内容や職場の雰囲気にギャップが生じ、それが不整合感や違和感となって表れます。配属が希望と異なっていた人であれば、なおさら「ミスマッチだ」となりますし、希望どおりに配属された人でも、「ひょっとしたら自分は場違いな会社を選んでしまったのかも」と感じはじめます。
ミスマッチは彼らにとって誘惑の言葉です。ミスマッチという理由づけによって、辛抱づよくその与えられた場で能力を開いていく努力を脇に置いて、ある種、自己肯定してしまえるからです。「自分には潜在能力はあるが、ミスマッチだから開けないだけなんだ。環境を変えればなにかが起こるはず」と。そして、ゲームのリセット感覚で転職を考える人も出てきます。特に景気が好転し、人手不足が顕著になると、第二新卒採用の案件は増加するのでなおさらです。
こうしたミスマッチ感による心の揺らぎは、半年後のタイミングから、その後1年も2年も続き、拡大することも起こります。大卒入社の3割が3年以内に離職するという現象は、このこととつながっています。入社3年目に次の大きなフォローアップ研修を施すところが多いですが、20代の彼らにとって、その揺らぎの1年間、2年間はとても長い。ですから、新入社員のフォロー研修は、彼らのその後の数年先まで見据えたプログラムが必要だと留意すべきです。
私はこうしたときこそ「観・マインド」にはたらきかけることが重要だと考えます。「観・マインド」とは、思考や感情、記憶をつかさどる精神性で、単純には、ものの見方・とらえ方、意識基盤といったものです。
観はだれの内にもすでになにかしらが醸成されています。ただ、その分厚さや堅固さ、向きは異なります。学生から上がったばかりの新入社員たちの多くは当然、観がぜい弱(未醸成)です。入社から半年経った彼らが、多少の違和感を「これはミスマッチだ」と考えてしまうのも、(忍耐力の欠如というより)観のぜい弱さによるものです。
ですから私が新入社員向けのフォロー研修で行うのは、観醸成を促し、一段深いところにもぐってものごとを見つめさせる訓練をすることです。この次元の教育によって、彼らの意識基盤をつくり、自律的に行動を抑制したり、促進したりします。本稿では、私が行っている具体的な方法を2つご紹介します。1つは「概念化して肚に落とすワーク」、もう1つは「分厚い観から出た言葉を提示すること」です。
◆仕事観・能力観・プロフェッショナル観を養うワーク
まず「モザイク作文」というゲームワークです。
〈ワーク1回目〉
□受講者に、「海」「幸福」「夏の日」「中華料理」「甘い」と印刷してある5枚のカードを配ります。
□次に、講師はホワイドボードに大きく「机」と書きます。
□そして課題作業を告げます。───「カードに記された5つの単語を盛り込んで(順番は自由)、ホワイトボードに書いてある「机」に物語が帰結するよう作文してください。時間は10分間」
受講者はあれこれカードの順番を入れ替えながら、なんとか「机」にたどり着くように作文を始めます。たとえば、回答はこのような感じになります───
【出てきた作文例:Kさん・女性】
「桜の花が『甘い』香りを放つ4月、私たちは入学した。みんなで『海』に行き、大騒ぎをした後、横浜に立ち寄って本格的な『中華料理』に舌鼓を打った。そんな『夏の日』もまるで昨日のよう。そして秋が過ぎ、冬が過ぎた。『幸福』な思い出をいっぱい詰め込んで、きょう、私はこの教室、この『机』ともお別れだ」。
各自が書いた作文をグループで披露しあいますが、いろいろと名作・珍作が出て盛り上がります。それで次のワークです。
〈ワーク2回目〉
□作業内容は同じです。さきほどの手元にある5つの単語を盛り込んで作文します。
□ただ、帰結ワードを変えます。講師は「クルマ(車)」とホワイトボードに書きます。
【出てきた作文例:Tさん・男性】
「『中華料理』の丸テーブルを囲みながら、きょうは我が家の家族会議だ。今年の『夏の日』の旅行は何処に行こうか。『海』にも行きたい、山にも行きたい。温泉にも浸かりたい、キャンプもしたい。そんな『幸福』プランはいろいろ出てくる。しかし、現実はそんなに『甘い』ものではなかった。なぜなら我が家は先月、『クルマ』を売っ払ったばかりだった(凹む)」。
帰結ワードががらり変わっても、受講者はたいてい見事に作文をこしらえることができます。人によっては1回目とまったく異なった感じで作文する人もいれば、1回目と同じような路線でシリーズ化する人もいます。さらに、ワークを続けます。
〈ワーク3回目〉
□作業内容は同じです。手元にある5つの単語を盛り込んで作文します。
□帰結ワードを変えます。講師は「夕焼け」とホワイトボードに書きます。
□さらに1点、要件を加えます。───「作文はサトシ君(中学3年生)に贈るものです。サトシ君は、高校受験の前日に交通事故にあって大けがをしてしまい、入院1週間目です。第一志望校の受験も見送らざるをえませんでした。ベッドで元気をなくしています」。
さて、1,2回目のワークでは単純に作文すればよかったのが、3回目ではそれをやることの意味が加わりました。受講者は考えを巡らせます。どういう物語でサトシ君を励ませられるのかと。たとえば、このような作文が出てきます。
【出てきた作文例:Hさん・男性】
「光太郎は小さな島を飛び出て一流の『中華料理』人になるために、東京の名店で修行を重ねた。そしていよいよ独立して東京に店を出した矢先、火事を起こしてしまい、店は全焼。莫大な借金だけが残った。光太郎は生まれ故郷の島に戻り、『海』を見つめていた。人生、そんなに『甘い』ものではないな、と。でも、命をなくしたわけじゃない。どうにだってやり返せる。この絶望の先に『幸福』はあるはず。『夏の日』の『夕焼け』が水平線を赤く染めていた」。
サトシ君への励まし作文はいろいろと出てきます。上の作例のように希望を持つかぎり頑張れるというメッセージを込めた内容のものもあれば、なにかオチのあるおもしろい小話を作って気分を明るくさせるものも出てきます。
さて、この単純な3回の作文ワークによって、入社半年後の受講者に何を学んでもらうことができるのでしょうか? 何の「観」を醸成することができるのでしょうか───?
私が意図するのは次の2点です。
1)能力をひらく能力=「メタ能力」の重要性
2)「優れた組織内プロフェッショナル」観の醸成
◆「メタ能力」とは
メタ能力の「メタ(meta)」とは「高次の」という意味です。たとえば心理学の世界では、「メタ認知」という概念があります。メタ認知とは、認知(知覚、記憶、学習、思考など)する自分を、より高い視点から認知することです。たとえば、何かスポーツをしているときに、実際にグランドに立ってプレーしている自分がいると同時に、試合全体を上から俯瞰し、自分を含め戦う相手や観客などを観察し、プレーする自分に指示を送る自分がいます。この俯瞰でみている意識のはたらきが「メタ認知」というわけです。
それと同じように、自分が持つもろもろの能力を、一段高いところから統合して成果に結び付ける能力をここで「メタ能力」と呼びます。
【Ⅰ次元能力】能力をもろもろ保持し、単体的に発揮する
「〇〇語がしゃべれる」「数学ができる」「記憶力が強い」「幅広い教養がある」、「文章力が優れている」「表計算ソフト『エクセル』の達人である」、「〇〇の資格を持っている」「運動神経が鋭い」「論理的思考に長けている」───これらは単体的な能力、素養としての能力です。これらを発揮することをⅠ次元の能力があるととらえます。
新入社員の多くは、こうしたⅠ次元能力を自己の強みとして就活でアピールし、採用もされたので、その延長線上で配属されるだろうことを(一人勝手に)思っています。つまり───
・「私は語学力が買われた。だから海外折衝の部門に配属されるはず」。 →でも、国内支社の購買部に配属された。意欲ダウン
・「私は広告研究会でコピーを何本も書いてきた。その能力で採用されたにちがいない。だからクリエイティブな仕事のできる部署に配属されるはず」。 →ところが、体育会的な営業部に配属された。意欲ダウン
会社では往々にしてこのような配置があるわけですが、これを彼らがミスマッチだとして意欲の低下や安易な転職につながらないようにするために、会社側は新入社員たちに対して、メッセージを発しておくことが必要です。すなわち、「あなたがたの採用はⅠ次元能力を見込んでのことではない。Ⅱ次元能力・Ⅲ次元能力こそ、会社が期待するものである」と。
【Ⅱ次元能力】能力を“場”にひらく能力
私たちは仕事をするうえで、能力を発揮する「場」というものが必ずあります。たとえば、営業部で働いているとすれば、その営業チームという職場、営業という職種の世界、そして事業が属する市場。一般社員であるか管理職であるかという立場。これらが「場」です。そして場はそれぞれに目標や目的を持っている。
私たちは、もろもろに習得した知識や技能(=Ⅰ次元能力)を、さまざまに編成して「場」に成果を出そうと努める。このⅠ次元能力を一段上から司る能力が、Ⅱ次元能力であり、ここで「メタ能力Ⅱ」と名付けるものです。
【Ⅲ次元能力】能力と場を“意味”にひらく能力
さらに言えば、もろもろのⅠ次元能力を自在に組み合わせ、場の要請に応じて成果を出し、ある大きな意味・事業理念を満たしていく(そのために新しい能力を積極的に獲得したり、場をも変えていったりする)能力が、Ⅲ次元能力/メタ能力Ⅲです。
さきほどの「モザイク作文」が、まさにこのメタ能力という概念を肚に落とすためのワークです。つまり、5枚のカードは自分が持つ単体の能力(Ⅰ次元能力)です。そして講師がホワイトボードに書く帰結ワードは、場が与えるミッションです。そのミッションをかなえるべく、5つの能力素材を組み合わせて、自分なりの成果物(=作文表現)を出す。自分の得意で好きなⅠ次元能力の延長に業務があるのではない。会社という事業組織においては、必ず「場」(職場・市場・立場)からの要請・需要があって、それに応える形で成果を出していく。それが「会社という舞台で仕事ができる人」であり、「優れた組織内プロフェッショナルの姿」なのだ、というマインドセットに通じていくワークです。
そういう仕事観・能力観・プロフェッショナル観を会社側が発信していかねば、いつまでも彼らは「会社はやりたいことをやらせてくれない」とか「ミスマッチだ」などの感情に傾きやすく、組織にとっても個人にとってもハッピーでない状態に陥るリスクが継続します。
「単に~ができる」というⅠ次元能力を超えて、どんな部署に配属されようと、どんな業務命題を与えられようと、そこで成果を出し、大きな意味のもとに自分をひらいくメタ能力に優れた組織内プロフェッショナルに育っていってほしい───そのメッセージを研修プログラムに込めて伝えるのが、新入社員フォロー研修の大きな目的になりえるのではないでしょうか。
◆分厚い観から出た言葉を差し出す
知識や技術は伝授や植え付けが可能ですが、観やマインドはそうした一方的な教え込みはできません。あくまで、ある観を示し、それによる影響や感化によって本人の内の醸成を促すことができるのみです。研修でさまざまなワークや講義を行った後に、私が届ける言葉はたとえば次のようなものです───
「最初の仕事はくじ引きである。
最初から適した仕事につく確率は高くない。
得るべきところを知り、向いた仕事に移れるようになるには数年を要する」。
───ピーター・ドラッカー(経営学者)
「下足番を命じられたら、
日本一の下足番になってみよ。
そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ」。
───小林一三(阪急グループ創設者)
「小さな役はない。小さな役者がいるだけだ」。
───(演劇の世界での言葉)
「人生とは10パーセントの我が身に起こること、
そして90パーセントはそれにどう対応するかだ」。
───ルー・ホルツ(米・アメリカンフットボールコーチ)
「転職は、今いる会社で実績を積み、“伝説”をつくってからでも遅くはありません。
いや、実績を積んだときはじめて、転職するもしないも自由な身になれるのです」。
―――土井英司『「伝説の社員」になれ!』
こうした言葉の含蓄を彼らがどこまでそしゃくできるかはわかりません。しかし、耳に入れておくのとそうでないのとでは大きな違いが生まれます。こうした下地があれば、この先、彼らが遭遇する出来事から、「あ、あのときのワークはこういう意味があったのか! あの言葉の本質はこれだったのだ!」という気づきが起こりやすくなります。そしてそのときの意識変化、行動変化は根本的なものになるでしょう。「観・マインド」醸成の教育とはこうした中長期わたってじわりと効いていく類のものです。
昨今、人事担当者の間では社員を「自律的」に育てたいということがよく言われます。この「自律」とは何でしょう。“律”とは規範やルールです。つまり、自らの規範やルールに基づいて判断、行動できることが自律ということです。自らの規範やルールを内面に打ち立てるには、そもそもその根っことなる価値基軸や観がしっかりなければなりません。ですから、自律的な人材の育成には、観の醸成教育を避けて通ることはできません。
と同時に、そこでは組織側の観も問われることになるでしょう。一体全体、会社はどんな就労観、事業観、人材観、キャリア観、社会観を持って事業を推し進めようとするのか。そこをていねいに発信し、社員と共有しようとすることが会社にも求められます。「観は人それぞれ多様だから、縛ることはよくない」というのは、社会全体には言えることですが、こと事業体にあっては、むしろ観を共有できる人が集まって、強い思いの製品・サービスをつくるほうが望ましい姿といえます。共有できる理念・バリュー・文化が土壌としてあって、その上に多様で強力なアイデアが出る。昨今、顧客に強く支持される企業の共通点はそういったところにありはしないでしょうか。
いずれにしても、新入社員に対し、技術習得や知識獲得とは別に、意味・価値次元からものごとを考える機会を、内面の揺らぎの大きい20代にこそ豊富に与えるべきだと思います。「観・マインド」の醸成や共有は、しかるべきタイミングを逃すと、人の内面の土壌は固まってしまい、後からの教育はなかなかうまくいきません。新入社員をけっして子ども扱いせず、真正面から「観・マインド」を見つめさせる問いを投げかけていいのではないでしょうか。
* * * * * * *
【関連記事】
●3つの「テンショク」~展職・転職・天職
●新社会人に贈る ~力強い仕事人生を歩むために
陽光きらめく春。このたび社会人となり、職業を持つみなさん、おめでとうございます。これから何十年と続く仕事人生の出発にあたり、次の2つのことをお伝えしたいと思います。
1)「働くこと」は深く応えてくれること梵鐘のごとし
~あなたは鐘を割り箸でたたきますか、丸太でたたきますか
2)「働くこと」はおおいなること山のごとし
~「登山型キャリア」と「トレッキング型キャリア」
◆目の前の仕事にどれだけ「強く」当たれるか
まず1点めです。「職・仕事・働くこと」は梵鐘のようなものである───いきなりそう言われてもピンとこないかもしれませんが、私は若手社員の研修でよくこの比喩を用います。
働くことは、ほんとうに奥深い人間の営みです。私たちは、職・仕事を通して、無限大に成長が可能ですし、またそこから無尽蔵に喜びや感動を引き出すことができます。それはあたかも、働くことがお寺に吊してある大きな鐘のようなもので、丸太で力一杯しっかりとたたけば、ゴォーーンと深い音で鳴ってくれることに似ています。
ところが本来そんな深い音を鳴らす鐘であっても、割り箸のような木でちょこちょことたたいたならどうでしょう。チン、チーン、カラン、カランと、鍋ややかんをたたいているくらいにしか鳴りません。要は、鐘が深く味わいのある音を鳴らすのも、浅く軽い音を鳴らすのも、すべてはたたき方しだいということです。
みなさんはこれから緊張と高揚に包まれながら、スタートダッシュで懸命に仕事を覚えていくでしょう。おそらく、最初の半年や1年はすぐに経つと思います。そして2年が経ち、3年が経つころから、人によって差が出てきます。どういう差かというと、仕事という梵鐘をどんどん大きく鳴らすことができ、働くことの面白さや奥行きの広さを知っていく人と、仕事ってしょせんこんなものかと言って、働くことに対し強く当たることをやめてしまう人との差です。後者の人たちは、当然、梵鐘の鳴らす深い音を聴くことはありません。
働くという梵鐘は目に見えません。ここがとても重要な点です。もし働くという梵鐘が立派で大きな形として見えているものであれば、だれしも丸太でたたいて、よい音を鳴らせてみせようとがんばることができます。ところが実際は、働くことがどれほどの大きさなのか、そしてどれほどのものを自分に返してくれるかはわからない。一生懸命たたいたとしても、いい音が鳴らないかもしれないし、即座に反応してくれないときもある。仕事が自分の期待どおりに進むことは少なく、「なんでこうもうまくいかないんだ」と落ち込むことは頻繁に起こります。そんなとき、鐘にケチをつけるのは筋違いです。それは梵鐘の問題ではなく、あくまでたたくほうである私たち一人一人の問題なのですから。
みなさんの職業人生はこれから何十年と続きます。けっして短気を起こさず、地道に能力を身につけ、意志を強く育み――すなわち、それが丸太を担ぎ、鐘をたたけるような力を持つということ――、目の前の仕事にひとつひとつ当たっていってください。すると中長期的には必ず思いどおりの音が鳴り響くようになるはずです。そしてその深く遠くまで響く音は、周囲の人にもよい影響を与えるものになるでしょう。
◆「10年後どうなっていたいか?」という質問に答えられなくてもよい
2つめの話に移ります。私は入社3年~5年目くらいの若手社員にキャリア研修を行っています。すると、少なからずの人たちから「いまの会社・いまの仕事で何を目指していけばよいのかわからない……」といった声が漏れ聞こえてきます。
就職活動のときは、あれほど志望動機を考えたはずなのに、いざ入社してみると、仕事の内容や会社の様子が実は思っていたものと全然違ったものであったり、あるいは予想外のところに配属されたりして、でも、ともかく目の前の仕事をこなすことにてんてこ舞いになる。そして働き始めて数年も経てば、当初の志望動機は知らずのうちに消え去ってしまっていて、「あれ、自分はこの会社でいったい何をしたいんだろう?」となる。
たぶん、これを読んでいるみなさんの中にも、入社して数年後にはそうやって悩む人が出てくるでしょう。そんなときのために、キャリア形成には2つのタイプがあることをお伝しておきましょう。
◆頂を目指す「登山型」/穏やかに回る「トレッキング」型
もし、あなたが職業人として一心不乱に没頭できるキャリア上の目標像・到達点が確固とあり、そこに邁進しているのであれば、それはとても幸福な働き人です。どんどん突き進めばよい。しかし、世の中には、そういった明確な目標が見出せない人のほうが圧倒的に多いものです。特に会社員の場合は、自分の配属は自分で決めることができず、中長期の目標を見出しづらい存在です。しかし、このことにめげる必要はまったくありません。山の楽しみ方に、「登山」と「トレッキング」というタイプがあるように、キャリアにもこの2つのタイプがあるからです。
登山の場合、目標はただ一つ「登頂」です。その結果を得るためにあらゆる努力をしていく。頂を目指す途中、道草はしない。
つまり、「登山型のキャリア」とは、「プロ野球選手になってホームラン王をとる!」とか「弁護士になって多くの人を助けたい!」、あるいは「新薬開発の先進企業に入ってガンの治療薬をつくりたい!」「この会社でNo.1の営業マンになる!」などのように、唯一絶対の頂上を決めて脇目も振らずそこを目指すキャリアです。
他方、トレッキングの場合は、登頂のように明確な目標をあらかじめ掲げるわけではありません。山の中を回遊して、何か自分のお気に入りの場所を探すというその活動自体を楽しみにするものです。途中でたまたま見つけた滝や池が気に入れば、しばらくそこにたたずんでその居心地を楽しめばいいし、道端に咲く植物をいろいろと観察しながら時間をかけて歩くのもいいでしょう。そうした過程で山の奥深い細かなものがさまざま見えてくる。
すなわち、「トレッキング型」のキャリアは、「自分は絶対ここを目指すぞ」というような目標は思い浮かべていない(浮かべられない)けれども、会社内でいろいろな部署を経験したり、場合によっては転職したりして、働く環境を変えつつキャリアを形成していくスタイルです。あるときは営業現場で商品を売ることの楽しみや苦労を知ったり、あるときは企画部門で新しいアイデアを打ち出すことの奥深さや大変さを知ったり。また、業界を越えて転職したときなどは、業界ごとで仕事に対する考え方がこんなに違うんだ、と感じることもあるかもしれません。
そうしてトレッキングを続けていくと、しだいに山のことがわかってきて、体力や技術もついてくる。すると自分の登りたい山が見えてきて、その頂上に挑戦したいなと思えるときがやってくるかもしれない。そのときが「登山型キャリア」への転換点です。ですから、「いま何を目指してよいかわからない」という人に対し私は、あせらずトレッキングを楽しむことでいいのではと答えています。
私自身も、20代、30代はトレッキング型でした。メーカーや出版社など数社を渡り、さまざまな仕事を経験しました。そして40代になって、人財教育事業という山がすーっと見えたのです。「これをライフワークにしたい。この道を自分なりに究めたい」と思い、独立しました。だから、いまはどっぷり登山型のキャリアです。私がいま見つめている頂上は、「働くとは何か?の第一級の翻訳者になる!」「100年読まれ続ける本を著す」です。そこを目指し、日々、険しい岩斜面にはいつくばって一歩一歩登っています。
登山型とトレッキング型とで、どちらがよいかわるいかという問題ではありません。人それぞれでいいと思いますし、一人の人間の中でも人生の状況によってどちらを選ぶかが変わってきます。ただ、ハイリスク・ハイリターンという意味では、登山型は危険が大きい分、達成したときの喜びも成長も大きいといえます。そして何より自分の強い意志で見出した頂上を目指すわけですから、人生の醍醐味がそこにはあります。
いずれにせよ、働くことという山は巨大で奥深く、さまざまな楽しみも試練も内包しています。登っても登っても、歩いても歩いても、そこから得るものには限りがありません。みなさんはいよいよこの山の中に入っていきます。おおいに山に育んでもらってください。
では、みなさんお一人お一人のご活躍を期待しています。いつかどこかでお会いしましょう!
* * * * *
【過去の記事】
〇新社会人に贈る2014 ~仕事は「正解のない問い」に自分なりの答えをつくり出す営み
〇新社会人に贈る2013 ~自分の物語を編んでいこう
〇新社会人に贈る2012 ~キャリアは航海である
〇新社会人に贈る2011~人は仕事によってつくられる
〇新社会人に贈る2010 ~力強い仕事人生を歩むために